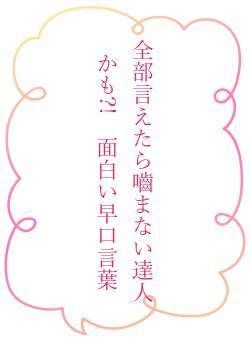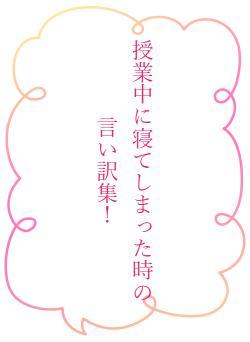談話室の奥のソファに腰を下ろすと、奏希くんのお母さんは優雅な所作でカップを手に取り、お茶をひと口含んだ。
律歌は緊張しながら、その言葉を待つ。
「奏希のことで、お礼を言いたくて」
「お礼……?」
律歌が目を瞬かせると、お母さんは柔らかく微笑んだ。
「あなたが奏希に、ピアノを弾く楽しさを思い出させてくれたこと。本当に感謝しているの」
「そんな……私はただ、教えてもらっていただけで……」
「いいえ。あの子が久しぶりに心から楽しそうにしているのを見て、私も嬉しくなったのよ」
律歌の胸がじんわりと温かくなる。
奏希くんにとって、少しでも支えになれていたのなら――それだけで嬉しかった。
けれど、お母さんはふと表情を曇らせた。
「……でも、正直に言うと、不安でもあるの」
律歌は思わず息をのむ。
「奏希はね、小さい頃から強がりで、誰にも弱音を吐かない子だったの。
でも、今のあの子は、あなたに対してだけは少し違う。あなたの前では、素直になれるみたい」
「奏希くんが……?」
信じられない気持ちで聞き返すと、お母さんはそっと頷いた。
「ええ。だからこそ、あなたにお願いがあるの」
律歌は真剣な眼差しで、お母さんを見つめる。
「……お願い?」
「どうか、奏希を支えてあげてちょうだい。最後まで、あの子のそばにいてほしいの」
その言葉に、律歌は息をのんだ。
奏希くんの余命は、あと半年。
彼が今、どんな気持ちでいるのか、律歌にはまだ完全には理解できていないかもしれない。
けれど――。
「……はい」
律歌はまっすぐお母さんを見つめ、力強く頷いた。
「私、奏希くんと一緒にいたいです。彼のために、できることを全部したい」
お母さんは少し驚いたような表情をしたあと、微笑んだ。
「ありがとう、律歌さん」
優しく細められた目元を見て、ようやく律歌は自分の緊張がほぐれていくのを感じた。
そして、改めて思う。
――私は、奏希くんが好きだ。
だから、彼のためにできることを、全部したい。
その決意を胸に、律歌はゆっくりと席を立ち、病室へ向かった。
律歌は緊張しながら、その言葉を待つ。
「奏希のことで、お礼を言いたくて」
「お礼……?」
律歌が目を瞬かせると、お母さんは柔らかく微笑んだ。
「あなたが奏希に、ピアノを弾く楽しさを思い出させてくれたこと。本当に感謝しているの」
「そんな……私はただ、教えてもらっていただけで……」
「いいえ。あの子が久しぶりに心から楽しそうにしているのを見て、私も嬉しくなったのよ」
律歌の胸がじんわりと温かくなる。
奏希くんにとって、少しでも支えになれていたのなら――それだけで嬉しかった。
けれど、お母さんはふと表情を曇らせた。
「……でも、正直に言うと、不安でもあるの」
律歌は思わず息をのむ。
「奏希はね、小さい頃から強がりで、誰にも弱音を吐かない子だったの。
でも、今のあの子は、あなたに対してだけは少し違う。あなたの前では、素直になれるみたい」
「奏希くんが……?」
信じられない気持ちで聞き返すと、お母さんはそっと頷いた。
「ええ。だからこそ、あなたにお願いがあるの」
律歌は真剣な眼差しで、お母さんを見つめる。
「……お願い?」
「どうか、奏希を支えてあげてちょうだい。最後まで、あの子のそばにいてほしいの」
その言葉に、律歌は息をのんだ。
奏希くんの余命は、あと半年。
彼が今、どんな気持ちでいるのか、律歌にはまだ完全には理解できていないかもしれない。
けれど――。
「……はい」
律歌はまっすぐお母さんを見つめ、力強く頷いた。
「私、奏希くんと一緒にいたいです。彼のために、できることを全部したい」
お母さんは少し驚いたような表情をしたあと、微笑んだ。
「ありがとう、律歌さん」
優しく細められた目元を見て、ようやく律歌は自分の緊張がほぐれていくのを感じた。
そして、改めて思う。
――私は、奏希くんが好きだ。
だから、彼のためにできることを、全部したい。
その決意を胸に、律歌はゆっくりと席を立ち、病室へ向かった。