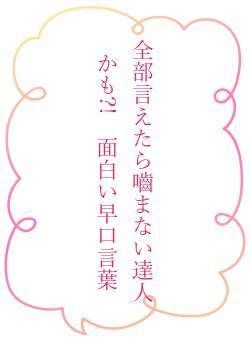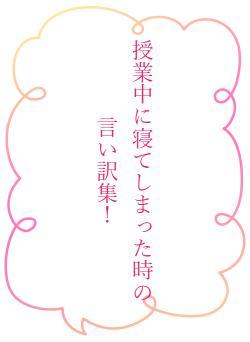律歌の涙をそっと拭いながら、奏希くんは静かに微笑んでいた。
その手の温もりは優しくて、それなのにどこか儚げで――律歌はまた涙が零れそうになる。
「奏希くん……」
震える声で名を呼ぶと、奏希くんは少し照れくさそうに目を伏せた。
そして、ゆっくりと息を整えながら、もう片方の手でも律歌の手を包み込む。
「……律歌」
掠れるような声が、静かな病室に落ちる。
「僕も……君のことが、好きだよ」
その言葉が耳に届いた瞬間、律歌の胸がぎゅっと締めつけられた。
「え……?」
驚きと喜びが入り混じり、言葉が出てこない。
奏希くんは、まっすぐに律歌を見つめていた。
「最初に君を見たとき……君のピアノの音に、どこか懐かしさを感じたんだ。
僕はずっと、ピアノは“技術”で魅せるものだと思ってた。でも、君の音は違った。
すごく優しくて、まるで心に沁み込んでくるような――そんな音だった」
律歌は息をのむ。
「でも、君はその音を閉じ込めてしまっていた。だから……もう一度、心から楽しいって思いながら、ピアノを弾いてほしかった」
奏希くんの言葉が、律歌の心の奥深くに染みわたる。
「最初は、それだけだった。でも……君が一生懸命にピアノに向き合おうとする姿を見て、どんどん惹かれていった。
君はきっと、自分では気づいていないけど、本当に努力家で、誰よりも優しくて……すごく純粋なんだ」
奏希くんは微笑む。
「そんな君を見ているうちに、気づいたら……好きになってた」
律歌の頬が熱を帯びる。
「でも……僕は、時間が限られてる。君とこうして一緒にいられる時間が、あとどれくらいあるのか分からない。
それが、すごく怖かったんだ」
かすかに震えた声が、律歌の胸を締めつける。
「だから、想いを伝えるのをためらってた。君を好きになればなるほど、君を悲しませることになるんじゃないかって……
でも、律歌が僕に気持ちを伝えてくれたことで、やっと決心がついたんだ」
奏希くんは、律歌の手をぎゅっと握りしめる。
「僕は……君のことが、本当に大好きだよ」
その言葉に、律歌の涙腺が再び緩む。
「奏希くん……」
涙が頬を伝っても、もう拭おうとはしなかった。
「私も、奏希くんが大好き……!」
そう言うと、奏希くんは安心したように微笑み、そっと律歌の頬に触れる。
「ありがとう……律歌」
病室の窓の外では、夕陽が優しく二人を包み込んでいた。
限られた時間の中で、それでも二人は互いの想いを確かめ合い、心を寄せ合う。
――どんなに短い時間でも、きっと、永遠よりも輝く日々になる。
律歌は、そう強く願った。
その手の温もりは優しくて、それなのにどこか儚げで――律歌はまた涙が零れそうになる。
「奏希くん……」
震える声で名を呼ぶと、奏希くんは少し照れくさそうに目を伏せた。
そして、ゆっくりと息を整えながら、もう片方の手でも律歌の手を包み込む。
「……律歌」
掠れるような声が、静かな病室に落ちる。
「僕も……君のことが、好きだよ」
その言葉が耳に届いた瞬間、律歌の胸がぎゅっと締めつけられた。
「え……?」
驚きと喜びが入り混じり、言葉が出てこない。
奏希くんは、まっすぐに律歌を見つめていた。
「最初に君を見たとき……君のピアノの音に、どこか懐かしさを感じたんだ。
僕はずっと、ピアノは“技術”で魅せるものだと思ってた。でも、君の音は違った。
すごく優しくて、まるで心に沁み込んでくるような――そんな音だった」
律歌は息をのむ。
「でも、君はその音を閉じ込めてしまっていた。だから……もう一度、心から楽しいって思いながら、ピアノを弾いてほしかった」
奏希くんの言葉が、律歌の心の奥深くに染みわたる。
「最初は、それだけだった。でも……君が一生懸命にピアノに向き合おうとする姿を見て、どんどん惹かれていった。
君はきっと、自分では気づいていないけど、本当に努力家で、誰よりも優しくて……すごく純粋なんだ」
奏希くんは微笑む。
「そんな君を見ているうちに、気づいたら……好きになってた」
律歌の頬が熱を帯びる。
「でも……僕は、時間が限られてる。君とこうして一緒にいられる時間が、あとどれくらいあるのか分からない。
それが、すごく怖かったんだ」
かすかに震えた声が、律歌の胸を締めつける。
「だから、想いを伝えるのをためらってた。君を好きになればなるほど、君を悲しませることになるんじゃないかって……
でも、律歌が僕に気持ちを伝えてくれたことで、やっと決心がついたんだ」
奏希くんは、律歌の手をぎゅっと握りしめる。
「僕は……君のことが、本当に大好きだよ」
その言葉に、律歌の涙腺が再び緩む。
「奏希くん……」
涙が頬を伝っても、もう拭おうとはしなかった。
「私も、奏希くんが大好き……!」
そう言うと、奏希くんは安心したように微笑み、そっと律歌の頬に触れる。
「ありがとう……律歌」
病室の窓の外では、夕陽が優しく二人を包み込んでいた。
限られた時間の中で、それでも二人は互いの想いを確かめ合い、心を寄せ合う。
――どんなに短い時間でも、きっと、永遠よりも輝く日々になる。
律歌は、そう強く願った。