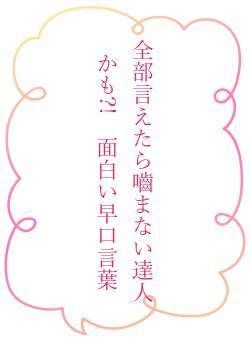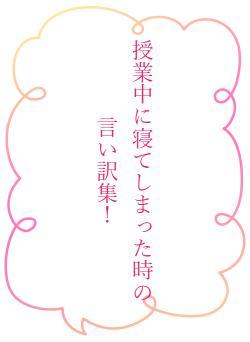病室の外、廊下の窓から差し込む夕陽が、淡い橙色の光を落としていた。
律歌は手すりに寄りかかり、震える指先で涙を拭った。
――半年。
たった半年しかないのに、奏希さんはあんなにも穏やかに受け入れていた。
「……っ」
胸が苦しくて、喉が詰まる。涙をこらえようとするほど、押し寄せる感情に飲み込まれそうだった。
「お姉ちゃん」
優しく肩に触れる感触。
振り向くと、響歌が立っていた。
「響……歌……」
泣き腫らした顔を見られたくなくて、律歌は俯こうとした。
でも、響歌はそっと律歌の手を取ると、そのまま廊下のベンチに座らせた。
「無理しなくていいよ。……泣きたいだけ泣けばいい」
その言葉に、律歌の涙腺がまた崩れる。
「だって……だって、半年しかないんだよ……? それなのに奏希さんは……っ、あんなに……」
言葉が詰まり、嗚咽がこぼれる。
響歌は黙って、律歌の背中を優しくさすった。
しばらくそうしていると、響歌がぽつりと呟いた。
「お姉ちゃんさ……奏希さんのこと、好きなんでしょ?」
「え……?」
涙の滲んだ瞳で響歌を見ると、彼女はまっすぐな目で律歌を見つめていた。
「気づいてないと思ってる? バレバレだよ」
くすっと笑いながら、響歌は続ける。
「お姉ちゃん、いつも奏希さんのことばっかり見てたもん。ピアノを教えてもらってるときも、すっごく楽しそうだったし……今だって、奏希さんのことが心配で仕方ないでしょ?」
律歌は息を呑んだ。
――そうだ。
私は、奏希さんが好きだ。
彼のピアノに憧れた。彼の優しさに救われた。
そして、彼のことを想って、こんなにも胸が締めつけられる。
「……でも」
律歌は膝の上で拳を握った。
「私が好きになったところで、奏希くんは……もう……」
半年後には――
「そんなの関係ないじゃん」
響歌はきっぱりと言った。
「お姉ちゃん、好きなら伝えなよ。今言わなきゃ、一生後悔するよ?」
その言葉が、律歌の心にまっすぐ響いた。
――今、伝えなきゃ。
――時間が限られているからこそ、私の想いを伝えたい。
「……私……」
唇を噛みしめ、震える声で律歌は呟いた。
「奏希さんに……気持ち、伝えたい……!」
響歌は微笑み、律歌の手をぎゅっと握った。
「うん。それでいいんだよ」
夕陽の光の中、律歌の決意が固まった。
――私は、奏希さんに告白する。
この気持ちを、全部伝えるんだ。
律歌は手すりに寄りかかり、震える指先で涙を拭った。
――半年。
たった半年しかないのに、奏希さんはあんなにも穏やかに受け入れていた。
「……っ」
胸が苦しくて、喉が詰まる。涙をこらえようとするほど、押し寄せる感情に飲み込まれそうだった。
「お姉ちゃん」
優しく肩に触れる感触。
振り向くと、響歌が立っていた。
「響……歌……」
泣き腫らした顔を見られたくなくて、律歌は俯こうとした。
でも、響歌はそっと律歌の手を取ると、そのまま廊下のベンチに座らせた。
「無理しなくていいよ。……泣きたいだけ泣けばいい」
その言葉に、律歌の涙腺がまた崩れる。
「だって……だって、半年しかないんだよ……? それなのに奏希さんは……っ、あんなに……」
言葉が詰まり、嗚咽がこぼれる。
響歌は黙って、律歌の背中を優しくさすった。
しばらくそうしていると、響歌がぽつりと呟いた。
「お姉ちゃんさ……奏希さんのこと、好きなんでしょ?」
「え……?」
涙の滲んだ瞳で響歌を見ると、彼女はまっすぐな目で律歌を見つめていた。
「気づいてないと思ってる? バレバレだよ」
くすっと笑いながら、響歌は続ける。
「お姉ちゃん、いつも奏希さんのことばっかり見てたもん。ピアノを教えてもらってるときも、すっごく楽しそうだったし……今だって、奏希さんのことが心配で仕方ないでしょ?」
律歌は息を呑んだ。
――そうだ。
私は、奏希さんが好きだ。
彼のピアノに憧れた。彼の優しさに救われた。
そして、彼のことを想って、こんなにも胸が締めつけられる。
「……でも」
律歌は膝の上で拳を握った。
「私が好きになったところで、奏希くんは……もう……」
半年後には――
「そんなの関係ないじゃん」
響歌はきっぱりと言った。
「お姉ちゃん、好きなら伝えなよ。今言わなきゃ、一生後悔するよ?」
その言葉が、律歌の心にまっすぐ響いた。
――今、伝えなきゃ。
――時間が限られているからこそ、私の想いを伝えたい。
「……私……」
唇を噛みしめ、震える声で律歌は呟いた。
「奏希さんに……気持ち、伝えたい……!」
響歌は微笑み、律歌の手をぎゅっと握った。
「うん。それでいいんだよ」
夕陽の光の中、律歌の決意が固まった。
――私は、奏希さんに告白する。
この気持ちを、全部伝えるんだ。