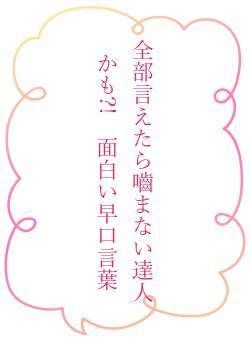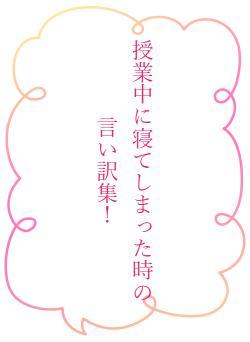最初の一音がホールに溶け込むと、静寂が優しく空間を包み込んだ。
律歌の指が鍵盤をなぞる。
そっと、まるで風が頬を撫でるように。
高音の旋律が夜空に瞬く星のようにきらめきながら、静かに広がっていく。
それに寄り添うように、奏希さんの低音が重なる。
深く、温かく、まるで大地のようにしっかりとした音。
二つの音色が絡み合い、ゆっくりと一つの物語を紡ぎ始めた。
旋律が流れるたびに、律歌の心は軽くなっていく。
不安も迷いも、過去の傷さえも、ピアノの音に溶けて遠ざかっていくようだった。
今、ここにあるのはただ――奏でる喜び。
響歌との共演で痛んだ心も、もう揺らがない。
ピアノが、私を前へと進ませてくれる。
静かに始まった演奏は、次第に力強く、輝きを増していく。
流れるアルペジオは、水面を跳ねる光の粒のように舞い、
奏希さんの和音がそれを優しく包み込む。
二人の指先が呼応するたびに、音が生き物のように息づいていく。
優雅で繊細で、けれどどこか儚く――
まるで、夢の中を漂うような旋律。
奏希さんの音がそっと律歌を導き、律歌の音が奏希に寄り添う。
そして、クライマックスへと向かう瞬間。
律歌の指が鍵盤を駆け抜ける。
それに呼応するように、奏希さんの音も高鳴る。
まるで夜空に打ち上がる花火のように、壮大な音がホールを満たした。
客席が息を呑むのがわかる。
(もっと、もっと――)
心が震える。
まだ、この音を止めたくない。
けれど、曲はやがて終わりを迎えようとしていた。
静かな余韻がホールを包み、最後の和音がふたりの指から生み出される。
温かく、穏やかで、まるで微笑みのような音色。
それは――律歌が"ピアノを愛していた頃"の記憶を呼び起こす音だった。
そして。
最後の音が響き渡り、静寂が訪れる。
一瞬の沈黙のあと、客席から大きな拍手が沸き起こった。
まるで波のように押し寄せる歓声。
律歌はゆっくりと顔を上げた。
隣を見ると、奏希さんが穏やかに微笑んでいた。
彼の瞳には、まるで「おかえり」と語りかけるような優しさが宿っている。
(――私は、やっぱりピアノが好きだ)
そう、心の底から思えた。
律歌の指が鍵盤をなぞる。
そっと、まるで風が頬を撫でるように。
高音の旋律が夜空に瞬く星のようにきらめきながら、静かに広がっていく。
それに寄り添うように、奏希さんの低音が重なる。
深く、温かく、まるで大地のようにしっかりとした音。
二つの音色が絡み合い、ゆっくりと一つの物語を紡ぎ始めた。
旋律が流れるたびに、律歌の心は軽くなっていく。
不安も迷いも、過去の傷さえも、ピアノの音に溶けて遠ざかっていくようだった。
今、ここにあるのはただ――奏でる喜び。
響歌との共演で痛んだ心も、もう揺らがない。
ピアノが、私を前へと進ませてくれる。
静かに始まった演奏は、次第に力強く、輝きを増していく。
流れるアルペジオは、水面を跳ねる光の粒のように舞い、
奏希さんの和音がそれを優しく包み込む。
二人の指先が呼応するたびに、音が生き物のように息づいていく。
優雅で繊細で、けれどどこか儚く――
まるで、夢の中を漂うような旋律。
奏希さんの音がそっと律歌を導き、律歌の音が奏希に寄り添う。
そして、クライマックスへと向かう瞬間。
律歌の指が鍵盤を駆け抜ける。
それに呼応するように、奏希さんの音も高鳴る。
まるで夜空に打ち上がる花火のように、壮大な音がホールを満たした。
客席が息を呑むのがわかる。
(もっと、もっと――)
心が震える。
まだ、この音を止めたくない。
けれど、曲はやがて終わりを迎えようとしていた。
静かな余韻がホールを包み、最後の和音がふたりの指から生み出される。
温かく、穏やかで、まるで微笑みのような音色。
それは――律歌が"ピアノを愛していた頃"の記憶を呼び起こす音だった。
そして。
最後の音が響き渡り、静寂が訪れる。
一瞬の沈黙のあと、客席から大きな拍手が沸き起こった。
まるで波のように押し寄せる歓声。
律歌はゆっくりと顔を上げた。
隣を見ると、奏希さんが穏やかに微笑んでいた。
彼の瞳には、まるで「おかえり」と語りかけるような優しさが宿っている。
(――私は、やっぱりピアノが好きだ)
そう、心の底から思えた。