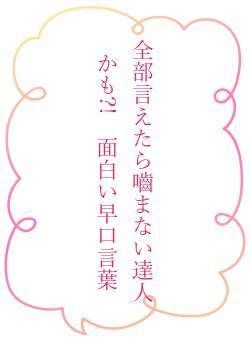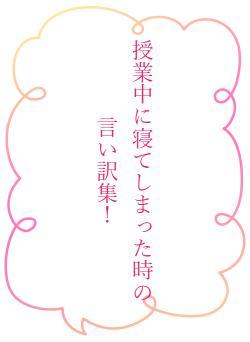静まり返ったピアノ室に、澄んだ旋律が響く。
律歌の指先は、鍵盤の上を滑るように流れ、奏希さんの隣で真剣な表情を浮かべていた。
今日は発表会前、最後のレッスン。
この数ヶ月間、奏希さんのもとで積み重ねた努力のすべてを音に込める。
――最後の音を弾き終え、そっと息をつく。
しんとした静寂が訪れた。
奏希さんは目を閉じたまま余韻に浸るように微動だにしない。
律歌は無意識に指を握りしめた。
(どうだったんだろう……?)
緊張が張り詰めた空気をまとったまま、奏希さんの言葉を待つ。
やがて、ゆっくりと目を開き、彼は小さく微笑んだ。
「……素晴らしかった」
その一言に、律歌の肩の力がふっと抜ける。
「本当に?」
「うん。今までで一番、良かった」
奏希さんはそう言って、律歌の手元を見つめる。
「音がすごく柔らかくなった。無理に完璧を求めるんじゃなくて、自然と曲と向き合えていたね」
律歌の胸がじんわりと熱くなる。
「奏希さんのおかげだよ。私、一人だったら、ここまで弾けるようにはならなかった……」
「違うよ。これは、律歌の力だ」
奏希さんはまっすぐに律歌を見つめた。
「僕は、ほんの少し背中を押しただけ。ここまで来られたのは、律歌が諦めなかったからだよ」
その言葉に、胸がぎゅっと締め付けられる。
(私、本当にここまで来られたんだ……)
数ヶ月前、ピアノをやめた自分が、またこうして鍵盤に向かっているなんて思いもしなかった。
そして――こんなにも誰かの言葉が、心の支えになるなんて。
律歌は、そっと奏希を見つめた。
「奏希さん、本当にありがとう」
すると、奏希さんは少しだけ困ったように笑った。
「ありがとうなんて、まだ早いよ」
「え?」
「明日が本番なんだから。ここで満足してたら、ダメでしょ?」
くすっと微笑む奏希さんの表情が、なぜか儚く見えた。
律歌はどこか胸の奥が痛むのを感じながら、小さく息を吐いた。
「……うん。明日、頑張る」
「うん。律歌なら、きっと大丈夫」
奏希さんの優しい声に包まれながら、律歌は明日への決意を胸に刻んだ。
律歌の指先は、鍵盤の上を滑るように流れ、奏希さんの隣で真剣な表情を浮かべていた。
今日は発表会前、最後のレッスン。
この数ヶ月間、奏希さんのもとで積み重ねた努力のすべてを音に込める。
――最後の音を弾き終え、そっと息をつく。
しんとした静寂が訪れた。
奏希さんは目を閉じたまま余韻に浸るように微動だにしない。
律歌は無意識に指を握りしめた。
(どうだったんだろう……?)
緊張が張り詰めた空気をまとったまま、奏希さんの言葉を待つ。
やがて、ゆっくりと目を開き、彼は小さく微笑んだ。
「……素晴らしかった」
その一言に、律歌の肩の力がふっと抜ける。
「本当に?」
「うん。今までで一番、良かった」
奏希さんはそう言って、律歌の手元を見つめる。
「音がすごく柔らかくなった。無理に完璧を求めるんじゃなくて、自然と曲と向き合えていたね」
律歌の胸がじんわりと熱くなる。
「奏希さんのおかげだよ。私、一人だったら、ここまで弾けるようにはならなかった……」
「違うよ。これは、律歌の力だ」
奏希さんはまっすぐに律歌を見つめた。
「僕は、ほんの少し背中を押しただけ。ここまで来られたのは、律歌が諦めなかったからだよ」
その言葉に、胸がぎゅっと締め付けられる。
(私、本当にここまで来られたんだ……)
数ヶ月前、ピアノをやめた自分が、またこうして鍵盤に向かっているなんて思いもしなかった。
そして――こんなにも誰かの言葉が、心の支えになるなんて。
律歌は、そっと奏希を見つめた。
「奏希さん、本当にありがとう」
すると、奏希さんは少しだけ困ったように笑った。
「ありがとうなんて、まだ早いよ」
「え?」
「明日が本番なんだから。ここで満足してたら、ダメでしょ?」
くすっと微笑む奏希さんの表情が、なぜか儚く見えた。
律歌はどこか胸の奥が痛むのを感じながら、小さく息を吐いた。
「……うん。明日、頑張る」
「うん。律歌なら、きっと大丈夫」
奏希さんの優しい声に包まれながら、律歌は明日への決意を胸に刻んだ。