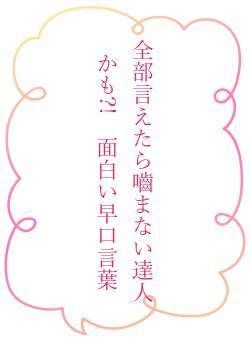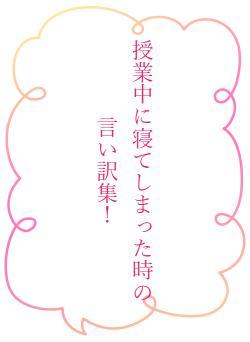翌朝――。
朝日がカーテンの隙間から差し込み、部屋の空気をやわらかく照らしていた。
律歌は目を覚まし、しばらくぼんやりと天井を見つめていた。昨夜の出来事が夢のように思えて、ほんの少し不思議な気分だった。
(……響歌と、ちゃんと話せたんだよね)
少し前まで、まともに会話することさえ難しかったのに、今はなぜか胸が軽かった。
布団から抜け出し、洗面所で身支度を整えた後、リビングへ向かうと――。
「お姉ちゃん! 朝ごはん、一緒に食べよ!」
響歌の弾むような声が飛んできた。
律歌は驚いたように目を瞬かせる。
今まで、家の中では最低限の会話しか交わさなかったのに。こんなふうに響歌から誘ってくれるなんて、少し前の自分なら考えられなかっただろう。
「……うん、一緒に食べよ」
自然と笑顔がこぼれる。
響歌と並んで食卓に座ると、両親が驚いたように目を丸くした。
「……珍しいわね、二人が並んで座るなんて」
母の言葉に、父もうなずく。
「最近は険悪な雰囲気ばかりだったのに、今日はなんだか穏やかだな」
律歌と響歌は顔を見合わせ、くすっと笑った。
「まあね。昨日、ちゃんと話し合ったから」
律歌がそう答えると、母は一瞬驚いたように目を見開き、そして少し寂しそうな、それでいてどこか申し訳なさそうな表情を浮かべた。
「律歌……今まで、ごめんなさい」
律歌は驚いて母を見た。
「え……?」
「あなたがピアノをやめたとき、本当はもっと話を聞いてあげるべきだったのに……響歌と比べられることがつらかったなんて、気づいてあげられなかった」
父も静かにうなずいた。
「律歌、お前の努力をちゃんと見ていたはずなのに、気づいてやれなかった。親として失格だったな」
律歌は少し目を伏せた。
確かに、両親はいつも響歌のことを誇らしげに話していた。だからこそ、自分は必要ないんだと思ってしまったのも事実だった。
けれど、昨夜響歌と本音を話し合って、今なら分かる。
(お父さんも、お母さんも、私を愛してくれていたんだ)
響歌が悪気なくピアノの才能の話をするたびに、両親もどう接していいか分からなかったのかもしれない。
律歌はそっと笑みを浮かべた。
「……ううん。もういいよ。今、ちゃんとお父さんとお母さんの気持ちを聞けたから、それで十分」
すると、響歌が勢いよく箸を置いて、腕を組んだ。
「ほんとだよ! お姉ちゃん、めっちゃ頑張ってたのに! もっと褒めてあげてよね!」
その言葉に、両親がまた驚いた顔をする。
律歌も思わず笑った。
「……響歌、ありがとう」
「えへへ。昨日話したら、なんかちょっとお姉ちゃんのこと見直しちゃった」
響歌が得意げに笑う。
(……こんな朝を迎えられるなんて、思ってもみなかった)
食卓には、今までになく温かい空気が流れていた。
少しずつ――確実に、何かが変わり始めている。
律歌は、温かい味噌汁をひと口飲みながら、小さく息をついた。
朝日がカーテンの隙間から差し込み、部屋の空気をやわらかく照らしていた。
律歌は目を覚まし、しばらくぼんやりと天井を見つめていた。昨夜の出来事が夢のように思えて、ほんの少し不思議な気分だった。
(……響歌と、ちゃんと話せたんだよね)
少し前まで、まともに会話することさえ難しかったのに、今はなぜか胸が軽かった。
布団から抜け出し、洗面所で身支度を整えた後、リビングへ向かうと――。
「お姉ちゃん! 朝ごはん、一緒に食べよ!」
響歌の弾むような声が飛んできた。
律歌は驚いたように目を瞬かせる。
今まで、家の中では最低限の会話しか交わさなかったのに。こんなふうに響歌から誘ってくれるなんて、少し前の自分なら考えられなかっただろう。
「……うん、一緒に食べよ」
自然と笑顔がこぼれる。
響歌と並んで食卓に座ると、両親が驚いたように目を丸くした。
「……珍しいわね、二人が並んで座るなんて」
母の言葉に、父もうなずく。
「最近は険悪な雰囲気ばかりだったのに、今日はなんだか穏やかだな」
律歌と響歌は顔を見合わせ、くすっと笑った。
「まあね。昨日、ちゃんと話し合ったから」
律歌がそう答えると、母は一瞬驚いたように目を見開き、そして少し寂しそうな、それでいてどこか申し訳なさそうな表情を浮かべた。
「律歌……今まで、ごめんなさい」
律歌は驚いて母を見た。
「え……?」
「あなたがピアノをやめたとき、本当はもっと話を聞いてあげるべきだったのに……響歌と比べられることがつらかったなんて、気づいてあげられなかった」
父も静かにうなずいた。
「律歌、お前の努力をちゃんと見ていたはずなのに、気づいてやれなかった。親として失格だったな」
律歌は少し目を伏せた。
確かに、両親はいつも響歌のことを誇らしげに話していた。だからこそ、自分は必要ないんだと思ってしまったのも事実だった。
けれど、昨夜響歌と本音を話し合って、今なら分かる。
(お父さんも、お母さんも、私を愛してくれていたんだ)
響歌が悪気なくピアノの才能の話をするたびに、両親もどう接していいか分からなかったのかもしれない。
律歌はそっと笑みを浮かべた。
「……ううん。もういいよ。今、ちゃんとお父さんとお母さんの気持ちを聞けたから、それで十分」
すると、響歌が勢いよく箸を置いて、腕を組んだ。
「ほんとだよ! お姉ちゃん、めっちゃ頑張ってたのに! もっと褒めてあげてよね!」
その言葉に、両親がまた驚いた顔をする。
律歌も思わず笑った。
「……響歌、ありがとう」
「えへへ。昨日話したら、なんかちょっとお姉ちゃんのこと見直しちゃった」
響歌が得意げに笑う。
(……こんな朝を迎えられるなんて、思ってもみなかった)
食卓には、今までになく温かい空気が流れていた。
少しずつ――確実に、何かが変わり始めている。
律歌は、温かい味噌汁をひと口飲みながら、小さく息をついた。