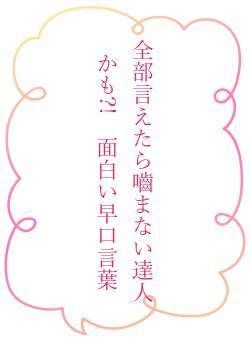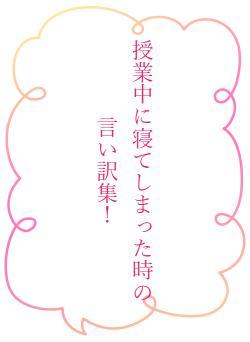静まり返ったホールに、スポットライトが灯る。
私と響歌が並んで座るステージ上。
正面に広がる満席の客席が、心臓を強く締め付けた。
(これが……最後の舞台)
指先が、わずかに震える。
ピアノの鍵盤の上にそっと手を置くと、冷たい感触が肌に伝わった。
隣にいる響歌は、余裕の笑みを浮かべている。
彼女にとって、この舞台は"成功して当然"の場所だ。
だけど私にとっては、全く違う。
私は、この舞台を最後にピアノを捨てる――
演奏が始まる。
響歌の歌声が、ホールいっぱいに響き渡る。
透き通るような高音、華やかで力強い歌声は、観客の心を一瞬で掴んだ。
私は、ただその伴奏を弾くだけ。
妹を引き立てるための音。
私が弾く意味なんて、きっと誰も気にしない。
(それでいい……それで……)
でも、思った以上に指が動かない。
普段通りに弾いているはずなのに、何かが違う。
心が、音に乗らない。
そして、ついにその瞬間が訪れた。
ミス――
指が鍵盤を滑り、和音が濁る。
一瞬の沈黙。
観客がざわめく音が、耳に突き刺さる。
響歌が眉をひそめ、ちらりとこちらを見る。
――しまった。
取り戻さなきゃ。
そう思えば思うほど、焦りが胸に広がり、頭が真っ白になっていく。
再び指を動かすけれど、今度はタイミングがずれる。
響歌の歌と合わなくなり、さらに観客が騒ぎ始めた。
「……はぁ」
響歌が大きく息を吐く音が、はっきりと聞こえた。
そして次の瞬間、マイクを通して、あからさまに言った。
「お姉ちゃん、本番でミスなんて恥ずかしいよ?」
その言葉が、ホール中に響き渡る。
観客が笑う。
クスクスと、まるで見世物を眺めるように。
「やっぱり、妹さんの方が才能あるわよね」
「伴奏のせいで台無しじゃない?」
「かわいそうに、姉妹で比べられるってキツいね」
耳を塞ぎたかった。
何も聞きたくなかった。
――もう無理だ。
演奏を続けなきゃいけないのに、指が動かない。
目の前の鍵盤が、ぼやけていく。
涙があふれそうになるのを、必死でこらえた。
終わりにしよう。
こんな苦しい思いをするくらいなら、ピアノなんてやめてしまえばいい――
そう決めたのは、このときだった。
コンサートは、私にとって"ピアノの最後の舞台"となった。
それが、このときの私の"限界"だった。
私と響歌が並んで座るステージ上。
正面に広がる満席の客席が、心臓を強く締め付けた。
(これが……最後の舞台)
指先が、わずかに震える。
ピアノの鍵盤の上にそっと手を置くと、冷たい感触が肌に伝わった。
隣にいる響歌は、余裕の笑みを浮かべている。
彼女にとって、この舞台は"成功して当然"の場所だ。
だけど私にとっては、全く違う。
私は、この舞台を最後にピアノを捨てる――
演奏が始まる。
響歌の歌声が、ホールいっぱいに響き渡る。
透き通るような高音、華やかで力強い歌声は、観客の心を一瞬で掴んだ。
私は、ただその伴奏を弾くだけ。
妹を引き立てるための音。
私が弾く意味なんて、きっと誰も気にしない。
(それでいい……それで……)
でも、思った以上に指が動かない。
普段通りに弾いているはずなのに、何かが違う。
心が、音に乗らない。
そして、ついにその瞬間が訪れた。
ミス――
指が鍵盤を滑り、和音が濁る。
一瞬の沈黙。
観客がざわめく音が、耳に突き刺さる。
響歌が眉をひそめ、ちらりとこちらを見る。
――しまった。
取り戻さなきゃ。
そう思えば思うほど、焦りが胸に広がり、頭が真っ白になっていく。
再び指を動かすけれど、今度はタイミングがずれる。
響歌の歌と合わなくなり、さらに観客が騒ぎ始めた。
「……はぁ」
響歌が大きく息を吐く音が、はっきりと聞こえた。
そして次の瞬間、マイクを通して、あからさまに言った。
「お姉ちゃん、本番でミスなんて恥ずかしいよ?」
その言葉が、ホール中に響き渡る。
観客が笑う。
クスクスと、まるで見世物を眺めるように。
「やっぱり、妹さんの方が才能あるわよね」
「伴奏のせいで台無しじゃない?」
「かわいそうに、姉妹で比べられるってキツいね」
耳を塞ぎたかった。
何も聞きたくなかった。
――もう無理だ。
演奏を続けなきゃいけないのに、指が動かない。
目の前の鍵盤が、ぼやけていく。
涙があふれそうになるのを、必死でこらえた。
終わりにしよう。
こんな苦しい思いをするくらいなら、ピアノなんてやめてしまえばいい――
そう決めたのは、このときだった。
コンサートは、私にとって"ピアノの最後の舞台"となった。
それが、このときの私の"限界"だった。