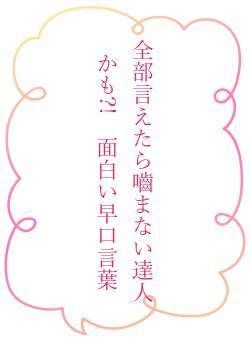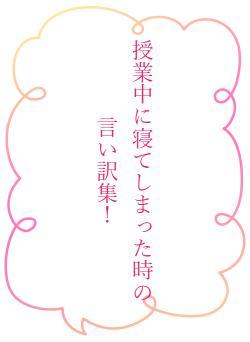放課後。
律歌は奏希さんの家のピアノ室に足を踏み入れた。
高城財閥の御曹司の家だけあって、音楽ホールのように広々とした部屋には、上品な木の香りが漂い、
中央には黒く艶やかなグランドピアノが静かに佇んでいる。
「今日もよろしくね」
奏希さんは穏やかに微笑みながら、律歌にピアノの前の席を勧めた。
「……うん。よろしくお願いします」
律歌は少し緊張しながら、鍵盤の前に座る。奏希さんはその隣に腰を下ろし、優しく手を鍵盤に添えた。
「まずは、基礎からやってみようか」
「基礎?」
「うん。いきなり難しい曲に挑戦するより、まずは指をしっかり慣らしていくのが大事だからね」
そう言いながら、奏希さんは律歌の手元を見つめる。
「指の力を抜いて。もっと柔らかく鍵盤に触れてみて」
律歌は言われた通り、力を抜いて鍵盤に指を置く。奏希さんがそっと手を添えて、指の位置を直してくれた。
「……こんな感じ?」
「そう、いい感じ。ほら、そのままスケールを弾いてみて」
律歌はゆっくりとドレミファソラシドと指を動かす。
奏希さんは律歌の演奏をじっと聴きながら、微笑んだ。
「うん、綺麗な音が出てるね。そのまま、もう一度」
律歌は何度か繰り返すうちに、少しずつ指の動きが滑らかになっていくのを感じた。
(奏希さんの教え方、すごく丁寧で優しい……)
これまでのレッスンでは、響歌と比較されることが多く、厳しい言葉をかけられることもあった。
しかし、奏希さんの教え方は違った。
一つひとつの音を大切に、無理のないペースで進めてくれる。
「じゃあ、今度はこの曲を弾いてみようか」
奏希さんが楽譜を開く。そこに書かれていたのは、クラシックの中でも比較的シンプルな小品だった。
「これなら、久しぶりの演奏でも無理なく弾けると思うよ」
「……うん、やってみる」
律歌は譜面を目で追いながら、慎重に指を鍵盤に置いた。そして、ゆっくりと最初の音を鳴らす。
奏希さんは黙ってその演奏を聴き、律歌が弾き終わると静かに拍手をした。
「すごい。久しぶりとは思えないくらい、綺麗な演奏だったよ」
「……そんなことないよ」
律歌は恥ずかしそうに視線を落とす。しかし、奏希さんは微笑みながら、静かに言葉を続けた。
「本当に、君のピアノは優しい音がする。聴いていて心地いいんだ」
「……」
律歌の胸がじんわりと温かくなる。
「でも、少しだけテンポを意識してみようか。この部分、少し遅くなっていたから、もう少しリズムに乗る感じで」
奏希さんは優しくアドバイスをしながら、実際にお手本を弾いてみせる。
(やっぱり、すごい……)
律歌は奏希さんの指先が鍵盤の上を滑る様子をじっと見つめた。流れるような美しい音色が、ピアノ室いっぱいに広がっていく。
「……じゃあ、もう一度やってみようか」
律歌は頷き、再び鍵盤に指を置いた。
奏希さんの穏やかな声に導かれるように、律歌はゆっくりと音を紡いでいく。
(私は……やっぱり、ピアノが好きなんだ)
そんな思いが、胸の奥でふんわりと広がっていくのを感じた。
律歌は奏希さんの家のピアノ室に足を踏み入れた。
高城財閥の御曹司の家だけあって、音楽ホールのように広々とした部屋には、上品な木の香りが漂い、
中央には黒く艶やかなグランドピアノが静かに佇んでいる。
「今日もよろしくね」
奏希さんは穏やかに微笑みながら、律歌にピアノの前の席を勧めた。
「……うん。よろしくお願いします」
律歌は少し緊張しながら、鍵盤の前に座る。奏希さんはその隣に腰を下ろし、優しく手を鍵盤に添えた。
「まずは、基礎からやってみようか」
「基礎?」
「うん。いきなり難しい曲に挑戦するより、まずは指をしっかり慣らしていくのが大事だからね」
そう言いながら、奏希さんは律歌の手元を見つめる。
「指の力を抜いて。もっと柔らかく鍵盤に触れてみて」
律歌は言われた通り、力を抜いて鍵盤に指を置く。奏希さんがそっと手を添えて、指の位置を直してくれた。
「……こんな感じ?」
「そう、いい感じ。ほら、そのままスケールを弾いてみて」
律歌はゆっくりとドレミファソラシドと指を動かす。
奏希さんは律歌の演奏をじっと聴きながら、微笑んだ。
「うん、綺麗な音が出てるね。そのまま、もう一度」
律歌は何度か繰り返すうちに、少しずつ指の動きが滑らかになっていくのを感じた。
(奏希さんの教え方、すごく丁寧で優しい……)
これまでのレッスンでは、響歌と比較されることが多く、厳しい言葉をかけられることもあった。
しかし、奏希さんの教え方は違った。
一つひとつの音を大切に、無理のないペースで進めてくれる。
「じゃあ、今度はこの曲を弾いてみようか」
奏希さんが楽譜を開く。そこに書かれていたのは、クラシックの中でも比較的シンプルな小品だった。
「これなら、久しぶりの演奏でも無理なく弾けると思うよ」
「……うん、やってみる」
律歌は譜面を目で追いながら、慎重に指を鍵盤に置いた。そして、ゆっくりと最初の音を鳴らす。
奏希さんは黙ってその演奏を聴き、律歌が弾き終わると静かに拍手をした。
「すごい。久しぶりとは思えないくらい、綺麗な演奏だったよ」
「……そんなことないよ」
律歌は恥ずかしそうに視線を落とす。しかし、奏希さんは微笑みながら、静かに言葉を続けた。
「本当に、君のピアノは優しい音がする。聴いていて心地いいんだ」
「……」
律歌の胸がじんわりと温かくなる。
「でも、少しだけテンポを意識してみようか。この部分、少し遅くなっていたから、もう少しリズムに乗る感じで」
奏希さんは優しくアドバイスをしながら、実際にお手本を弾いてみせる。
(やっぱり、すごい……)
律歌は奏希さんの指先が鍵盤の上を滑る様子をじっと見つめた。流れるような美しい音色が、ピアノ室いっぱいに広がっていく。
「……じゃあ、もう一度やってみようか」
律歌は頷き、再び鍵盤に指を置いた。
奏希さんの穏やかな声に導かれるように、律歌はゆっくりと音を紡いでいく。
(私は……やっぱり、ピアノが好きなんだ)
そんな思いが、胸の奥でふんわりと広がっていくのを感じた。