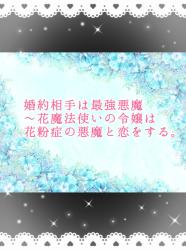外に出るため魔王と廊下を歩いていると、まだ明かりがついていて、ヒソヒソ声が聞こえる部屋があった。扉の隙間から覗くと、おまつりの出店にいた者たちが酒を飲んでいた。
今日はこの者たちも泊まるのか、俺らだけではないのだな。この宿は貸切も良いけれど、他の客もいて賑わっている雰囲気も良いのだろうなと、ふと思う。
そして再び魔王と外に出ると、同時に空を見上げた。まだ星は輝いている。庭のベンチに並んで腰掛けた。たこやきの箱を開けると、たこやきに爪楊枝を刺し魔王の口の中に入れた。
「味は、どうだ?」
「……美味しい」
いきなり口に入れられ若干戸惑う魔王だが、きちんと感想を述べてくれた。
「美味しいか、残しておいて良かった。全部食べてくれ!」
「味見しないのか? いや、勇者はおまつりで食べていたな」
「魔王は子らに射的を教えるのに忙しかったのに、俺がたこやきを食べていたの、見てたんだな」
「……偶然だ」
魔王は爪楊枝を俺から奪うと、たこやきをもうひとつ口にした。
美味しそうに食べてくれている魔王を見つめた。タイミングは今ではない気がするが、魔王に対してモヤモヤしているものを、早く全て吐き出してしまいたい衝動に駆られた。この星空も背中を押してくれているのかなんて、珍しく頭の中はロマンティックモードだ。
「……魔王、色々とごめん」
「昨日は突然お礼を言い、今日は突然謝る日なのか。何故、今、我に謝った?」
「魔王の背中の傷を……」
魔王の心と体も傷付けてしまった。魔王を切ってしまった事実は、俺の人生の中で最大の罪だった。まるで罪を白状するような気持ちになり、これ以上の言葉を本人に伝えるのが怖くなった。
「もう、いい。あの争いの原因は先に手を出してしまった我にある。我が全て悪かったのだ」
「違う……俺は、魔王が自分を責める度に辛くなる。魔王、お前は人間に大切な物を盗まれたから人間に手を出したんだろ?」
「……何故知っている」
魔王は爪楊枝を箱の上に置き、驚いたような強い眼差しで俺を見つめる。
きちんと正直に伝えよう。子らも嘘をついてしまった時などはきちんと緊張しながらも伝えてくれていた。魔王に怒られたり嫌われたりするのは怖いけれど、俺も――
「それは、見てしまったからだ。魔王の日記を!」
「勇者だったのか、見たのは。置いてある場所がズレていたから子供の仕業かと思っていたのだが」
「怒らないのか?」
「見られる場所に置いた、我が悪い」
「いや、見た俺が悪い。勝手に見てごめん」
ふたりで俯く。一瞬だけ強い風が吹いてきて、俺と魔王の間を通っていった。
「母が亡くなる前、災いから守り健康でいられるようにと特殊な魔力を込め、我のためにアミュレットを作ってくれたのだ」
「そんな大切な物を盗まれたのか?」
「そうだ。犯人を突き止めたが、犯人の手元にはもうアミュレットはなかった。追及すると、好奇心だとか金になるとか……くだらない理由で盗んだんだと白状した。しかもその人間は嘲笑ったのだ『魔界の物は金にならなかったな』と。我は頭に血が上り、そして――」
人間の間では、完全に魔王は悪の存在だ。俺もかつては魔王は悪だと認識していた。だが、魔王を知り、話を聞いた後となっては、この件は魔王は悪くはない。悪は盗みを働いた人間の方だ。
「俺は、過去をやり直したい。魔王と対決する時に。あの時きちんと魔王と話し合えば、魔王を知れば。決して戦うことはなかった。傷つけることをしなかった。魔王、本当にごめん」
「あの時、我を倒してくれて良かったのかもしれない。あの時は全てが行き止まりだった。孤独で目的もなく、何も感じずにただ立っている。屍のようだった。勇者たちに倒されて子供たちと出会い、そして勇者とも今こうして過ごせている。だからもう、謝らないでくれ。我は今、幸せだ」
『幸せ』
魔王がはっきりと幸せだと言った。
魔王の過去を知った後だと、ずしんと重みのある言葉になる。
俺はたこやきを端に寄せると魔王を抱きしめた。
「どれだけ良い奴なんだよ、魔王は。俺、世間に魔王の良さを伝えたい――」
「いや、それはいい」
「……魔王、家族にならないか?」
伝えたい言葉が次々溢れてくる。
「我と勇者が家族だと? もし家族になったら、そなたの立場はどうなる? 世間からは冷たい目で見られるだろう」
「……世間とかそんなもの、魔王の今までの痛みと比べたら、たいしたことないし、どうでもいい!」
魔王の背中にある手に力を込める。魔王も俺の背中に手をまわし、力を込めてきた。
「分かった。今から家族になろう」
今はまだ言葉だけの契約に過ぎないが、魔王と家族になった。魔王と特別な関係になったのだ。ふたりの間にあった見えない壁が崩壊していく。まだ解決しなければならないことはあるが、魔王との絆は深いものとなった。
魔王と抱き合い、ぬくもりを感じていると背後からカサっと音がした。
急いで魔王から離れると音の方を向く。警戒をしながら、俺の背中の中心辺りに魔王を寄せる。魔王が襲われた時以来ずっと肌身離さず、風呂の時や就寝時も近くに置いてあるナイフを握った。
今日はこの者たちも泊まるのか、俺らだけではないのだな。この宿は貸切も良いけれど、他の客もいて賑わっている雰囲気も良いのだろうなと、ふと思う。
そして再び魔王と外に出ると、同時に空を見上げた。まだ星は輝いている。庭のベンチに並んで腰掛けた。たこやきの箱を開けると、たこやきに爪楊枝を刺し魔王の口の中に入れた。
「味は、どうだ?」
「……美味しい」
いきなり口に入れられ若干戸惑う魔王だが、きちんと感想を述べてくれた。
「美味しいか、残しておいて良かった。全部食べてくれ!」
「味見しないのか? いや、勇者はおまつりで食べていたな」
「魔王は子らに射的を教えるのに忙しかったのに、俺がたこやきを食べていたの、見てたんだな」
「……偶然だ」
魔王は爪楊枝を俺から奪うと、たこやきをもうひとつ口にした。
美味しそうに食べてくれている魔王を見つめた。タイミングは今ではない気がするが、魔王に対してモヤモヤしているものを、早く全て吐き出してしまいたい衝動に駆られた。この星空も背中を押してくれているのかなんて、珍しく頭の中はロマンティックモードだ。
「……魔王、色々とごめん」
「昨日は突然お礼を言い、今日は突然謝る日なのか。何故、今、我に謝った?」
「魔王の背中の傷を……」
魔王の心と体も傷付けてしまった。魔王を切ってしまった事実は、俺の人生の中で最大の罪だった。まるで罪を白状するような気持ちになり、これ以上の言葉を本人に伝えるのが怖くなった。
「もう、いい。あの争いの原因は先に手を出してしまった我にある。我が全て悪かったのだ」
「違う……俺は、魔王が自分を責める度に辛くなる。魔王、お前は人間に大切な物を盗まれたから人間に手を出したんだろ?」
「……何故知っている」
魔王は爪楊枝を箱の上に置き、驚いたような強い眼差しで俺を見つめる。
きちんと正直に伝えよう。子らも嘘をついてしまった時などはきちんと緊張しながらも伝えてくれていた。魔王に怒られたり嫌われたりするのは怖いけれど、俺も――
「それは、見てしまったからだ。魔王の日記を!」
「勇者だったのか、見たのは。置いてある場所がズレていたから子供の仕業かと思っていたのだが」
「怒らないのか?」
「見られる場所に置いた、我が悪い」
「いや、見た俺が悪い。勝手に見てごめん」
ふたりで俯く。一瞬だけ強い風が吹いてきて、俺と魔王の間を通っていった。
「母が亡くなる前、災いから守り健康でいられるようにと特殊な魔力を込め、我のためにアミュレットを作ってくれたのだ」
「そんな大切な物を盗まれたのか?」
「そうだ。犯人を突き止めたが、犯人の手元にはもうアミュレットはなかった。追及すると、好奇心だとか金になるとか……くだらない理由で盗んだんだと白状した。しかもその人間は嘲笑ったのだ『魔界の物は金にならなかったな』と。我は頭に血が上り、そして――」
人間の間では、完全に魔王は悪の存在だ。俺もかつては魔王は悪だと認識していた。だが、魔王を知り、話を聞いた後となっては、この件は魔王は悪くはない。悪は盗みを働いた人間の方だ。
「俺は、過去をやり直したい。魔王と対決する時に。あの時きちんと魔王と話し合えば、魔王を知れば。決して戦うことはなかった。傷つけることをしなかった。魔王、本当にごめん」
「あの時、我を倒してくれて良かったのかもしれない。あの時は全てが行き止まりだった。孤独で目的もなく、何も感じずにただ立っている。屍のようだった。勇者たちに倒されて子供たちと出会い、そして勇者とも今こうして過ごせている。だからもう、謝らないでくれ。我は今、幸せだ」
『幸せ』
魔王がはっきりと幸せだと言った。
魔王の過去を知った後だと、ずしんと重みのある言葉になる。
俺はたこやきを端に寄せると魔王を抱きしめた。
「どれだけ良い奴なんだよ、魔王は。俺、世間に魔王の良さを伝えたい――」
「いや、それはいい」
「……魔王、家族にならないか?」
伝えたい言葉が次々溢れてくる。
「我と勇者が家族だと? もし家族になったら、そなたの立場はどうなる? 世間からは冷たい目で見られるだろう」
「……世間とかそんなもの、魔王の今までの痛みと比べたら、たいしたことないし、どうでもいい!」
魔王の背中にある手に力を込める。魔王も俺の背中に手をまわし、力を込めてきた。
「分かった。今から家族になろう」
今はまだ言葉だけの契約に過ぎないが、魔王と家族になった。魔王と特別な関係になったのだ。ふたりの間にあった見えない壁が崩壊していく。まだ解決しなければならないことはあるが、魔王との絆は深いものとなった。
魔王と抱き合い、ぬくもりを感じていると背後からカサっと音がした。
急いで魔王から離れると音の方を向く。警戒をしながら、俺の背中の中心辺りに魔王を寄せる。魔王が襲われた時以来ずっと肌身離さず、風呂の時や就寝時も近くに置いてあるナイフを握った。