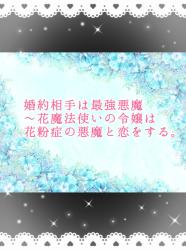「魔王、ずっと手を繋いでて大丈夫?」
途中でブラックが魔王に問う。ブラックはずっと魔王の手を握りながら魔王城に戻る道を進んでいた。
「あぁ、大丈夫だ」
「魔王城に戻ったらブラックが魔王に甘えられる時間は減るからな。今のうちに甘えておけばいい。ほら、俺の右手もあいてるぞ」
右手をブラックに差し出すと、ブラックは俺の手も握った。ブラックは今、俺と魔王ふたりの手を握りながら真ん中を歩いている。感情は分かりづらいタイプだが嬉しそうな雰囲気だった。いつもはお兄さんらしく過ごしているから大きく見えるけれども、まだ甘えんぼうな部分もあるんだな。ブラックを見つめていると、視線に気がついたブラックがこっちを見てふっと笑った。
あっという間に魔王城に着いた。扉を開けると全員が「魔王が帰ってきた~!」と喜びながら走ってきた。ホワイトを抱っこし、更にギルバードもおんぶしている執事は心配だった表情を隠せない状態だ。小さい子らは魔王の太もも辺りに、大きい子らは腹など上の方に巻きつくように抱きついた。子らが魔王に巻きついたその光景は、雪の季節に着るもこもこなコートを魔王が纏っているようだった。しばらくするとひとり、またひとりと魔王から剥がれていく。全員が剥がれると、それぞれが自由に動きだす。
「さっき我を恨む男が現れる前、何を言いかけた?」と、魔王から問われる。
さっき?
一瞬なんのことだと考えたが、すぐに思い出した。池の前で「魔王の母親になりたい」と言おうとした時だろう。
「あ、いや……うん」
さっきの状態なら勢いよく言えた気がするが、あらためて聞かれると言いづらく、ためらってしまう。
「勇者よ、今すぐに答えろ!」
「……魔王の母親になるって言おうとしただけだよ」
「な、なんだと?」
眉間に皺を寄せた魔王は俺の目をずっと見つめた。俺はムズ痒い気持ちになり、視線を斜め下に向ける。
「いや、そんなことよりも。魔王、お前、どうにかした方が良いぞ?」
「何をだ?」
「と、とにかくだ。これをやる!」
よだれふきや小さなクッキーなどを入れて魔王城の中でも常に身につけているポーチから温泉チケットを取り出し、魔王に渡した。
「なんだこれは!」
「温泉チケットだ。たまにはひとりでゆっくりするといい。こっちのことは、俺と執事に任せろ」
「温泉……ひとりでか……」
少し不満そうにも見えるような、不思議な表情でチケットをじっと見つめている魔王。
「いや、いらない。ひとりで行くのはどうも気が進まない」と、魔王はチケットを返してきた。
「いや、受け取れよ」
「いらない」
「なぜ受け取らない!」
初等部のブルー、オレンジ、レッドの三人が不安そうな表情をしながら執事を連れてこっちにきた。そして「喧嘩はダメ。仲直りして?と三人が仰っております」と様子を伺いながら執事が話しかけてきた。
「いや、喧嘩ではない」と俺は思い切り否定する。
「勇者、何持ってるんだ? 温泉チケットって書いてある……」と、レッドがチケットを覗き込んだ。
「温泉、行ってみたい……」とオレンジが言うと
「温泉って、ぽかぽか気持ちいいお湯に入る場所?」とブルーも反応した。
魔王は三人をひとりずつ丁寧に見つめた。
「子供たちも温泉へ連れて行きたい。連れて行けるのなら、我も行く」
「分かった。そうだよな……連れて行きたいよな! そしたら、きちんと全員連れて行けるように、そして魔王も休めるように。計画を真面目に考える」
話を聞いていた他の子らもわらわらと近くに寄ってきて、バンザイをしたり飛び跳ねたりして全員で喜んでいた。
*
途中でブラックが魔王に問う。ブラックはずっと魔王の手を握りながら魔王城に戻る道を進んでいた。
「あぁ、大丈夫だ」
「魔王城に戻ったらブラックが魔王に甘えられる時間は減るからな。今のうちに甘えておけばいい。ほら、俺の右手もあいてるぞ」
右手をブラックに差し出すと、ブラックは俺の手も握った。ブラックは今、俺と魔王ふたりの手を握りながら真ん中を歩いている。感情は分かりづらいタイプだが嬉しそうな雰囲気だった。いつもはお兄さんらしく過ごしているから大きく見えるけれども、まだ甘えんぼうな部分もあるんだな。ブラックを見つめていると、視線に気がついたブラックがこっちを見てふっと笑った。
あっという間に魔王城に着いた。扉を開けると全員が「魔王が帰ってきた~!」と喜びながら走ってきた。ホワイトを抱っこし、更にギルバードもおんぶしている執事は心配だった表情を隠せない状態だ。小さい子らは魔王の太もも辺りに、大きい子らは腹など上の方に巻きつくように抱きついた。子らが魔王に巻きついたその光景は、雪の季節に着るもこもこなコートを魔王が纏っているようだった。しばらくするとひとり、またひとりと魔王から剥がれていく。全員が剥がれると、それぞれが自由に動きだす。
「さっき我を恨む男が現れる前、何を言いかけた?」と、魔王から問われる。
さっき?
一瞬なんのことだと考えたが、すぐに思い出した。池の前で「魔王の母親になりたい」と言おうとした時だろう。
「あ、いや……うん」
さっきの状態なら勢いよく言えた気がするが、あらためて聞かれると言いづらく、ためらってしまう。
「勇者よ、今すぐに答えろ!」
「……魔王の母親になるって言おうとしただけだよ」
「な、なんだと?」
眉間に皺を寄せた魔王は俺の目をずっと見つめた。俺はムズ痒い気持ちになり、視線を斜め下に向ける。
「いや、そんなことよりも。魔王、お前、どうにかした方が良いぞ?」
「何をだ?」
「と、とにかくだ。これをやる!」
よだれふきや小さなクッキーなどを入れて魔王城の中でも常に身につけているポーチから温泉チケットを取り出し、魔王に渡した。
「なんだこれは!」
「温泉チケットだ。たまにはひとりでゆっくりするといい。こっちのことは、俺と執事に任せろ」
「温泉……ひとりでか……」
少し不満そうにも見えるような、不思議な表情でチケットをじっと見つめている魔王。
「いや、いらない。ひとりで行くのはどうも気が進まない」と、魔王はチケットを返してきた。
「いや、受け取れよ」
「いらない」
「なぜ受け取らない!」
初等部のブルー、オレンジ、レッドの三人が不安そうな表情をしながら執事を連れてこっちにきた。そして「喧嘩はダメ。仲直りして?と三人が仰っております」と様子を伺いながら執事が話しかけてきた。
「いや、喧嘩ではない」と俺は思い切り否定する。
「勇者、何持ってるんだ? 温泉チケットって書いてある……」と、レッドがチケットを覗き込んだ。
「温泉、行ってみたい……」とオレンジが言うと
「温泉って、ぽかぽか気持ちいいお湯に入る場所?」とブルーも反応した。
魔王は三人をひとりずつ丁寧に見つめた。
「子供たちも温泉へ連れて行きたい。連れて行けるのなら、我も行く」
「分かった。そうだよな……連れて行きたいよな! そしたら、きちんと全員連れて行けるように、そして魔王も休めるように。計画を真面目に考える」
話を聞いていた他の子らもわらわらと近くに寄ってきて、バンザイをしたり飛び跳ねたりして全員で喜んでいた。
*