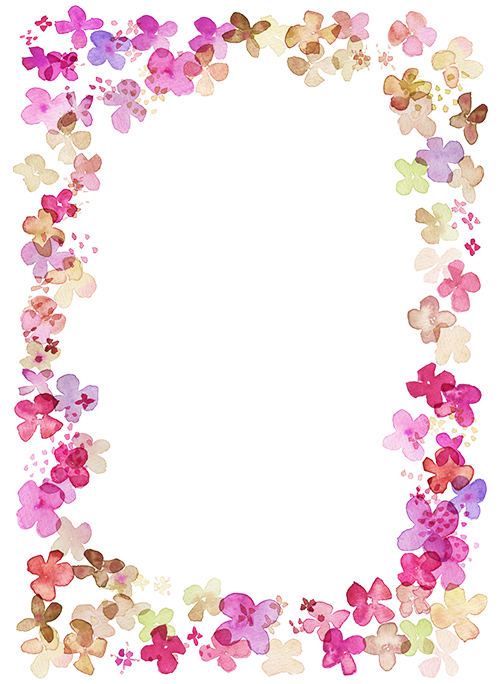「千早様……」
まだ死にたくない。
まだ千早様の側にいたい。
千早様の気まぐれが終わるその時まで、彼の側で、彼にお仕えしたかった。
彼の側は、暖かいのだ。
決して口数の多い方ではない。
時にぶっきらぼうであったり、淡々していたり……。
でも、わたしをわたしとして「見て」くれる方。
わたしに、手を差し伸べてくれる方。
千早様を想うと胸が温かくなるこの感情を何と呼ぶのか、わたしにはわからない。
だけど、わたしを生かすのも殺すのも、千早様でないと嫌だと思った。
彼の知らないところで、彼以外のものの手によって死ぬのは嫌なのだ。
死の間際まで千早様の側にいたい。
こんな風に考えるわたしは、どこかおかしいのだろうか。
まだ死にたくない。
まだ千早様の側にいたい。
千早様の気まぐれが終わるその時まで、彼の側で、彼にお仕えしたかった。
彼の側は、暖かいのだ。
決して口数の多い方ではない。
時にぶっきらぼうであったり、淡々していたり……。
でも、わたしをわたしとして「見て」くれる方。
わたしに、手を差し伸べてくれる方。
千早様を想うと胸が温かくなるこの感情を何と呼ぶのか、わたしにはわからない。
だけど、わたしを生かすのも殺すのも、千早様でないと嫌だと思った。
彼の知らないところで、彼以外のものの手によって死ぬのは嫌なのだ。
死の間際まで千早様の側にいたい。
こんな風に考えるわたしは、どこかおかしいのだろうか。