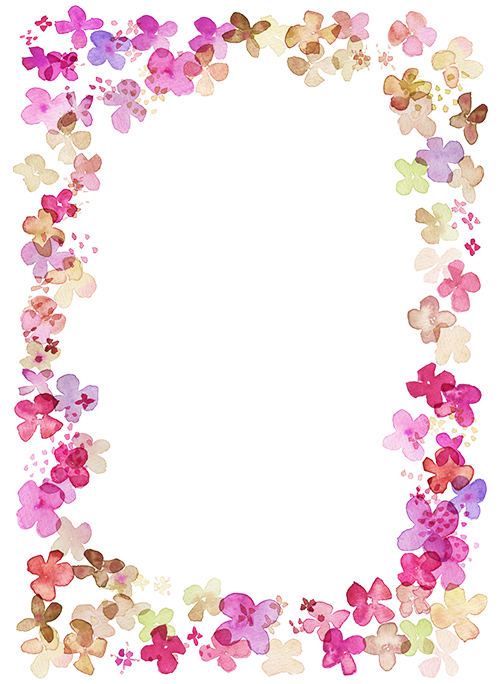白い肌に、青銀色のまっすぐな髪。
わたしよりいくつか年上の、まだお若い女性に見えるけれど、鬼というものは外見で年齢を測れない。二十歳前後に見える千早様も、齢百年を優に超えているのだ。
失礼にならないように頭を下げると、彼女はわたしの方に手を伸ばし、顎に指先をかけた。
くいっと顔をあげさせられ、思わず目をぱちくりとさせてしまう。
「まあまあ、本当に鬼になっていること。道間に生まれ、鬼になるなんて、お前も難儀な運命を背負った子ねえ」
彼女の指先が顎にかかったままなので、わたしは動くに動けない。
どうしたものかと思っていると、慌てたように玄関の引き戸が開いた。
わたしよりいくつか年上の、まだお若い女性に見えるけれど、鬼というものは外見で年齢を測れない。二十歳前後に見える千早様も、齢百年を優に超えているのだ。
失礼にならないように頭を下げると、彼女はわたしの方に手を伸ばし、顎に指先をかけた。
くいっと顔をあげさせられ、思わず目をぱちくりとさせてしまう。
「まあまあ、本当に鬼になっていること。道間に生まれ、鬼になるなんて、お前も難儀な運命を背負った子ねえ」
彼女の指先が顎にかかったままなので、わたしは動くに動けない。
どうしたものかと思っていると、慌てたように玄関の引き戸が開いた。