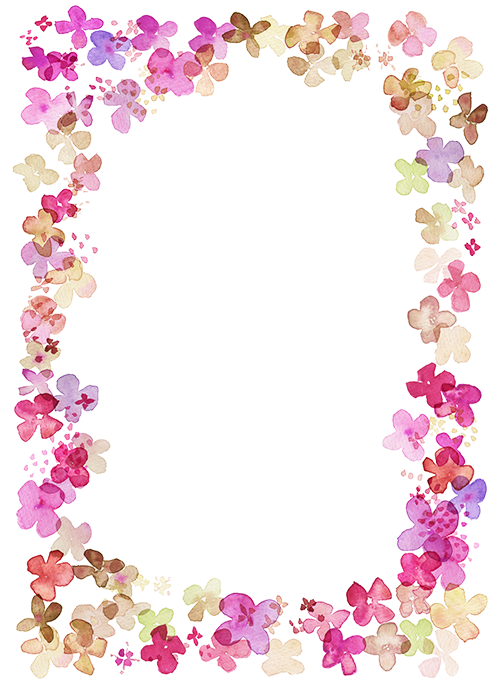正直なことを言えば、千早もそれを決めかねていた。
先ほど連れてきて、千早の邸の一室に寝かせて置いた「女」。――道間の娘。
山の中で女を見つけた時、千早は確かに彼女を殺そうと思っていた。
放置していても死にそうなほど弱っていたが、百年前に父を殺した道間に対する恨みは未だ根深い。
人の一生は短く、あの女はその時の道間の女狐ではなく末裔だったが、そんなことは千早には関係のないことだった。
放置しても死にそうだが、この手でなぶり殺しにしてやりたいという攻撃的な感情に支配され、千早は女の前に立った。
――だというのに、なぜ、その考えが変わったのだろう。
自分でもよくわからない。
もしかしたら、見下ろした女に道間らしさがなかったからかもしれない。
女は何がおかしいのか儚く笑い、そして目を閉じた。ああ、死ぬのだなと思った。
死ぬのか、という千早の問いかけに返すこともなく、諦観めいた無に近い表情で、ただただそのときが来るのを待っているように見えた。
先ほど連れてきて、千早の邸の一室に寝かせて置いた「女」。――道間の娘。
山の中で女を見つけた時、千早は確かに彼女を殺そうと思っていた。
放置していても死にそうなほど弱っていたが、百年前に父を殺した道間に対する恨みは未だ根深い。
人の一生は短く、あの女はその時の道間の女狐ではなく末裔だったが、そんなことは千早には関係のないことだった。
放置しても死にそうだが、この手でなぶり殺しにしてやりたいという攻撃的な感情に支配され、千早は女の前に立った。
――だというのに、なぜ、その考えが変わったのだろう。
自分でもよくわからない。
もしかしたら、見下ろした女に道間らしさがなかったからかもしれない。
女は何がおかしいのか儚く笑い、そして目を閉じた。ああ、死ぬのだなと思った。
死ぬのか、という千早の問いかけに返すこともなく、諦観めいた無に近い表情で、ただただそのときが来るのを待っているように見えた。