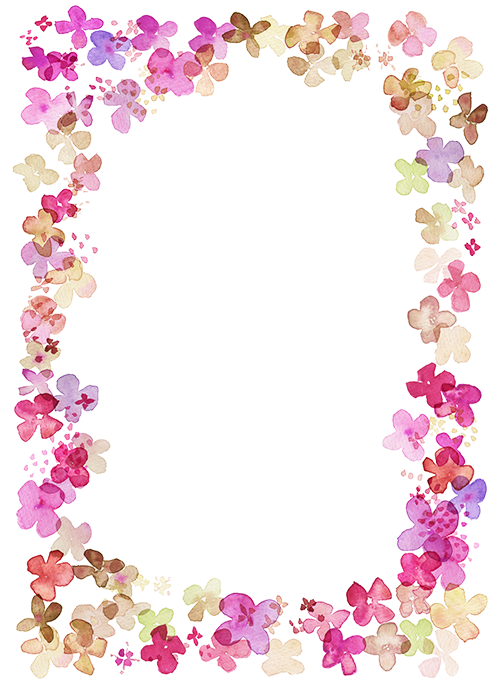決して誉められていないのはわかっているけれど、その言葉はわたしを傷つけることはなかった。
無用なものとされ、存在ごと打ち捨てられていたようなわたしにとって、変と表現されることは逆に小さな感慨すらもたらす。
変、と言われると言うことは、すなわちわたし自身を「表現」してくれていると言うことだ。
わたしを、見て、感じてくれていることなのだ。
彼の綺麗な赤紫色の瞳に、わたしが映っている。
感動せずには、いられない。
「お前は死んだ」
彼は同じ言葉を繰り返す。
「俺が殺した。そしてお前は人の理から外れた」
彼はわたしの首元に手を伸ばす。
指先が触れ、何かを確かめるように滑った。
ちょっとだけ、くすぐったい。
「お前は、もはや道間ではない。――お前は、鬼だ」
わたしは、大きく目を見開いた。
無用なものとされ、存在ごと打ち捨てられていたようなわたしにとって、変と表現されることは逆に小さな感慨すらもたらす。
変、と言われると言うことは、すなわちわたし自身を「表現」してくれていると言うことだ。
わたしを、見て、感じてくれていることなのだ。
彼の綺麗な赤紫色の瞳に、わたしが映っている。
感動せずには、いられない。
「お前は死んだ」
彼は同じ言葉を繰り返す。
「俺が殺した。そしてお前は人の理から外れた」
彼はわたしの首元に手を伸ばす。
指先が触れ、何かを確かめるように滑った。
ちょっとだけ、くすぐったい。
「お前は、もはや道間ではない。――お前は、鬼だ」
わたしは、大きく目を見開いた。