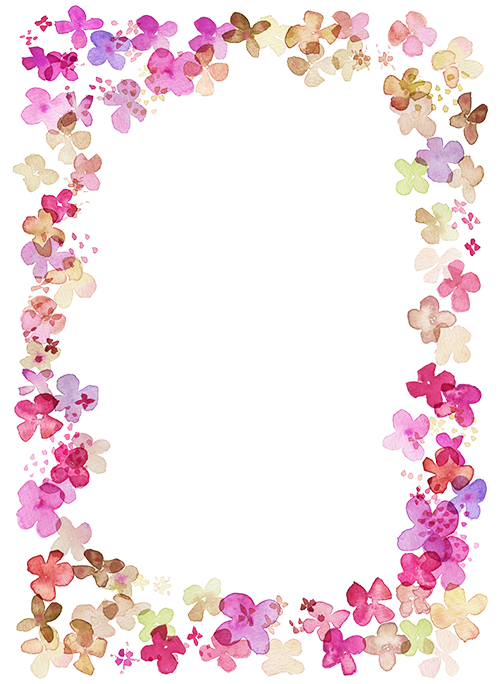頬を撫でられるのが気持ちよくて目を細めると、千早様がひょいとわたしを膝の上に抱き上げる。
こんなことをされたのははじめてで、恥ずかしくておろおろしてしまったけれど、湯上りの千早様の体温が心地よかった。
千早様の手が頭に伸びて、地肌をくすぐるように撫でられる。
「お前はあれこれ考えすぎるきらいがある。もう少し肩の力を抜いて生きろ」
「……はい」
わたしの小さな不安を、こうやって千早様は一つ一つ溶かしてくれる。
千早様の胸に甘えるように頬をつけると、つむじのあたりに口づけが落ちてきた。
こういう、穏やかで優しいふれあいが、その時間が、わたしは好きだ。
「千早様、今日の山菜ごはんが美味しかったので、お邸に帰ったら挑戦したいです」
「そうか、それは楽しみだな」
千早様が楽しみにしてくださるなら、頑張って美味しいものを作らなくては。
この日、わたしたちは、夜遅くまでぼんやりと夜空を眺めて過ごした。
こんなことをされたのははじめてで、恥ずかしくておろおろしてしまったけれど、湯上りの千早様の体温が心地よかった。
千早様の手が頭に伸びて、地肌をくすぐるように撫でられる。
「お前はあれこれ考えすぎるきらいがある。もう少し肩の力を抜いて生きろ」
「……はい」
わたしの小さな不安を、こうやって千早様は一つ一つ溶かしてくれる。
千早様の胸に甘えるように頬をつけると、つむじのあたりに口づけが落ちてきた。
こういう、穏やかで優しいふれあいが、その時間が、わたしは好きだ。
「千早様、今日の山菜ごはんが美味しかったので、お邸に帰ったら挑戦したいです」
「そうか、それは楽しみだな」
千早様が楽しみにしてくださるなら、頑張って美味しいものを作らなくては。
この日、わたしたちは、夜遅くまでぼんやりと夜空を眺めて過ごした。