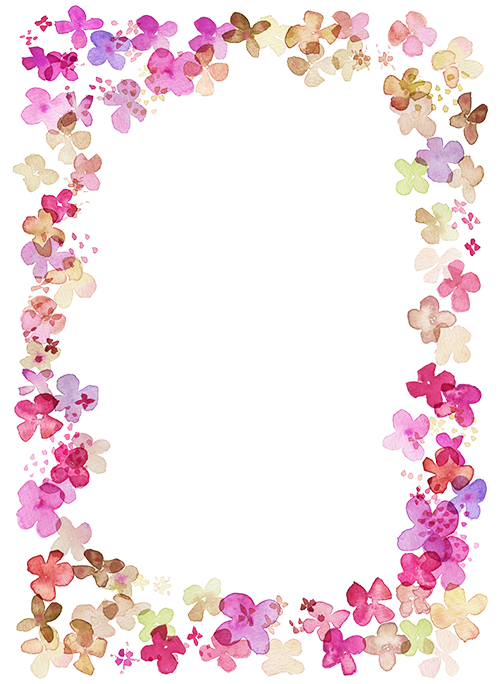「……がんばろう」
「何を頑張るんだ?」
ぐっと拳を握り締めたとき、頭上から千早様の声がして、わたしは思わず「ひゃっ」と飛び上がった。
顔を上げれば、浴衣姿の千早様が立っている。
湯上りの千早様は、ほんのり頬が上気していて、直視できない色気が漂っていた。
「え、ええっと、その……、牡丹様をお手本に、千早様の妻として立派に、なりたいと……思っていました……」
なんだか気恥ずかしくて声が尻すぼみになるわたしに、千早様はぐっと眉を寄せた。
「ユキがしたいことに異論を唱えるわけではないが、牡丹を手本にするのはあまりお勧めできない」
「どうしてですか?」
湯上りの千早様に冷ましたお茶を用意しながら訊ねると、千早様が縁側の椅子に腰を下ろしてため息をつく。
「母親に振り回されている青葉を見ていて気づかないか? あれは、面倒くさい女だ」
そうだろうか?
千早様の前にお茶を置きつつ首をひねると、千早様がわたしの頬に手を伸ばした。
「何かを手本にする必要はない。ユキはユキのままでいればいい」
「わたしの、ままで……」
千早様はどうして、いつもわたしを肯定してくれるのだろう。
至らない点ばかりなのに、わたしのままでいいなんて。
「何を頑張るんだ?」
ぐっと拳を握り締めたとき、頭上から千早様の声がして、わたしは思わず「ひゃっ」と飛び上がった。
顔を上げれば、浴衣姿の千早様が立っている。
湯上りの千早様は、ほんのり頬が上気していて、直視できない色気が漂っていた。
「え、ええっと、その……、牡丹様をお手本に、千早様の妻として立派に、なりたいと……思っていました……」
なんだか気恥ずかしくて声が尻すぼみになるわたしに、千早様はぐっと眉を寄せた。
「ユキがしたいことに異論を唱えるわけではないが、牡丹を手本にするのはあまりお勧めできない」
「どうしてですか?」
湯上りの千早様に冷ましたお茶を用意しながら訊ねると、千早様が縁側の椅子に腰を下ろしてため息をつく。
「母親に振り回されている青葉を見ていて気づかないか? あれは、面倒くさい女だ」
そうだろうか?
千早様の前にお茶を置きつつ首をひねると、千早様がわたしの頬に手を伸ばした。
「何かを手本にする必要はない。ユキはユキのままでいればいい」
「わたしの、ままで……」
千早様はどうして、いつもわたしを肯定してくれるのだろう。
至らない点ばかりなのに、わたしのままでいいなんて。