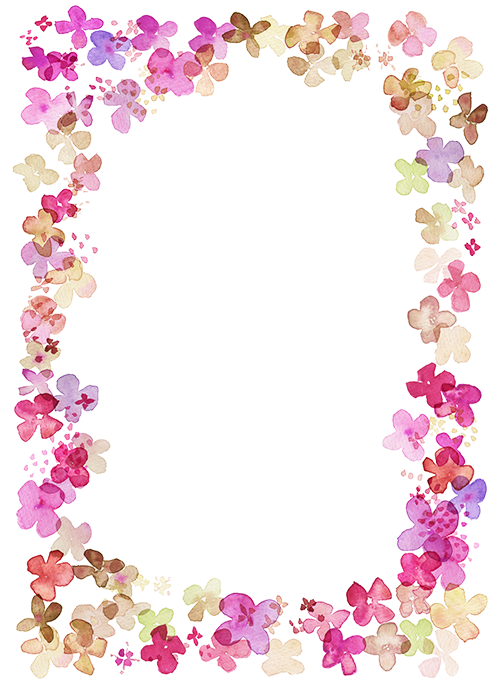一度の声かけで起きてくださらないのもいつものことだ。
声をかけても、軽く揺さぶっても、千早様は眉一つ動かさない。
根気よく何度も何度も声をかけ続けると、ようやく、千早様の眉がぐぐっと寄った。
同時に、わたしを抱き込む腕に力がこもる。
「……ユキ、まだ夜だ」
「夜ではございません、朝ですよ。ほら、窓の外も白んでいます」
「知らないのか、陽が完全に上るまでは夜というんだ……」
「何をおっしゃっているんですか千早様」
寝ぼけているのだろうか、千早様がよくわからないことを口走る。
「お日様が完全に登れば、朝ではなくお昼だと思います」
「俺が朝と言えば朝なんだ……」
無茶苦茶な。
わたしを抱き込んだまま再び深い眠りに落ちようとする千早様に、わたしは慌てる。
声をかけても、軽く揺さぶっても、千早様は眉一つ動かさない。
根気よく何度も何度も声をかけ続けると、ようやく、千早様の眉がぐぐっと寄った。
同時に、わたしを抱き込む腕に力がこもる。
「……ユキ、まだ夜だ」
「夜ではございません、朝ですよ。ほら、窓の外も白んでいます」
「知らないのか、陽が完全に上るまでは夜というんだ……」
「何をおっしゃっているんですか千早様」
寝ぼけているのだろうか、千早様がよくわからないことを口走る。
「お日様が完全に登れば、朝ではなくお昼だと思います」
「俺が朝と言えば朝なんだ……」
無茶苦茶な。
わたしを抱き込んだまま再び深い眠りに落ちようとする千早様に、わたしは慌てる。