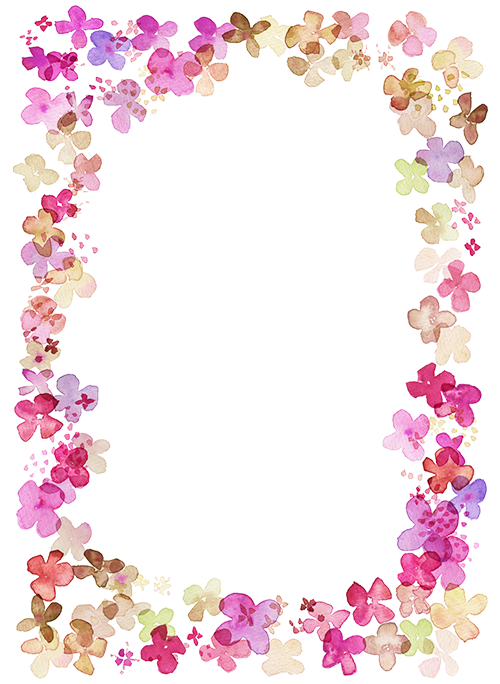千早様と手を繋いで歩く。
昨日と今日で、千早様との距離がぐっと近くなったような気がして、彼の隣にいるだけでどきどきと心臓がうるさくなった。
……わたし、千早様と結婚するのね。
時間が経つほどに、じんわりと喜びが胸の中に広がっていく。
昨日の今日だ。
恐れ多いという感情が消えてなくなったわけではないけれど、今はそれ以上に、安堵というのか、千早様の隣にいさせてもらえる権利をいただいたことが、どうしようもないほどに嬉しかった。
だけど、婚礼の前にどうしても聞いておきたいことがあって、わたしは千早様を見上げた。
「あの、千早様。このようなことを聞くのは失礼かもしれないのですが……、あの、わたしを娶るということは、鬼の頭領のお血筋に、道間の血が混じると言うことになりませんか?」
妻になるのだ。そのうち、子ができることもあろう。その子が、わたしの血で嫌な思いをしないかどうか、わたしはどうしても不安だった。
すると、千早様は不思議なことを聞かれたと言わんばかりに目を丸くした。
「何を言うのかと思えば、そのようなくだらないことを気にしなくてもいい。それに、そもそも道間には鬼の血が混じっているだろう」
昨日と今日で、千早様との距離がぐっと近くなったような気がして、彼の隣にいるだけでどきどきと心臓がうるさくなった。
……わたし、千早様と結婚するのね。
時間が経つほどに、じんわりと喜びが胸の中に広がっていく。
昨日の今日だ。
恐れ多いという感情が消えてなくなったわけではないけれど、今はそれ以上に、安堵というのか、千早様の隣にいさせてもらえる権利をいただいたことが、どうしようもないほどに嬉しかった。
だけど、婚礼の前にどうしても聞いておきたいことがあって、わたしは千早様を見上げた。
「あの、千早様。このようなことを聞くのは失礼かもしれないのですが……、あの、わたしを娶るということは、鬼の頭領のお血筋に、道間の血が混じると言うことになりませんか?」
妻になるのだ。そのうち、子ができることもあろう。その子が、わたしの血で嫌な思いをしないかどうか、わたしはどうしても不安だった。
すると、千早様は不思議なことを聞かれたと言わんばかりに目を丸くした。
「何を言うのかと思えば、そのようなくだらないことを気にしなくてもいい。それに、そもそも道間には鬼の血が混じっているだろう」