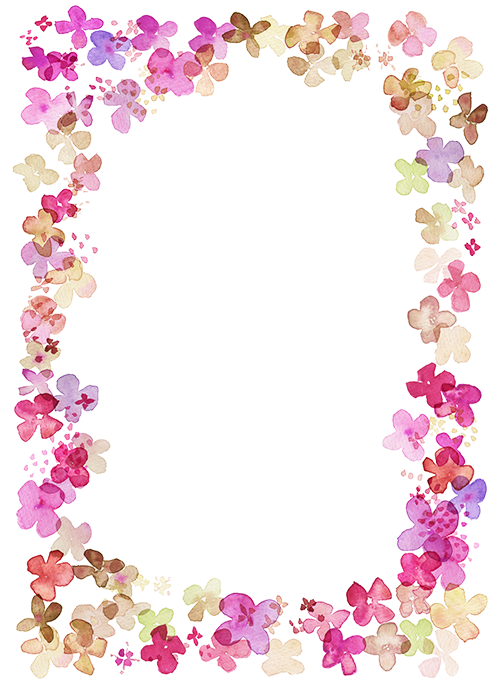着るのはわたしなのに、完全に置いてきぼりにされていた。
わたしが口を挟める雰囲気でもないのだけれど、話を聞いていると、祝言の仕方は人とほとんど変わらないらしい。
強いて言えば、帝都では最近、西洋風の結婚式が流行っているらしいのだけど、鬼の里では伝統を重んじて古来の方法で行うと言うことくらいだろうか。
もっと言えば、西洋風の結婚式を挙げるための教会が、ここにはないらしい。
母子の会話に口を挟めないのはわたしだけではないようで、お着物を持って来てくださった店主様も弱り顔でお二人を見ていた。
柄を決めたら、これから反物から作るそうなのだが……、逆を言えば、早く柄を決めないと、いつまでたってもお着物が仕立てられない。
わたしとしては、持って来ていただいた見本をお借りしてもいいのではないかと思うのだけれど、千早様は頭領様だ。頭領様の祝言に、そのようなみっともないことはできないと言う。
「あ、あの、お茶をお持ちしますね……」
母子の口論はまだ続きそうなので、わたしが店主様にお茶をご用意しようと部屋を出て行こうとしたそのときだった。