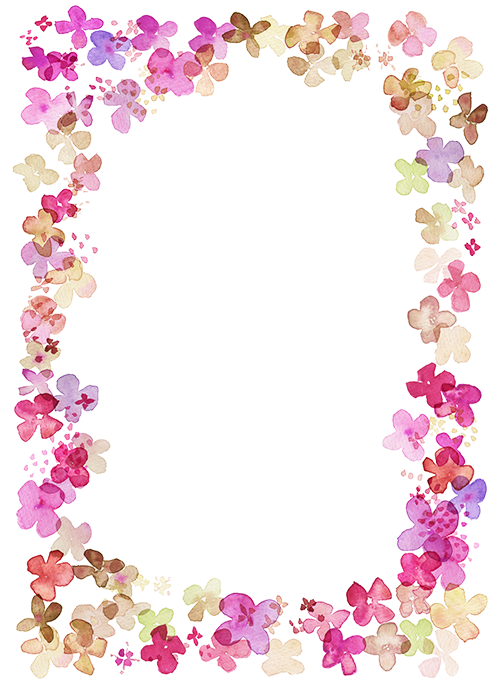うずくまったままのわたしに、彼は忌々しそうに言う。
女狐なんてはじめて言われた。
何の力もないちっぽけなわたしが「女狐」なんて呼ばれるとは――、その言葉が決して誉め言葉ではないことはわかったけれど、なんだかおかしくなる。
彼はわたしを、道間の人間と警戒しているのかもしれない。
魑魅魍魎を払う力もなく、父から忌み嫌われていたわたしなんて、警戒する必要はどこにもないだろうに。
「……ふふ」
「なにがおかしい」
「いえ……」
寒さで、わたしの頭は動きが鈍くなっていたのかもしれない。
この状況で笑えた自分に、わたし自身が驚くと同時に、ああ、それもそうかと得心する。
――一人で死に逝くさだめだと思っていたのに、誰かに看取られることが……たとえそれが、わたしを憎んでいそうな鬼だとしても、それが、わたしは嬉しいのだ。
女狐なんてはじめて言われた。
何の力もないちっぽけなわたしが「女狐」なんて呼ばれるとは――、その言葉が決して誉め言葉ではないことはわかったけれど、なんだかおかしくなる。
彼はわたしを、道間の人間と警戒しているのかもしれない。
魑魅魍魎を払う力もなく、父から忌み嫌われていたわたしなんて、警戒する必要はどこにもないだろうに。
「……ふふ」
「なにがおかしい」
「いえ……」
寒さで、わたしの頭は動きが鈍くなっていたのかもしれない。
この状況で笑えた自分に、わたし自身が驚くと同時に、ああ、それもそうかと得心する。
――一人で死に逝くさだめだと思っていたのに、誰かに看取られることが……たとえそれが、わたしを憎んでいそうな鬼だとしても、それが、わたしは嬉しいのだ。