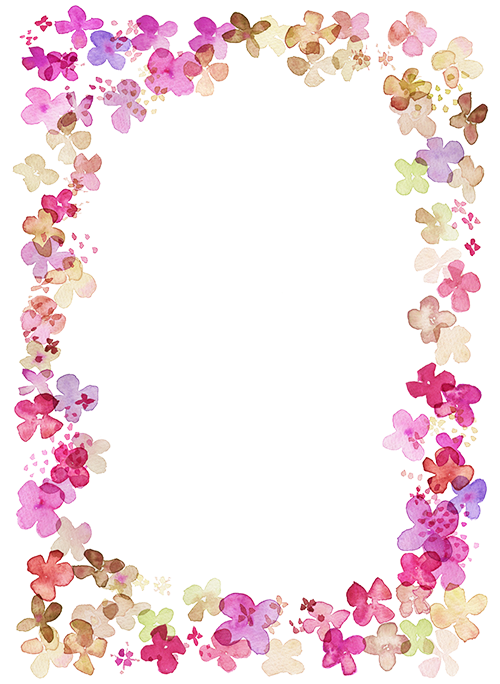「……申し訳ありません」
本当に、何故覚えていないのだろう。
気を失っていたのだろうか。だけど、千早様が驚いているようなので、少なくとも途中までは意識があったものと思われる。
しょんぼりしていると、千早様がわたしの髪を梳くように撫でながらふっと笑った。
その綺麗な微笑みに、自然と視線が釘付けになる。
「なるほど、あれは無意識下、か」
どこか楽しそうな声に、わたしはますますよくわからなくなった。
わたしは一体、何をやらかしたのだろう。絶対何かやらかした気がする。
「そんな顔をするな。問題を起こしたわけではないからな」
千早様はそのときの様子を思い出すように目を細めた。
「お前は、農村地にある農具入れの小屋の中に閉じ込められていた。それはわかるか?」
「はい」
どこに閉じ込められていたのかはわからないけれど、小屋の中に農具が詰めれていたので農具入れだろうなとは思っていた。
本当に、何故覚えていないのだろう。
気を失っていたのだろうか。だけど、千早様が驚いているようなので、少なくとも途中までは意識があったものと思われる。
しょんぼりしていると、千早様がわたしの髪を梳くように撫でながらふっと笑った。
その綺麗な微笑みに、自然と視線が釘付けになる。
「なるほど、あれは無意識下、か」
どこか楽しそうな声に、わたしはますますよくわからなくなった。
わたしは一体、何をやらかしたのだろう。絶対何かやらかした気がする。
「そんな顔をするな。問題を起こしたわけではないからな」
千早様はそのときの様子を思い出すように目を細めた。
「お前は、農村地にある農具入れの小屋の中に閉じ込められていた。それはわかるか?」
「はい」
どこに閉じ込められていたのかはわからないけれど、小屋の中に農具が詰めれていたので農具入れだろうなとは思っていた。