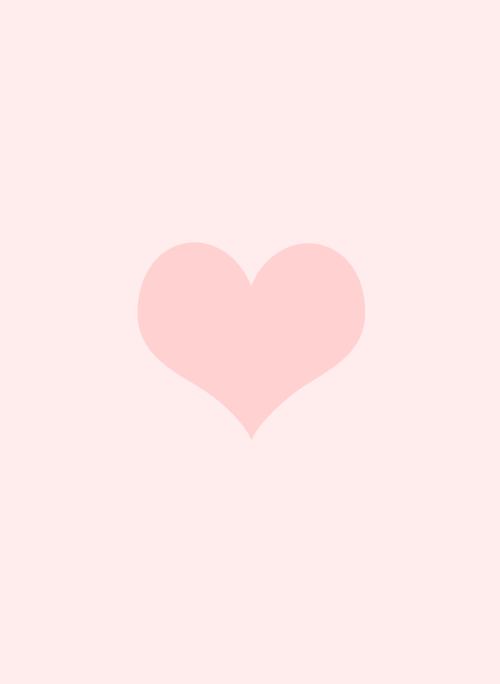「どう…思う?」
窓の外にはすっかり茜色に染まった空が見える。
私はただ彼の返事を待つ。
「……つまらん」
無駄に整った顔をこれでもかと歪め、彼は告げた。
「…はぁ⁉︎」
「なんっ、だよ!その反応。お前が感想を教えてくれって言うから、わざわざ三十分もかけて読んでやったのによ‼︎」
「結構自分的には自信作だったんだけどなぁ〜」
「辛口評価で良いって言ったよな?」
「言いました…」
「じゃあ、一つ一つ言ってく。この小説のダメなところをな!」
ひぃぃ…
「まず、心理描写が甘い。これ、一応恋愛小説なんだろ?よくある感動系にしたかったんだろうけどさ、全然感情移入できないから泣けねぇ」
「はぁ…」
私はため息をついた。
だけど、それに構わず、批評は続いた。
「第一、無駄な文章が多すぎる。正直読みづらい。同じような描写を何回も使ったりしてるだろ。あとはそうだな…」
「もういい!もういい!続きはメールで教えて」
面と向かって自分の小説の批判を受けるのは、
精神的にかなりきつかった。
こんなので本当にプロになれるのかなぁ、私……
「わかったよ。まあ、あくまで俺個人の感想だから、そこまで重く受け止められる必要もねぇけど」
あれ、発言内容と声色が急に優しくなった。
どうした?
さっきまでのとげとげしさはどこへ行ったの??
こほん、と咳払いをして彼は再び口を開いた。
「ただ、ひとつ確実なのは」
「確実なのは?」
彼は大きく息を吸って、
「お前は恋愛小説を書くのに向いてないってことだ‼︎」
人差し指を立て、険しい表情で言い放った。
「え…」
恋愛小説を書くのに向いてない…か。
薄々自分でも気づいていた事実だけど…。
他人から断言されると、より実感が湧いてしまって辛い。
「だって…仕方ないじゃん!
そもそも私……恋愛経験ゼロなんだから!」
気が付けば、そう叫んでいた。
「え、マジかよ……」
何で、ちょっと引いてんのよ。失礼な奴ね。
「そ、そうよ!だから私だって、リアルな経験さえあればもっと良い恋愛小説を書けるはずなの!」
「なるほど…ね」
にやり。
まさに、そんな表現が似合う笑みを彼は浮かべた。
「じゃあ、俺から一つ提案してもいいか?」
一体何を言い出すんだろう。
こいつのことだ、どうせろくでもない提案だろう。
「なぁ。次の日曜、俺と…」
「デートすることになったぁ〜〜⁉︎」
教室中の視線が私たちに集まる。
「ちょっと!声が大きいって‼︎」
私こと菊池瑠夏(17)は、
慌てて親友・由梨の口を塞いだ。
今は昼休みだから、
教室にそこまでの人数はいなかったのが
不幸中の幸いだ。
「ごめん、悪かったって!
でも増本も聞いてないしさぁ」
「ほんとに?」
疑わしかったので、一応私は親友の目線の先を辿ってみた。
慧翔は、ヘッドホンを装着し単語帳をペラペラとめくっている。完全に自分の世界に入ってるって感じだ。
何をしていたかって?
私は、例の彼…改め増本慧翔とのやり取りについて由梨に話を聞いてもらっているところだった。
だから、本人にその話を聞かれたらマズいというわけだ。
「あいつ、何で急にデートとか言ってきたんだと思う?」
「そりゃあ、瑠夏が恋愛小説を書くには、リアルな経験が必要なんだーとか言ったからでしょ?」
「いや、それはそうなんだけどさぁ〜。普通嫌じゃない?好きでもない女とデートとか。だから、何かあいつらしくない提案だなぁって思ってさぁ…」
「…瑠夏のことが本気で好きなんじゃない?」
ミートボールをピックでつまみながら由梨が言った。
「いや、ないない!可能性としては一瞬考えたけどね??だって、私らただの友達だよ?そもそも、私みたいに口うるさい女を好きになるはずないじゃん‼︎」
……いや、待てよ?
あいつは以前、土日は勉強をするためにあるのだから、遊ぶに行くなんて時間の無駄だとか言っていた。
普通、そんな考えの奴がわざわざ貴重な休日を潰してまで、私をデートに誘うか?
それってやっぱり、
私のことが好き……だから??
って、うぬぼれすぎかな。
「あーもー!考えれば考えるほど、分かんないよ」
「……この鈍感」
「なんて言った?」
「もーいい!とにかく、明日のデート楽しんできなよ?」
親友は何故か不機嫌そうな顔だ。
あのー、表情と発言が一致してないんですけど。
ツンデレですか??
「引っかかるところはあるけど、話し聞いてくれてありがと」
「うん、ファイトだよ。瑠夏!」
〈デート当日〉
「ふあ〜あ…」
私は大きくあくびをしながら、靴紐を結び直した。
昨日は色々なことを考えてしまって、結局眠りについたのは三時頃だった。
だから、今の私は完全なる寝不足状態。
ちなみに両親には、友達と遊んでくるとだけ伝えている。
デートに行ってくる、なんて言ったら変な探りを入れられそうで怖いからね。
今、私は待ち合わせ場所である公園へと向かっている途中。
今日のデートの予定はこう。
まず映画館へ行き、映画を楽しむ。
それから近くのランチを取って正午頃に解散。
慧翔は急遽、午後から塾が入ってしまったらしく…
デートは午前中だけにしようと決まった。
ちなみに私の服装はというと…
花柄のロングワンピースに、ベージュのケーブル編みカーディガンを羽織った、春らしいガーリーコーデ。
…って、そんなことはどうでもいいか。
なんて、考えていたら、待ち合わせ場所の公園に到着した。
腕時計に視線を落とすと、約束の時間まであと十五分もあった。
うーん、少し早かったかなぁ…
暇つぶしになるかな、と思い私は何となく慧翔とのラインを遡り始めた。
そこでは、他愛もない会話の数々が繰り広げられていた。
ー増本慧翔。
私のクラスメイト兼男友達。
出会いは高校一年生だった去年。
同じクラスになり、何となく話してみたら割と気が合って。
更には同じアーティストのファンだということも発覚して…
それから私たちはすぐに気心の知れた仲になった。
私にとってあいつは、恋愛的じゃない意味で一緒にいると心が落ち着く…
現在進行形で、そんな存在なんだ。
ただ、そう言っても周りは中々信じてくれず、
「ほんとは、あんたたちデキてるんじゃないの?」
なんてニヤニヤと問い詰めてくるわけで……
そのたび、私と慧翔は
「いやいやいや!違うから!私たち、男女の友情成立してるから!」
「瑠夏のいう通りだ!お前らの期待するようなことは何もねぇよ」
といった風に全力で誤解を解いてきた。
……だから。
今日のデートが終わっても、私たちがお互いに恋愛感情を抱くことはないし。
大人になったら、それぞれにパートナーを見つけて家庭を築いていくことになるんだろう。
私たちは一生、ただの友達だ。
「ねーねー、そこのお姉さん!」
突然若い男の声が聞こえ、私は顔を上げた。
そこには髪を明るく染めた、いかにも軽薄そうな男がいた。
よく見ると、彼は同じような容姿の男を二人引き連れている。
「え、私に話しかけてます?」
「そーそー!お姉さん、可愛いなぁと思ってさぁ」
「俺らと今から遊ばねぇ?」
「なんでも奢るよー?」
男たちがヘラヘラと言いながら、私につめ寄った。
うわっ、香水の匂いがすごい……
「あ…あのっ……」
「やめてください」って言いたいのに、口が思うように動いてくれない。
「きゃあっ」
突然、ナンパ男の一人が私の腕を掴んだ。
もの凄く強い力だから、振り払うことすらできない。
「なぁお姉さん、早く決めてくんね?」
「とっとと、何か言えよ!」
男たちが形相を変え、怒鳴り始めた。
どうしよう…
このままだと、殴られるのも時間の問題だ。
誰か、助けて…
恐怖でうつむいてしまったその時。
「おい、お前ら何やってんだ」
背後からドスの利いた、若い男の声が聞こえた。
一瞬、ナンパ男たちの仲間が来たのかと思ってしまった。
でも、私はその声に聞き覚えがあった。
振り向くと、そこにいたのは予想通りあいつだった。
「慧翔‼︎」
助けに来てくれたんだ…!
そう分かった瞬間、一気に肩の力が抜けた。
「何だぁ、お前⁉︎」
「邪魔すんじゃねぇ!いま、いいとこなんだよ」
「お前もこのコ狙いか?渡さねぇからな」
ナンパ男たちの怒りはヒートアップした。
だけど、そんな彼らにも慧翔が怯む様子はない。
「それはこっちのセリフだよ。早く手、離せ。この子、俺の彼女なんだけど」
かかかっ、かのっ……
「「「彼女ォ!?」」」
まるで、私の気持ちを代弁するかのように、ナンパ男たちが声を上げた。
「チっ、男いたなら、最初から言えよ」
「そーだそーだ!もう行こうぜ」
そんな捨て台詞を吐きながら、男たちは走り去っていった。
すると、さっきまでの騒々しさが嘘のように、
私たちの間に沈黙が流れた。
「あの、助けてくれてありがと」
「別に。お前に怪我とかがなくてよかった。ただ…」
「ただ?」
変なところで言葉を切るものだから、思わず聞き返してしまった。
「お前、自分が可愛いってこと、少しは自覚しろよ…」
慧翔は耳をほんのりと赤く染め、消え入りそうな声で言った。
「今日の服、すげぇ似合ってる」
「えっ…?」
おかしい。
これまでなら、こんなこと言われても、冗談として受け流せたのに……
今は胸が苦しくて仕方がない。
「ははっ、照れてやんの」
「うっ、るさい…あんたも……その、今日
かっこいいと思うよ……?」
そう答えると、
「……ばか」
慧翔は小さくそう言って、顔をそっぽに向けた。
今日の慧翔は、白いフード付パーカーに
グレーのテーパードパンツのシンプルコーデ。
だけど、いつもは下ろしている前髪を両眉の見えるセンター分けにしていて毛先もワックスで遊ばせている。
……気合、入ってるなぁ。
こんなのっ、まるでほんとのデートみたいじゃない。
それにさっきから私たちの間に流れる空気は甘ったるくて、息が詰まりそうになる。
「は、早く行くぞ」
「う、うん」
会話もぎこちなくて、いつもの私たちらしくない。
慧翔はただの友達のはずなのに…
こんなの絶対変だよ。
◇
公園を出た後、私たちは十分弱歩き、無事映画館に到着した。
「ねぇねぇ、何観る⁉︎」
「俺は何でもいいよ。瑠夏は観たいやつとか無いの?」
「あのねホラー映画なんだけどっ、いま超バズってるやつで!すごい面白いらしくて、観たいんだよね」
「ふぅん。でもお前ホラーとか苦手じゃなかった?」
うっ…
「そ、そうだけどっ!観てみたら意外と怖くないかもしれないしさ」
「まぁ、それもそうか。じゃあ、観ようぜ」
「うんっ!楽しみだなぁ〜」
私は軽やかな足取りで、
チケット売り場へと向かった。
◇
『やめて!!近寄らないで!』
遂に女性は、ナイフを持った奇妙な男に部屋の隅まで追い詰められてしまった。
『キーキッキッキッ!』
男は恐ろしい笑い声を上げたかと思えば、女性の胸に深くナイフを突き刺し…
『ギャアアァァ!!』
断末魔と共に女性の体からは、血飛沫があがった。
ひいぃぃぃ!!
そのあまりにもおぞましい光景に、
私は震え上がった。
幽霊が出てくるホラーかと思ってたのに、スプラッター系映画だったなんて……
こんなの予告編詐欺にも程があるよ‼︎
これが…あと、一時間半も続くなんて、
私耐えられるかな。
やっぱり、ホラーなんかやめておけば良かった……
ん?
突然、左手に程よい重みと温かさが伝わった。
隣に目を向けると、その理由はすぐに分かった。
慧翔が、私の手を優しく握っていたのだ。
そのまま、顔を上げると、
澄んだ瞳が私の姿を捉えた。
慧翔は何やら、口をパクパクと動かしている。
え、どういうこと?
私は、彼の唇の動きをじっくりと観察してみた。
お、れ、が?
『俺が居るから、安心しろ』
えっ、読み間違いじゃないよね??
不安がスッと消え…
同時に心臓が落ち着きなく、音を立て始めた。
『ありがとう』
そう返すと、暗闇でもはっきりと分かるほど
頬を紅潮させ、慧翔はそっぽを向いてしまった。
それから、「馬鹿」とでも言うように私の手を、
強く握り直した。
◇
映画を観終えた私たちはランチを取ろうと、近くのカフェに入った。
窓際の席へ案内され、そこに向かい合わせで座った。
「お待たせしましたー。バナナキャラメルパンケーキとカフェモカ。ミックスサンドとコーヒーになります」
若い店員さんによって、目の前にお皿やコップが
次々と置かれていく。
「ごゆっくりどうぞ〜」
店員さんがキッチンへと戻っていくのを見届けてから、私は口を開いた。
「…ねぇあんた、お昼それだけで足りるの?」
「だって腹減ってねぇし」
「あのねぇ!育ち盛りなんだから、もっと食べなさいよ」
私が冗談っぽく、頬を膨らませると、
「お前はおかんかよ」
慧翔がクスクスと笑った。
そうそう、これだ。
今日はドキドキさせられっぱなしで、
普段の感じを忘れちゃってたけど……
慧翔とは、いつもこういう雰囲気で話していたんだった。
やっぱり私たちには、友達っていう関係が一番似合ってるような気がするよ。
どうか、もうこれ以上こいつが心臓に悪い事を、言い出しませんように……
と、思ったのも束の間。
「なぁ、そのパンケーキ美味い?あーんして?」
全く、この男は…!
「まだ、私一口も食べてないんだけど」
「やだ。先、俺によこせよ」
いやいや、男友達に「あーん」とかしたくないんですけど。
何と言い返そうか迷っていると、
「……」
慧翔が、無言で冷たーい目線を送ってきた。
伊達にこいつと友達をやっていない私には分かる。
慧翔のこの表情は「俺に逆らうな」と同義だと。
「はぁ…仕方ないな」
私は猛獣にエサやりをするかのごとく、恐る恐るフォークを差し出した。
形の良い桜色の唇が、フォークの先の獲物を捕らえた。
それから数秒の沈黙を挟み、
「…すげぇ美味い」
余りにも典型的な感想を伝えてきた。
「そりゃあ〜このカフェ、どのレビューサイトでも星五つだからねぇ」
「違ぇよ」
「は?」
意味が分からず、首を傾げる私。
「お前が食わせてくれたから、特別美味く感じたんだよ。言わせんな、馬鹿…」
口元を手で抑え、瞳を潤ませながら、こちらを真っ直ぐ見つめる慧翔。
初めて見る表情に思わず、どくん、と胸が高鳴った。
「瑠夏、好きだ」
…スキ?
すき?
好き。
言葉の意味を理解した途端、顔が熱を帯びていくのが分かった。
心音が邪魔をして、上手く言葉がまとまらない。
「分かってる。俺なんて、眼中にないってことくらい」
「ちがうっ…」
声が震えたけれど、私は必死に言葉を紡いだ。
「私も慧翔が好きだよ」
「…ほんとに?」
無言でこくりと頷く。
「俺と…付き合ってくれないか」
「もちろん!」
こうして、私たちはめでたく恋人になった。
お互いの想いを打ち明けた後、ようやく私たちは食事を始めたわけだけど…
緊張していたからなのか、肝心なパンケーキの味はよく分からなかった。
◇
カフェを出た後、私は慧翔を塾まで送ることになった。
私から提案したわけではなく、せがまれたので仕方なく…という感じだ。
歩き始めてから、約十五分が経った。
私はずっと気になっていたことを訊ねてみた。
「ねぇ、いつから私のこと好きだったの?」
「覚えてないくらい前から。ずっと好きだった」
「へ、へぇー。そうなんだー」
平静を装ったものの…
余りにも真っ直ぐなその言葉に、私の心臓は今にも暴れ出しそうだった。
「何だよ、その反応。そういう瑠夏はいつからなんだよ」
「今日だよ」
「えっ?」
よっぽど驚いたのか、慧翔の声が裏返った。
「今日デートをしなかったら、慧翔とは一生友達だった気がするんだ」
「瑠夏は友達のままの方が良かったか?」
私は首を横に振る。
「確かに今日、慧翔を意識し始めちゃった時は戸惑ったけど…今は彼女になれてすごい幸せだよ」
この発言を、「友達」という関係にこだわっていた過去の自分が聞いたら、すごく驚くんだろうなぁ。
「デートに誘ってくれてありがとね」
私はニッコリと笑いかけた。
「そういうの良いから」
あぁ、目を逸らされた。
本当は嬉しいくせに、素直じゃないなぁ。
「そろそろ着くぞ」
慧翔につられて前を見ると、確かに、塾の看板が目視出来る距離まで近付いていた。
「さっきから、思ってたんだけどさ」
「どうした?」
慧翔はくるりとこちらに顔を向けた。
「何で手、繋いでくれないの?」
私、手汗まみれとかじゃないよね…?
もしそういう理由だったら、どうしよう⁉︎
「あー、それはご褒美だから。お預けな」
「え?」
「今日の経験を活かした恋愛小説を一作書け。
そしたら、ご褒美として手繋いでやるから」
命令口調であることも気にならないくらいの名案だった。
「慧翔、天才じゃん!」
「だろ?一石二鳥ってやつだな」
「うんっ、今日帰ったら早速書き始める……っ⁉︎」
突然、体が引き寄せられたかと思えば、目に飛び込んできたのは一面、白の世界。
耳元で鳴る「どくっどくっ」という音。
心地よい温かさと、漂う甘い香り。
私、いま抱きしめられてる。
大きな手が私の背中をぽんぽん、と叩く。
「ごめん、我慢できなかった…小説、期待してる」
そう囁く声は、いつもよりうんと柔らかくて。
「うん、頑張ります…」
再び鳴り出した鼓動は、しばらく止みそうにない。