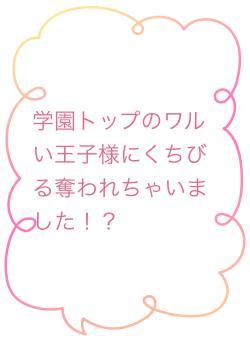「あの公園で、俺と会ったこと覚えてる?」
日が沈みゆく住宅街を駅前のスーパーへと向かって歩きながら、彗くんは私に訊いた。
「もちろん覚えてます……彗くんに助けてもらったから」
「俺、何もしてないけどね。それより紗宇が泣き出して、なかなか泣き止まなくて、すっごく困ったことはよく覚えてる」
「ご、ごめんなさい……」
「いや、はじめは俺が怖くて泣いてるのかと思ってたから」
「え……私は助けてもらって、安心して……」
「それがそのときの俺にはすぐにわかんなくてさ。思いきって泣いてる紗宇の頭撫でたら、ちょっとづつ笑顔になりながら『ありがとう』って言ってくれて、俺のことが怖いわけじゃないんだって思ったらなんか……うれしかった」
私の中での彗くんの記憶と、彗くんの中での私の記憶。
少しづつ重ねていくとセピア色みたいな思い出が、色づいていく気がした。
「彗くんのこと……私は、怖いと思ったことないです」
「校内で俺のこと探してまた会いに来たくらいだもんな。噂なんて気にかけて、わざわざ謝りに」
「だって私のせいで、いろいろ……」
「俺も紗宇に謝りたかったからうれしかった。……引っ越すって俺が言ったときも、泣き出しそうな顔して。こんな顔してくれる子いるんだなってうれしかった」
日が沈みゆく住宅街を駅前のスーパーへと向かって歩きながら、彗くんは私に訊いた。
「もちろん覚えてます……彗くんに助けてもらったから」
「俺、何もしてないけどね。それより紗宇が泣き出して、なかなか泣き止まなくて、すっごく困ったことはよく覚えてる」
「ご、ごめんなさい……」
「いや、はじめは俺が怖くて泣いてるのかと思ってたから」
「え……私は助けてもらって、安心して……」
「それがそのときの俺にはすぐにわかんなくてさ。思いきって泣いてる紗宇の頭撫でたら、ちょっとづつ笑顔になりながら『ありがとう』って言ってくれて、俺のことが怖いわけじゃないんだって思ったらなんか……うれしかった」
私の中での彗くんの記憶と、彗くんの中での私の記憶。
少しづつ重ねていくとセピア色みたいな思い出が、色づいていく気がした。
「彗くんのこと……私は、怖いと思ったことないです」
「校内で俺のこと探してまた会いに来たくらいだもんな。噂なんて気にかけて、わざわざ謝りに」
「だって私のせいで、いろいろ……」
「俺も紗宇に謝りたかったからうれしかった。……引っ越すって俺が言ったときも、泣き出しそうな顔して。こんな顔してくれる子いるんだなってうれしかった」