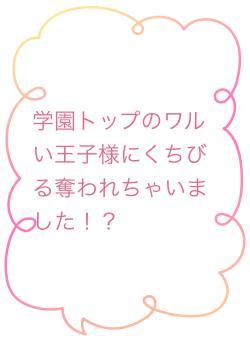彼は相変わらず学ランを羽織るスタイルで、屋上の入り口そばに寄りかかり腕を組み、長い足を投げ出して座っていた。
こちらを見上げる彼は寝ぼけ眼にも見える。
昼寝にはほどよい陽気だ。
寝ていたところを起こしてしまったのかもしれない。
「サボり?」
「……です」
緊張しながら私が肯定すると、彗くんは「そう」と言って笑った。
「座れば?」
優しい笑い方にドキドキしながら緊張で直立する私を見たまま、彗くんは自分の右隣のスペースをポンポンと叩いた。
「……い、いいんですか?」
「特別ね」
「し、失礼します……!」
ぎこちない動きで彗くんの隣に腰を下ろすと、お日様がポカポカとして気持ちがいい。
ちらっと盗み見るように彼へと視線を向ければ目と目が合う。
日差しのせいではなく顔が熱くなるのを感じ、私は彼に向けていた視線をすぐに下に落として膝を抱えた。
こちらを見上げる彼は寝ぼけ眼にも見える。
昼寝にはほどよい陽気だ。
寝ていたところを起こしてしまったのかもしれない。
「サボり?」
「……です」
緊張しながら私が肯定すると、彗くんは「そう」と言って笑った。
「座れば?」
優しい笑い方にドキドキしながら緊張で直立する私を見たまま、彗くんは自分の右隣のスペースをポンポンと叩いた。
「……い、いいんですか?」
「特別ね」
「し、失礼します……!」
ぎこちない動きで彗くんの隣に腰を下ろすと、お日様がポカポカとして気持ちがいい。
ちらっと盗み見るように彼へと視線を向ければ目と目が合う。
日差しのせいではなく顔が熱くなるのを感じ、私は彼に向けていた視線をすぐに下に落として膝を抱えた。