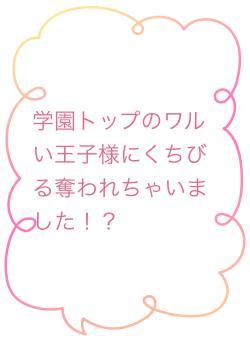「いいなぁ……」
湯川くんが彗くんと“仲良し”と言えてしまう間柄であることを知って、思わず私はそうこぼしていた。
永田くんと湯川くんの視線が私に向けられて、自分が口にしてしまった言葉にはっとなり口元を手で覆う。
「紗宇は井原さんがタイプかよ」
「彗くんかっこいいもんね!」
「う、うん!そんな感じ!」
私と彗くんのことを何も知らない二人は深く追及してくることもない。
それをありがたく思いながら、私は何事もなかったかのようにお弁当のおかずを口にする。
『いいなぁ……』と声に出してしまった自分の気持ちを整理しようにもよくわからない。
私も彗くんと出会って、友達になりたかった気がするけれど。
彗くんにとっては私は年下で、女の子で。
私は彼に一度、公園でピンチを救ってもらっただけの存在である。
『彗さんのこと、好きなんですか?』
ふと、乙部さんにそう訊ねられたことを思い出した。
あのとき『憧れ』だと答えたのは、間違いじゃない。
ヒーローみたいな存在で、強くて、優しくて、かっこいい。
好きと言えばもちろん好きだ。
けれどそれを恋と呼んでいいのかはわからなかった。
湯川くんが彗くんと“仲良し”と言えてしまう間柄であることを知って、思わず私はそうこぼしていた。
永田くんと湯川くんの視線が私に向けられて、自分が口にしてしまった言葉にはっとなり口元を手で覆う。
「紗宇は井原さんがタイプかよ」
「彗くんかっこいいもんね!」
「う、うん!そんな感じ!」
私と彗くんのことを何も知らない二人は深く追及してくることもない。
それをありがたく思いながら、私は何事もなかったかのようにお弁当のおかずを口にする。
『いいなぁ……』と声に出してしまった自分の気持ちを整理しようにもよくわからない。
私も彗くんと出会って、友達になりたかった気がするけれど。
彗くんにとっては私は年下で、女の子で。
私は彼に一度、公園でピンチを救ってもらっただけの存在である。
『彗さんのこと、好きなんですか?』
ふと、乙部さんにそう訊ねられたことを思い出した。
あのとき『憧れ』だと答えたのは、間違いじゃない。
ヒーローみたいな存在で、強くて、優しくて、かっこいい。
好きと言えばもちろん好きだ。
けれどそれを恋と呼んでいいのかはわからなかった。