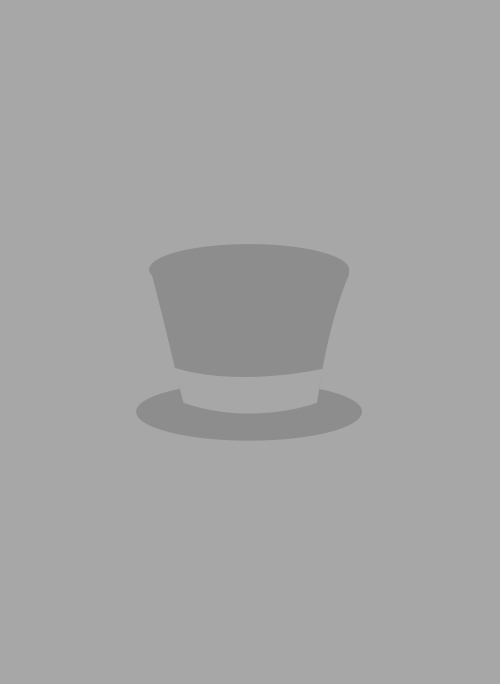やっぱり、私のことをちゃんと視野に入れて、このペンダントを渡した節があるんだと思う。
だって私に「いつでも頼って」て言ってくれるぐらいだし、「こんな生徒面倒くさい」と学校の先生から悪いことをしてないのに陰口を叩かれるくらいに、疎まれてた部分はあるから。
そんな生徒を、「守りたい」って思うのは何か特別なシンパシーのような心がなければ到底手を差し伸べる勇気なんて出ないと思うから。
そう思ったからこそ、私が先生の特別な生徒になってしまうって考えが産まれたからこそ、私の心が拒絶した。
「修先生とこれ以上近づいてはいけない!!遠ざからなきゃ!!」
そう頭の中で、反芻してーーー現在に至るのだ。
「その……婚約の話………本当なのかい?……嘘偽りじゃないんだね?」
零くんが覗き込んだ。
真っ赤な嘘を見抜かれてしまいそうになって、額から汗が滝のように湧き出る。
「………そう。そうなの……」
語尾は萎んでしまった。
何で完璧に嘘つけないんだろう……馬鹿だな……。