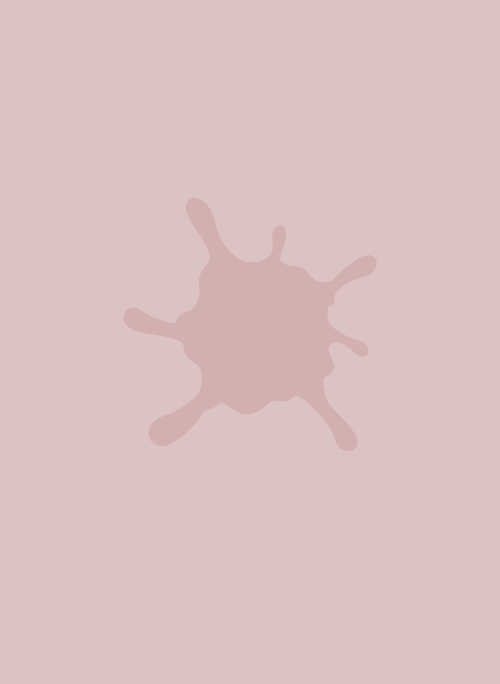「んー…」
…自分で作ったカレーを食卓に並べ。
フューニャと一緒に、いざ食べてみたのだが。
…何だろう。なんかちょっと…なんか違うような。
不味くはない。不味くはないのだけど…ちょっと違う。
味が尖ってると言うか…えぐみを感じる。
フューニャのカレーみたいに、まろやかな美味しさがない。
…何なんだよ、俺は。
フューニャに汚名返上するつもりが。
「えぐいカレーを作る夫」という、新たな汚名を獲得した。
あんなに頑張って作ったのに…。
ずーんと沈み込んだ俺に、フューニャは。
「美味しいですよ、ルヴィアさん」
不味くて食べられませんね、やっぱりまだまだですね。
そう言ってくれても良かったのに。
むしろそう言って欲しかった。下手な慰めが一番傷つく。
「良いんだよ、フューニャ…。不味いって言ってくれれば」
「あら、本当に不味くはないですよ。私は好きです」
「…そうか?」
「えぇ。故郷の郷土料理の味に似てます。懐かしい味です」
「…」
…箱庭帝国の料理って、確か凄く不味いんだよね?
それ、俺…喜んで良いの?
多分喜んじゃいけないよな?
ますますショックを受けた俺に、フューニャはなおも言った。
「何より、あなたが私の為を思って作ってくれたことが伝わってきます。だから美味しいです」
「…でも、これ…失敗じゃないか?なんか…不味くはないけど、ちょっとえぐみがある…」
「これくらい全然許容範囲ですよ。最初から上手に作れる人なんていません。最初は誰だってちょっとミスするものです。この私だってそうなんですから」
え…そうなの?
「フューニャの作るご飯はいつも美味しいだろ…」
「あら。たまにちょっと焦がしたり、塩を入れ過ぎたりするじゃないですか。あなたはそんなときいつも、『このくらい全然気にならない』って言いながらぱくぱく食べるでしょう?」
「…」
それは…だって、本当に気にならないんだもん。
むしろ、ちょっとお茶目なフューニャが可愛いと思ってるくらいで。
「だから私も、美味しいです。ありがとうございます、ルヴィアさん」
「…フューニャ…」
なんて良い子なんだ、お前は。
「おかわり、しても良いですか?」
「うん…。うん…!良いよ」
今度、またカレー作りに挑戦しよう。
次は、もう少し上手く出来るはずだ。
…自分で作ったカレーを食卓に並べ。
フューニャと一緒に、いざ食べてみたのだが。
…何だろう。なんかちょっと…なんか違うような。
不味くはない。不味くはないのだけど…ちょっと違う。
味が尖ってると言うか…えぐみを感じる。
フューニャのカレーみたいに、まろやかな美味しさがない。
…何なんだよ、俺は。
フューニャに汚名返上するつもりが。
「えぐいカレーを作る夫」という、新たな汚名を獲得した。
あんなに頑張って作ったのに…。
ずーんと沈み込んだ俺に、フューニャは。
「美味しいですよ、ルヴィアさん」
不味くて食べられませんね、やっぱりまだまだですね。
そう言ってくれても良かったのに。
むしろそう言って欲しかった。下手な慰めが一番傷つく。
「良いんだよ、フューニャ…。不味いって言ってくれれば」
「あら、本当に不味くはないですよ。私は好きです」
「…そうか?」
「えぇ。故郷の郷土料理の味に似てます。懐かしい味です」
「…」
…箱庭帝国の料理って、確か凄く不味いんだよね?
それ、俺…喜んで良いの?
多分喜んじゃいけないよな?
ますますショックを受けた俺に、フューニャはなおも言った。
「何より、あなたが私の為を思って作ってくれたことが伝わってきます。だから美味しいです」
「…でも、これ…失敗じゃないか?なんか…不味くはないけど、ちょっとえぐみがある…」
「これくらい全然許容範囲ですよ。最初から上手に作れる人なんていません。最初は誰だってちょっとミスするものです。この私だってそうなんですから」
え…そうなの?
「フューニャの作るご飯はいつも美味しいだろ…」
「あら。たまにちょっと焦がしたり、塩を入れ過ぎたりするじゃないですか。あなたはそんなときいつも、『このくらい全然気にならない』って言いながらぱくぱく食べるでしょう?」
「…」
それは…だって、本当に気にならないんだもん。
むしろ、ちょっとお茶目なフューニャが可愛いと思ってるくらいで。
「だから私も、美味しいです。ありがとうございます、ルヴィアさん」
「…フューニャ…」
なんて良い子なんだ、お前は。
「おかわり、しても良いですか?」
「うん…。うん…!良いよ」
今度、またカレー作りに挑戦しよう。
次は、もう少し上手く出来るはずだ。