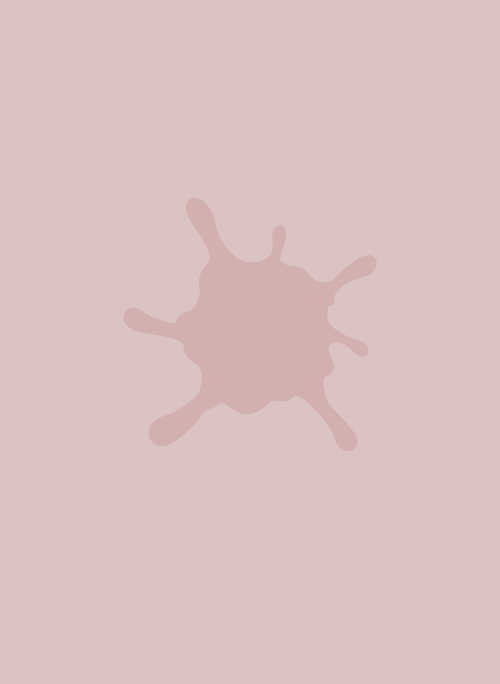「…?」
十歳かそこらのときだったと思う。
その頃トミトゥは、俺に仕えるようになって半年もたっていなかった。
その日、彼女は俺にお茶のティーカップを持ってきた。
ふと見ると、彼女の指には、切り傷のようなものがあった。
それも、一つや二つではない。
ほとんど全ての指に、赤い線が刻まれていた。
一目見るだけで、とても痛そうだった。
その傷を、絆創膏も何もせずに放ったらかしにしているのだ。
「…それ、何?」
思わず、俺は声をかけてしまった。
「え…?」
いつもは、仕事があるときしか使用人と会話をすることはない。
それなのに唐突に質問を投げ掛けられ、トミトゥは戸惑っていた。
俺の言う、それ、が何を指しているのか分からなかったのだろう。
「その傷…何?」
「あっ…申し訳ありません。お見苦しいところを」
トミトゥはさっと指を隠した。
きっと俺が、汚い傷を見たことで気分を害したと思っていたのだろう。
「何であんな傷があるの?」
恥ずかしながら、俺はあんな傷が出来たことはなかった。
だからあれが何なのか、全く分からなかった。
何か、皮膚の病気なのではないかと思っていた。
「何で…と申されましても…。その、昨日は水仕事が多かったもので」
「…」
その傷は所謂、あかぎれ、と呼ばれるものだった。
冬だというのに、井戸から汲んだばかりの冷たい水で洗濯や皿洗いをしていたら、誰だってそうなる。
それなのに、俺は全くの無知だったのだ。
「痛くないの?それ」
放置しているということは、多分見た目ほどは痛くないのだろう。
痛いなら、テープを巻くなり、薬を塗るなりするだろうから。
しかし。
「水に触るときは少々痛みますが…。でも、慣れているので大丈夫です」
…え?痛いの?
「テープを巻けば良いのに。何で巻かないの?」
「…」
トミトゥは困ったような顔をしていた。
今から思えば本当に恥ずかしいが、俺は知らなかったのだ。
例え消毒液や絆創膏程度のものでも、使用人にとっては簡単には手の届かない高級品であったことに。
「…お気遣い、ありがとうございます。若旦那様」
トミトゥは誤魔化すようにそう言って、そそくさと俺の傍から去っていった。
俺は首を傾げたが、しかし、それ以上深く考えることはなかった。
俺と彼女の決定的な差を、次に見せつけられたのは…その一ヶ月ほど後のことだった。
十歳かそこらのときだったと思う。
その頃トミトゥは、俺に仕えるようになって半年もたっていなかった。
その日、彼女は俺にお茶のティーカップを持ってきた。
ふと見ると、彼女の指には、切り傷のようなものがあった。
それも、一つや二つではない。
ほとんど全ての指に、赤い線が刻まれていた。
一目見るだけで、とても痛そうだった。
その傷を、絆創膏も何もせずに放ったらかしにしているのだ。
「…それ、何?」
思わず、俺は声をかけてしまった。
「え…?」
いつもは、仕事があるときしか使用人と会話をすることはない。
それなのに唐突に質問を投げ掛けられ、トミトゥは戸惑っていた。
俺の言う、それ、が何を指しているのか分からなかったのだろう。
「その傷…何?」
「あっ…申し訳ありません。お見苦しいところを」
トミトゥはさっと指を隠した。
きっと俺が、汚い傷を見たことで気分を害したと思っていたのだろう。
「何であんな傷があるの?」
恥ずかしながら、俺はあんな傷が出来たことはなかった。
だからあれが何なのか、全く分からなかった。
何か、皮膚の病気なのではないかと思っていた。
「何で…と申されましても…。その、昨日は水仕事が多かったもので」
「…」
その傷は所謂、あかぎれ、と呼ばれるものだった。
冬だというのに、井戸から汲んだばかりの冷たい水で洗濯や皿洗いをしていたら、誰だってそうなる。
それなのに、俺は全くの無知だったのだ。
「痛くないの?それ」
放置しているということは、多分見た目ほどは痛くないのだろう。
痛いなら、テープを巻くなり、薬を塗るなりするだろうから。
しかし。
「水に触るときは少々痛みますが…。でも、慣れているので大丈夫です」
…え?痛いの?
「テープを巻けば良いのに。何で巻かないの?」
「…」
トミトゥは困ったような顔をしていた。
今から思えば本当に恥ずかしいが、俺は知らなかったのだ。
例え消毒液や絆創膏程度のものでも、使用人にとっては簡単には手の届かない高級品であったことに。
「…お気遣い、ありがとうございます。若旦那様」
トミトゥは誤魔化すようにそう言って、そそくさと俺の傍から去っていった。
俺は首を傾げたが、しかし、それ以上深く考えることはなかった。
俺と彼女の決定的な差を、次に見せつけられたのは…その一ヶ月ほど後のことだった。