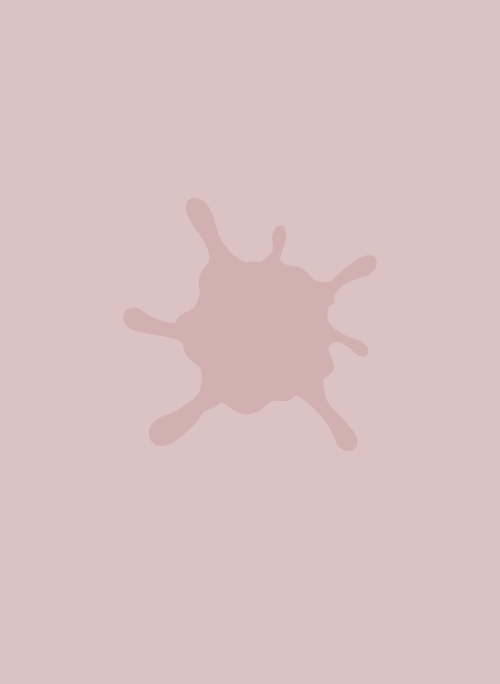ーーーーーー…ルルシーさんの許可をもらって、俺は午後に帰宅した。
帰ったときフューニャが家の中でごそごそしていたら、また叱ってやらなければいけないと思っていたが。
「…フューニャ?」
「…ルヴィアさん。今日は随分と早いお帰りですね」
フューニャはちゃんと、寝室で休んでいた。
よろしい。
「具合はどうだ?少しは熱下がったか」
「もう大丈夫です…」
はいはい。フューニャは元気だろうと元気じゃなかろうと、大丈夫だとか平気だとか言うのだ。
本人の自己申告を信用してはならない。
フューニャの額に触れる。
体感的には…昨日よりは、少しはましになった、かな?
峠は越した…と言っても良いかもしれない。
「薬は飲んだか?」
「…飲みました」
「よしよし。良い子だ」
少し熱は下がったようだが、全快には程遠い。
まだしばらくは、フューニャをベッドに拘束しておかなければならないな。
「…ルヴィアさん、何で今日はこんなに早いんですか」
「うん…?上司に頼んで、早めに帰らせてもらったんだ。フューニャが心配だったからな」
「…そんな、子供でもあるまいに…」
「隙あらば勝手に動き回るから、子供よりタチが悪いよ。フューニャは」
事実を言っただけなのに、フューニャは不満げに眉をひそめた。
「悔しかったら、ちゃんと休んで早く治すんだな」
「…見てなさい。あなたが風邪を引いたとき、絶対やり返しますから」
「残念だったな。俺は馬鹿だから風邪は引かない」
ここ十数年、風邪は引いたことがないぞ。
このときどや顔で勝ち誇っていた俺だが、実はこの数週間後、完全に形勢が逆転することを…俺はまだ知らない。
「それで?フューニャ。昼は何か食べたのか?」
「…何も」
「馬鹿。お粥作ってるから食べろって言ったろ」
ほら見たことか。俺が目を離したらこれだ。
「だって…。お腹空いてないんです」
「しょうがないな…。ヨーグルトや果物なら?切ってやろうか」
「…」
欲しくない…みたいな顔をしているな。
だが、そうはいかない。
「りんごでもすりおろしてこよう。ちょっと待っててな」
「…はい」
俺は寝室を出て、キッチンに向かった。
帰ったときフューニャが家の中でごそごそしていたら、また叱ってやらなければいけないと思っていたが。
「…フューニャ?」
「…ルヴィアさん。今日は随分と早いお帰りですね」
フューニャはちゃんと、寝室で休んでいた。
よろしい。
「具合はどうだ?少しは熱下がったか」
「もう大丈夫です…」
はいはい。フューニャは元気だろうと元気じゃなかろうと、大丈夫だとか平気だとか言うのだ。
本人の自己申告を信用してはならない。
フューニャの額に触れる。
体感的には…昨日よりは、少しはましになった、かな?
峠は越した…と言っても良いかもしれない。
「薬は飲んだか?」
「…飲みました」
「よしよし。良い子だ」
少し熱は下がったようだが、全快には程遠い。
まだしばらくは、フューニャをベッドに拘束しておかなければならないな。
「…ルヴィアさん、何で今日はこんなに早いんですか」
「うん…?上司に頼んで、早めに帰らせてもらったんだ。フューニャが心配だったからな」
「…そんな、子供でもあるまいに…」
「隙あらば勝手に動き回るから、子供よりタチが悪いよ。フューニャは」
事実を言っただけなのに、フューニャは不満げに眉をひそめた。
「悔しかったら、ちゃんと休んで早く治すんだな」
「…見てなさい。あなたが風邪を引いたとき、絶対やり返しますから」
「残念だったな。俺は馬鹿だから風邪は引かない」
ここ十数年、風邪は引いたことがないぞ。
このときどや顔で勝ち誇っていた俺だが、実はこの数週間後、完全に形勢が逆転することを…俺はまだ知らない。
「それで?フューニャ。昼は何か食べたのか?」
「…何も」
「馬鹿。お粥作ってるから食べろって言ったろ」
ほら見たことか。俺が目を離したらこれだ。
「だって…。お腹空いてないんです」
「しょうがないな…。ヨーグルトや果物なら?切ってやろうか」
「…」
欲しくない…みたいな顔をしているな。
だが、そうはいかない。
「りんごでもすりおろしてこよう。ちょっと待っててな」
「…はい」
俺は寝室を出て、キッチンに向かった。