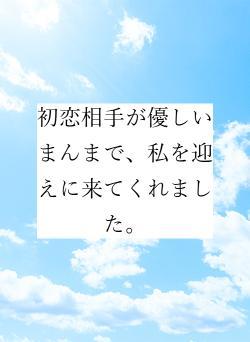朝起きたときから降る雨は、一度も止むことなく降り続いている。試験という制縛から解き放たれた土曜日。傘をさして陽馬を待つ。傘に当たる雨粒はバリバリと音を立て、水溜まりをつくっていく。
「雨の中待たせて悪い 」
黒の傘をさした陽馬が僕の前に現れた。持っている傘は、陽馬の身長からしたら小さく見える。
「いいよ、長時間待ってるわけじゃないから。それより、どこ行くの?」
「実はまだ決まってないんだよな。勇希はどっか行きたいところあるか?」
いや、と思わず言いそうになるが、おそらく陽馬はまだ近所にある店以外は知らないだろう。そう気ままに独断した僕は、「パンケーキ、食べに行かない?」と、口調を柔らかくして聞いてみる。朝食をまともに食べていないこともあり、とりあえず何かで腹を満たしたい気分だった。しかし、陽馬の苦手な甘いもの、しかもパンケーキと口にしたことを、あとになって後悔する。
「パンケーキか。なら、俺のお気に入りの店があるんだけど、そこでも良いか?」
陽馬はそう答えた。お気に入りの店…。陽馬の口からその言葉が発せられたことに、僕は正直驚いた。引っ越してきてまだ三か月も経っていないのに。
「いいよ。お気に入りの店気になるから連れてってよ」
「おう。任せとけって」
陽馬は身を少し縮めながら僕の少し前を歩く。強く降る雨は僕らの身体を冷やしていくだけなのかな。
陽馬に連れて来られたのは、一年前にオープンしたカフェだった。閑散とした商店街に突如オープンし話題となったところだ。僕も以前、母と二人で訪れたことがあったが、メニューにパンケーキがあることは知らなかった。
ドアベルが鳴る。店内でかかっている音楽は、降る雨に対する気持ちをポップなものにしてくれる。
「いらっしゃいませ。何名様でご来店ですか?」
「二人です」
「かしこまりました。それでは、あちらの席でお待ちください」
茶色のエプロンを腰に巻いた店員が、掌で席のある方向を差す。店内は土曜日の割には空いていた。促された席に座り、店員が再び来るのを待った。大学生ぐらいの女性が四人でテーブル席を囲み、ワイワイと話している。女子会と言われる類のものを開催しているのだろう、とまた変な決めつけをしてしまう。そしてカップルが一組、互いに見つめ合いながらストローを咥えている。
「メニューはお決まりでしょうか」
先ほどの店員が伝票バインダーを手に聞いてくる。陽馬は、メニュー表を見ずに、「イチゴヨーグルトパンケーキで」と注文する。僕は立て掛けられていたメニュー表に目を遣るも、「同じ物でお願いします」と伝える。
「イチゴヨーグルトパンケーキがお二つですね。お待ちください」
「お願いします」
目の前には陽馬がいる。普段横に並んで歩いているのとはまた違うドキドキを感じてしまう。
「勇希はさ、ここのパンケーキ食べたことある?」
「いや、初めてだよ。陽馬は何回も来てる感じだよね」
「そう。ここのパンケーキ美味しいからさ、リピートしたくなるんだ」
陽馬はスマホを取り出し、下を向いて操作している。
「へぇ、そうなんだ。陽馬が言うなら間違いなさそうだね」
「おう。間違いないさ」
決め台詞のように言い、右の口角を上げて笑う。
「でも、陽馬って甘いもの苦手じゃなかったっけ?」
「甘いものは苦手だけど、パンケーキだけは、まぁ色々あって…、食べるようにしてるんだよ」
「食べるようにしてるって、ほかの何かを我慢してるってこと?」
「んー、我慢とはまた違うんだよな。食べ終わったら、その理由も含めて話すから」
「わかった」
陽馬は表情一つ変えず、スマホを片手で操作し続けた。真剣な目つきをした陽馬を見つめていると、「勇希、この曲聴いて欲しいんだけど」と突然、自分のスマホとイヤホンを僕に渡してきた。右耳にイヤホンを装着する。「流すよ」と陽馬が言ったため、僕は「うん」と返事すると、再生ボタンが押された。流れ始めたのは、今から四年ほど前に流行ったバンドの一曲だった。普段バンド曲に興味がない僕ですら知っている。
「これ、『One ファイン』って曲だよね? 女子に刺さる歌詞って話題になった」
「そう」
「へー、陽馬ってこんな感じの曲聞くんだね」
「俺にとって、この曲だけは別格なんだ」
「どういうこと?」
店内BGMの曲調が雨に寄り添うようなものへと変わった。
「この曲、お母さんが作詞したんだ」
「そうなの! すごいね」
何でこの曲を聞かされたのか、わからなかった。自慢したいにしても、話の振り方が雑な気がする。曲が終わったため停止ボタンを押し、イヤホンを外す。
「ありがとう」
「聞いてもらえてよかった」
これ以上何も語ろうとする様子は見られない。ますますこの曲をなぜ、今、僕に聞かせようとしたのか、思考は迷宮入りしてしまった。
「陽馬のお母さんって、どんな人なの?」
「えっと…」
陽馬が少し困惑した表情を見せたとき、「お待たせいたしました。イチゴヨーグルトパンケーキです」と店員が僕らの前にパンケーキが乗せられた皿を置き、そしてカトラリーが入ったバケットを二人分並べる。イチゴは照明に照らされて蝋が塗られたように艶々としていた。陽馬の目には、一筋の輝いたものが光り、流れていった。
「こちらに伝票を置いておきますね。では、ごゆっくりとお楽しみください」
「ありがとうございます」
僕らが一礼すると、店員はもっと丁寧な一礼をして戻っていった。
陽馬がパンケーキにナイフを入れる。僕も見様見真似でナイフとフォークを手に取り、パンケーキに差し込む。フワフワとした感触がナイフ越しに伝わってくる。
「ねえ、陽馬。僕、やっぱり待てない。食べ終わるまでなんて、僕、待てないや」
陽馬は小さく首を縦に動かす。視線は僕でも、パンケーキでもないところに向けられている。
「もう、素直に聞く。なんでパンケーキだけ食べるようにしてるの?」
食べ終わるまで待とうとする自分は、そこにはいなかった。気付いたときには口に出し、話終わっていた。陽馬は手に持っていたナイフとフォークを皿の上に置く。カチン、という甲高い音が耳の奥に響いて消える。
「今日、母の誕生日なんだ」
少し暗めの声で答える陽馬。パンケーキの上にトッピングされたイチゴが皿の上に転がった。僕は何か悪い予感がして、慌ててイチゴ
を仲間の元へ戻す。
「そうなんだ。じゃあ、僕といるより家でお祝いしてあげたほうが―」
陽馬はさらにトーンを下げて、しかも、僕が話すのを止めるかのような勢いで話してきた。
「いいんだ。もう、一緒にお祝いすることは無理なんだ。母は…」
乗せ直したばかりのイチゴが、今度はヨーグルトソースの中に吸い込まれていった。
「死んだから」
何かを噛みしめながら言う陽馬。僕は言葉を失った。頭の中は空っぽで、何も整理できない。
「ごめん」
自分の発言のせいで陽馬を傷つけてしまった。そう思ったからなのか、口から出たのは、謝りの言葉だった。これ以外の言葉が見つからず、出てこない状況。謝りの言葉以外、何も言えない。
「勇希が謝ることないよ。いいから、食べよ」
陽馬は明るく振る舞う。が、瞳は嘘をつけないのか、目の奥の輝きは消えていた。それと対峙するようにパンケーキにかけられたヨーグルトソースは照明に照らされ、輝きを放つ。僕はもう一度、「ごめん 」と謝った。陽馬は何も言わず、ただパンケーキを見つめ、再びナイフを入れる。作り笑いの仮面の下を覗き見ることはできそうにない。
傘を閉じ、玄関前の柵に立てかける。傘からは雨粒が落ち、静かにコンクリートを濡らす。風に乗って流れて来る雨は塗装が剥がれた鉄の階段を刺激していく。降る雨はいつか階段を壊すんじゃないかと、気がかりになる。
「ここで待ってて。すぐ呼ぶから」
陽馬はそう言って玄関のドアを閉める。僕は湿気を含み重たくなった空気の中で陽馬を待つ。僕の家の隣に住む円谷さんが、雨の中、ピンク色の傘をさして飼い犬の散歩に出かけていく。犬は傘よりも鮮やかなピンク色の合羽を着せられている。
パンケーキを食べたあと、陽馬の提案で家にお邪魔することになった。雨が降りしきる中、駆け足で帰ってきた僕ら。ズボンの裾や靴下は深水している。でも、気にならなかった。陽馬と一緒に居られるのなら、それでいい。
近づく足音。僕は気を引き締める。ドアが開く。陽馬は服こそ変わっていないものの、黒縁の眼鏡をかけて出てきた。
「お待たせ、入って」
「お邪魔します」
「うん」
狭い玄関に靴を並べる。三足分しか置けないスペースに二足並んだ靴は、とても窮屈そうに見える。
「散らかってて悪いな。なんだったら物どけてもいいから」
「そんなことしないよ」
散らかっているという割には、綺麗に整頓された部屋。六畳ほどしかない室内には、ベッドと勉強机、小さなテレビ、棚が並べられている。玄関入ってすぐにあるキッチンと冷蔵庫は、生活しているという感じがしないほど、整えられていた。
「そこに座って。飲み物お茶しかないけど、いい?」
「ありがとう」
陽馬は冷蔵庫のドアを開ける。冷蔵庫の中に、鍋とペットボトルのお茶が入っているのが見えた。
「はい、これ」
ガラスコップに入っているお茶。中には一個の氷が浮いている。
「ありがとう。いただきます」
僕はお茶を一口飲む。冷えたお茶が喉を潤していく。パチンとグラスの中で氷が弾けた。
部屋の窓に叩き付ける雨。暗くなっていく空。
「陽馬、話の続き…、してくれないか?」
僕はグラスを置く。陽馬は正座をする。
「今まで誰にも言ったことがない内容を勇希に話す。でも、暗い気持ちにならないで欲しい。俺は、勇希が泣く姿を見たくないんだ。いいか?」
僕は頷く。陽馬は喉仏を動かし、ゴクリと音を立て生唾を飲み込む、何か覚悟したかのように。
「二年前の二月八日、母親は僕の前から忽然と姿を消した。連絡もつかない状態でさ。この期間は学校も休んで、父親と俺、あとは母方の親族で母親を探した。警察に捜索願も出したんだ。その間は生きた心地がしなかった。捜索願出して四日後ぐらいに、母親の持ってたスマホが近くの田んぼの中で見つかって。そっから一気に捜索範囲が広がって。十四日の二十二時過ぎ、警察から自宅に連絡がきた。『母親が見つかった』って。時間も遅かったから、その日は会いに行けなかった。翌日、元気な姿で会えると思ってさ、教えられた病院に行ったんだ。警察に案内されたのは、病院の地下だった。扉が開いた先は白い空間に蝋燭が置かれている場所だった。母親の姿見た瞬間、あぁ、死んだんだって。気付いたときには涙が溢れ出してて。こんなの初めてでさ。正直、戸惑った。これから俺はどうやって生きて行けばいいのかなって。不安にもなった。そのとき、僕の隣に父親もいたんだけど、俺を慰めようとしなかった。しかも、なぜか泣いてなかった。今になって、そのことが気になってる」
溢れ出す涙は止まることを知らず、僕を溺れさせていく。
「母親と会ったあと、父親と一緒に、どういう状況で母親が発見されたかっていう話を、警察の人から聞いた。母親は十三日の零時から十四日の一時までの間に、何者かに殴られて、そのうえ腹部まで刺されてた。その当時、警察からは『確実に仕留めるために刺したんだろう』って言われてさ。母親は病院に運ばれたけど、結局、出血多量で死んだ」
陽馬の声は徐々に震え出す。僕は陽馬の目を、姿を、直視することができなかった。
「少しだけ話が逸れるんだけど、俺、パンケーキだけ食べるようにしてるって話しただろ? あれは、大切な母親の存在を忘れないた
めに、母親の誕生日と、母親の月命日には、パンケーキを食べることにしてるからなんだ。僕、幼い頃から甘いもの苦手だったんだけど、母親が家で焼いてくれるパンケーキだけは、砂糖使ってるのになぜか甘くなくて、食べることができたんだ。仕事で忙しかった母親との数少ない思い出のひとつがパンケーキなんだ。母親との思い出や記憶は、年を重ねるにつれて忘れていってしまう。だからこそ、母親を少しでも近くに感じたくて、パンケーキだけは、食べるようにしてる」
なぜあの店のパンケーキを陽馬が選んだのか、何となくわかった気がした。
「パンケーキは、陽馬にとっては大切な存在なんだね」
陽馬は優しく、数回頷いた。
「パンケーキをなぜ食べるかについての話は終わり」
水道から垂れた一滴の水。シンクに到着し、ぼたっという、可愛らしい音を立てる。
「三日後、母親を殺した犯人が逮捕された。これで終わった、終わりだって思ったんだ。でも、この事件の終わりはまだ迎えていなかった」
陽馬の話し方のせいなのか、内容のせいなのか、口の中がどんどん乾いていく。ガラスコップに入っているお茶を流し込む。氷はいつの間にか溶け、お茶と融合していた。陽馬はコップに入ったお茶を喉を鳴らしながら飲む。コップから水滴が滴り落ち、机に着地する。
「僕を殴ってきた奴、母親を殺した犯人の仲間だった。同じ犯罪グループに所属してる奴」
「同じ、グループ、に……」
「警察から話聞いたときに、犯罪グループの主要メンバーの顔写真を見せられたんだけど、殴ってきた奴がその中の一人だった。ソイツは殺人事件に直接関与してないみたいでさ、逮捕されなかったんだよ。俺を見つけたとき、ソイツは『みーつけた』って言いながら近づいてきてさ。なんでこの町にいるのかも、なんで俺を探してたのかも理由はわからないけど、まあ、母親の息子だから、どうせ俺のことが気に食わないとかそんな理由で殴ったんだろうな」
「そ、そん、な、な、んで…陽馬のこ、と」
話そうとしても、途中で言葉が詰まって上手く話せない。絶句した、とはこのことを指すのだろうか。
陽馬はからのガラスコップを手にキッチンに向かう。僕は俯いたまま、止まらない涙を服で拭う。
「悪かったな、こんな暗い話、聞きたくねぇよな。話しといてなんだけど」
コップにお茶を入れながら言う。向けられた背中は悲しそうだった。陽馬は注いだばかりのお茶を飲みながら床に座る。強がっている
のか、涙目になりながらも、零さないようにしているように見えた。
「もう、我慢できない」
僕は後ろからそっと、優しく陽馬を抱きしめる。驚いたのか、陽馬の身体が少し跳ねる。
「陽馬、僕の前では強がらないで。泣きたいときは泣いていいんだよ」
歯を食いしばる陽馬。小刻みに震える身体。僕の手に一粒の雫が落ちる。それはダイヤモンドのように輝きを放つものだった。
陽馬は声を押し殺しながら、しばらく泣いた。僕は陽馬が落ち着くまで、ずっと抱き続けた。
「ごめん、もう大丈夫」
服の袖で零れた涙を拭く。
「ごめんね、突然抱いて。どうしても放っておけなくて」
「謝んなよ。なんか誰かに抱きしめてもらうなんて初めてでさ、驚いたけど嬉しかった」
「はじめて?」
「実は、両親との関係はずっと前から冷めててさ。どう甘えていいのかもわからなかった。でも、勇希に『泣いていい』って言われた
刹那、涙が止まらなくなった。甘えるってこういうことなのかな、って」
陽馬は誰にも甘えることなく今まで生きてきたんだと思うと、胸が締め付けられる。
「これからは僕に甘えて。大丈夫、陽馬のこと受け止めるから」
「ありがとな。勇希」
出会って初めて、本当の陽馬のことを知れた気がした。
陽馬の涙に、僕までも泣きそうになっていたとき、母から一件の電話連絡を受け、一度家に戻ることになった。
「待ってる間に気持ち戻しとく」
「わかった。すぐ戻って来るから」
「おう。待ってるからな」
雨上がりの階段は、少しだけ滑りやすくなっていた。一段ずつ丁寧に降り、家までの道路は全力で走る。
「ただいま」
返事が聞こえなかった代わりに、母と叔母さんが仲良さそうに話している声が聞こえてきた。
「ただいま」
「あら、おかえり」
母は呑気に言う。叔母さんは優雅に紅茶を飲んでいた。
「勇希君、久しぶり」
「はい、久しぶりですね」
叔母さんと会うのは半年ぶりで、どんな口調で話せばいいのか、その都度、距離感がわからなくなる。
「お姉ちゃん、これ。たのまれてたカモミールティーの。三袋でいいんだよね」
「ありがとう。しばらく持ちそうだわ」
「それなに?」
「カモミールっていう花の茶葉。リンとみたいな匂いがしてね、飲んだときにスッキリするのよ」
叔母さんはカモミールの花の画像と共に説明する。
「勇希も一度飲んでみたら?」
「これ、陽馬と一緒に飲んでもいい? 一人じゃ飲めそうにない」
「いいけど、今、持っていく? 小袋になら入れてあげられるよ」
「うん。持ってく」
「わかった。準備するから待ってて」
母はキッチンの戸棚を開け、茶葉を詰めていく。待つ間、叔母さんは僕に対して色々と質問してくる。それに対して僕は、丁寧語で話
したり、少し砕けた口調で話したりと、まとまりがないまま答え続けた。
「はい、できた」
「ありがと。もう一回陽馬ん家に行ってくる」
「はいはい」
茶葉が入った小袋を手に、僕は家を飛び出した。
陽馬の家の前に立ち、声を掛ける。陽馬はドアを開けて「おかえり」と微笑んだ。
「陽馬、これ叔母さんがくれたんだけど、よかったら飲まない?」
「なにそれ?」
「カモミールって花の茶葉。リンゴみたいな匂いで、スッキリとした味がするみたい。実は、僕もまだ飲んだことがないんだよね」
叔母さんから聞いたばかりのことを繰り返す。
「飲んでみたいかも。勇希と初めてを共有したい」
「わかった。じゃあ、ちょっと台所と電気ケトル借りるね」
「どうぞー」
蛇口をひねり、水を入れていると、陽馬は僕の背中に囁いた。
「俺の昔について、もう少し話してもいいか?」
ケトルをセットしてから、「うん、いいよ」と陽馬の目を見て答える。
陽馬と向かい合わせに座る。電源が入れられたケトルは、沸点に向かって走り出した。
「俺、母親がいなくなってから、周りの大人に可哀想な子って言われたり、同級生の親からは、あの子に近づいたらいけない、とか、陽馬君の親なら殺されてもしかたない、とか色んなことを言われ続けた。その当時は我慢して学校に行ってたんだけど、一か月経ったぐらいのときに、ついに精神が崩壊した。そんな俺を見た父親が『私の生まれ故郷で暮らしなさい 』って言われて、連れて来られたのがこの町だった。そのときは、祖父と伯父さんの家で暮らすって話だったんだけど、こんな子とは一緒に暮らせないって言われてさ。暮らせない理由もわからないまま、結局、隣の県にある親戚の家に招かれることになって。これで安定した生活ができるって思ってた」
ゴール間近の湯は、音を立てて僕に知らせる。
「でも、そうはならなかった。親戚の家に引っ越した翌日、父親は誰にも行き先を告げないまま、姿を消した。でも、行方不明届を警
察に出せなかった。祖父が頑なな態度を取ったからな。俺は、そんな祖父も、それに反対しない伯父さんも信じられなくなって。今の今までずっと連絡を取ってない。親戚の人は『きっと帰って来るわよ』と何度も俺を励ましてくれた。あの人は、本当に優しい人だった。表には出さない優しさに憧れるぐらい」
カモミールの茶葉をスプーンで掬い、熱湯を注ぐ。
「中学一年生のときだけ、親戚の家から通える中学に行ってたんだけど、伯父さんの友達の息子が変な噂を流したせいで、ある日から俺の居場所は無くなってた。引きこもる毎日は、楽しいなんて言える状況じゃなかった。そんな俺に、親戚の人は『あなたは一人暮らしをした方がいい』って言ってきた。それで、学生時代の友人を頼って、あの大家さんが経営してるアパートの一室を紹介してもらった。一目見た瞬間にこの部屋を気に入って。この町なら俺はやっていけるって、なんかわかんないけど、自信を手にした気分だった。それがなんだか嬉しくて」
カモミールティーの甘い匂いが部屋いっぱいに立ち込める。
「母親が殺されなければ、冷めきった関係も取り戻せてたのかなって考える日もあった。でも、こんなことが無かったら、俺は今みたいな、勇希と一緒に過ごせる幸せを感じることはできなかったと思う。だから、これは前向きに出来事を捉えないといけないのかなって」
陽馬の目から溢れ出した涙。頬を伝って落ちていく。
「逆境に耐えてきた陽馬は強いよ」
「……え、どういうこと?」
「逆境に耐えたから今の陽馬がいるんだよ? 耐えてなかったら、今みたいに強い陽馬は存在しない」
「そんなこと」
「そんなことあるよ。ほら、カモミールティーも淹れたし、一緒に飲もう、ね?」
「うん。飲む」
ガラスコップにカモミールティーを注ぐ。陽馬は入れたてを口に含み、「ほんとだ、スッキリする」と涙目のまま頬を緩ます。
「ストレスによる疲れとかもほぐしてくれるんだって。どう?」
「うん、新しい感じがいい。たまに飲むのもアリかも」
「だね」
「そのときは、また俺と一緒に飲んでくれよな」
「もちろん」
カモミールの花は、逆境の中で生まれた陽馬そのものだと思った。
「雨の中待たせて悪い 」
黒の傘をさした陽馬が僕の前に現れた。持っている傘は、陽馬の身長からしたら小さく見える。
「いいよ、長時間待ってるわけじゃないから。それより、どこ行くの?」
「実はまだ決まってないんだよな。勇希はどっか行きたいところあるか?」
いや、と思わず言いそうになるが、おそらく陽馬はまだ近所にある店以外は知らないだろう。そう気ままに独断した僕は、「パンケーキ、食べに行かない?」と、口調を柔らかくして聞いてみる。朝食をまともに食べていないこともあり、とりあえず何かで腹を満たしたい気分だった。しかし、陽馬の苦手な甘いもの、しかもパンケーキと口にしたことを、あとになって後悔する。
「パンケーキか。なら、俺のお気に入りの店があるんだけど、そこでも良いか?」
陽馬はそう答えた。お気に入りの店…。陽馬の口からその言葉が発せられたことに、僕は正直驚いた。引っ越してきてまだ三か月も経っていないのに。
「いいよ。お気に入りの店気になるから連れてってよ」
「おう。任せとけって」
陽馬は身を少し縮めながら僕の少し前を歩く。強く降る雨は僕らの身体を冷やしていくだけなのかな。
陽馬に連れて来られたのは、一年前にオープンしたカフェだった。閑散とした商店街に突如オープンし話題となったところだ。僕も以前、母と二人で訪れたことがあったが、メニューにパンケーキがあることは知らなかった。
ドアベルが鳴る。店内でかかっている音楽は、降る雨に対する気持ちをポップなものにしてくれる。
「いらっしゃいませ。何名様でご来店ですか?」
「二人です」
「かしこまりました。それでは、あちらの席でお待ちください」
茶色のエプロンを腰に巻いた店員が、掌で席のある方向を差す。店内は土曜日の割には空いていた。促された席に座り、店員が再び来るのを待った。大学生ぐらいの女性が四人でテーブル席を囲み、ワイワイと話している。女子会と言われる類のものを開催しているのだろう、とまた変な決めつけをしてしまう。そしてカップルが一組、互いに見つめ合いながらストローを咥えている。
「メニューはお決まりでしょうか」
先ほどの店員が伝票バインダーを手に聞いてくる。陽馬は、メニュー表を見ずに、「イチゴヨーグルトパンケーキで」と注文する。僕は立て掛けられていたメニュー表に目を遣るも、「同じ物でお願いします」と伝える。
「イチゴヨーグルトパンケーキがお二つですね。お待ちください」
「お願いします」
目の前には陽馬がいる。普段横に並んで歩いているのとはまた違うドキドキを感じてしまう。
「勇希はさ、ここのパンケーキ食べたことある?」
「いや、初めてだよ。陽馬は何回も来てる感じだよね」
「そう。ここのパンケーキ美味しいからさ、リピートしたくなるんだ」
陽馬はスマホを取り出し、下を向いて操作している。
「へぇ、そうなんだ。陽馬が言うなら間違いなさそうだね」
「おう。間違いないさ」
決め台詞のように言い、右の口角を上げて笑う。
「でも、陽馬って甘いもの苦手じゃなかったっけ?」
「甘いものは苦手だけど、パンケーキだけは、まぁ色々あって…、食べるようにしてるんだよ」
「食べるようにしてるって、ほかの何かを我慢してるってこと?」
「んー、我慢とはまた違うんだよな。食べ終わったら、その理由も含めて話すから」
「わかった」
陽馬は表情一つ変えず、スマホを片手で操作し続けた。真剣な目つきをした陽馬を見つめていると、「勇希、この曲聴いて欲しいんだけど」と突然、自分のスマホとイヤホンを僕に渡してきた。右耳にイヤホンを装着する。「流すよ」と陽馬が言ったため、僕は「うん」と返事すると、再生ボタンが押された。流れ始めたのは、今から四年ほど前に流行ったバンドの一曲だった。普段バンド曲に興味がない僕ですら知っている。
「これ、『One ファイン』って曲だよね? 女子に刺さる歌詞って話題になった」
「そう」
「へー、陽馬ってこんな感じの曲聞くんだね」
「俺にとって、この曲だけは別格なんだ」
「どういうこと?」
店内BGMの曲調が雨に寄り添うようなものへと変わった。
「この曲、お母さんが作詞したんだ」
「そうなの! すごいね」
何でこの曲を聞かされたのか、わからなかった。自慢したいにしても、話の振り方が雑な気がする。曲が終わったため停止ボタンを押し、イヤホンを外す。
「ありがとう」
「聞いてもらえてよかった」
これ以上何も語ろうとする様子は見られない。ますますこの曲をなぜ、今、僕に聞かせようとしたのか、思考は迷宮入りしてしまった。
「陽馬のお母さんって、どんな人なの?」
「えっと…」
陽馬が少し困惑した表情を見せたとき、「お待たせいたしました。イチゴヨーグルトパンケーキです」と店員が僕らの前にパンケーキが乗せられた皿を置き、そしてカトラリーが入ったバケットを二人分並べる。イチゴは照明に照らされて蝋が塗られたように艶々としていた。陽馬の目には、一筋の輝いたものが光り、流れていった。
「こちらに伝票を置いておきますね。では、ごゆっくりとお楽しみください」
「ありがとうございます」
僕らが一礼すると、店員はもっと丁寧な一礼をして戻っていった。
陽馬がパンケーキにナイフを入れる。僕も見様見真似でナイフとフォークを手に取り、パンケーキに差し込む。フワフワとした感触がナイフ越しに伝わってくる。
「ねえ、陽馬。僕、やっぱり待てない。食べ終わるまでなんて、僕、待てないや」
陽馬は小さく首を縦に動かす。視線は僕でも、パンケーキでもないところに向けられている。
「もう、素直に聞く。なんでパンケーキだけ食べるようにしてるの?」
食べ終わるまで待とうとする自分は、そこにはいなかった。気付いたときには口に出し、話終わっていた。陽馬は手に持っていたナイフとフォークを皿の上に置く。カチン、という甲高い音が耳の奥に響いて消える。
「今日、母の誕生日なんだ」
少し暗めの声で答える陽馬。パンケーキの上にトッピングされたイチゴが皿の上に転がった。僕は何か悪い予感がして、慌ててイチゴ
を仲間の元へ戻す。
「そうなんだ。じゃあ、僕といるより家でお祝いしてあげたほうが―」
陽馬はさらにトーンを下げて、しかも、僕が話すのを止めるかのような勢いで話してきた。
「いいんだ。もう、一緒にお祝いすることは無理なんだ。母は…」
乗せ直したばかりのイチゴが、今度はヨーグルトソースの中に吸い込まれていった。
「死んだから」
何かを噛みしめながら言う陽馬。僕は言葉を失った。頭の中は空っぽで、何も整理できない。
「ごめん」
自分の発言のせいで陽馬を傷つけてしまった。そう思ったからなのか、口から出たのは、謝りの言葉だった。これ以外の言葉が見つからず、出てこない状況。謝りの言葉以外、何も言えない。
「勇希が謝ることないよ。いいから、食べよ」
陽馬は明るく振る舞う。が、瞳は嘘をつけないのか、目の奥の輝きは消えていた。それと対峙するようにパンケーキにかけられたヨーグルトソースは照明に照らされ、輝きを放つ。僕はもう一度、「ごめん 」と謝った。陽馬は何も言わず、ただパンケーキを見つめ、再びナイフを入れる。作り笑いの仮面の下を覗き見ることはできそうにない。
傘を閉じ、玄関前の柵に立てかける。傘からは雨粒が落ち、静かにコンクリートを濡らす。風に乗って流れて来る雨は塗装が剥がれた鉄の階段を刺激していく。降る雨はいつか階段を壊すんじゃないかと、気がかりになる。
「ここで待ってて。すぐ呼ぶから」
陽馬はそう言って玄関のドアを閉める。僕は湿気を含み重たくなった空気の中で陽馬を待つ。僕の家の隣に住む円谷さんが、雨の中、ピンク色の傘をさして飼い犬の散歩に出かけていく。犬は傘よりも鮮やかなピンク色の合羽を着せられている。
パンケーキを食べたあと、陽馬の提案で家にお邪魔することになった。雨が降りしきる中、駆け足で帰ってきた僕ら。ズボンの裾や靴下は深水している。でも、気にならなかった。陽馬と一緒に居られるのなら、それでいい。
近づく足音。僕は気を引き締める。ドアが開く。陽馬は服こそ変わっていないものの、黒縁の眼鏡をかけて出てきた。
「お待たせ、入って」
「お邪魔します」
「うん」
狭い玄関に靴を並べる。三足分しか置けないスペースに二足並んだ靴は、とても窮屈そうに見える。
「散らかってて悪いな。なんだったら物どけてもいいから」
「そんなことしないよ」
散らかっているという割には、綺麗に整頓された部屋。六畳ほどしかない室内には、ベッドと勉強机、小さなテレビ、棚が並べられている。玄関入ってすぐにあるキッチンと冷蔵庫は、生活しているという感じがしないほど、整えられていた。
「そこに座って。飲み物お茶しかないけど、いい?」
「ありがとう」
陽馬は冷蔵庫のドアを開ける。冷蔵庫の中に、鍋とペットボトルのお茶が入っているのが見えた。
「はい、これ」
ガラスコップに入っているお茶。中には一個の氷が浮いている。
「ありがとう。いただきます」
僕はお茶を一口飲む。冷えたお茶が喉を潤していく。パチンとグラスの中で氷が弾けた。
部屋の窓に叩き付ける雨。暗くなっていく空。
「陽馬、話の続き…、してくれないか?」
僕はグラスを置く。陽馬は正座をする。
「今まで誰にも言ったことがない内容を勇希に話す。でも、暗い気持ちにならないで欲しい。俺は、勇希が泣く姿を見たくないんだ。いいか?」
僕は頷く。陽馬は喉仏を動かし、ゴクリと音を立て生唾を飲み込む、何か覚悟したかのように。
「二年前の二月八日、母親は僕の前から忽然と姿を消した。連絡もつかない状態でさ。この期間は学校も休んで、父親と俺、あとは母方の親族で母親を探した。警察に捜索願も出したんだ。その間は生きた心地がしなかった。捜索願出して四日後ぐらいに、母親の持ってたスマホが近くの田んぼの中で見つかって。そっから一気に捜索範囲が広がって。十四日の二十二時過ぎ、警察から自宅に連絡がきた。『母親が見つかった』って。時間も遅かったから、その日は会いに行けなかった。翌日、元気な姿で会えると思ってさ、教えられた病院に行ったんだ。警察に案内されたのは、病院の地下だった。扉が開いた先は白い空間に蝋燭が置かれている場所だった。母親の姿見た瞬間、あぁ、死んだんだって。気付いたときには涙が溢れ出してて。こんなの初めてでさ。正直、戸惑った。これから俺はどうやって生きて行けばいいのかなって。不安にもなった。そのとき、僕の隣に父親もいたんだけど、俺を慰めようとしなかった。しかも、なぜか泣いてなかった。今になって、そのことが気になってる」
溢れ出す涙は止まることを知らず、僕を溺れさせていく。
「母親と会ったあと、父親と一緒に、どういう状況で母親が発見されたかっていう話を、警察の人から聞いた。母親は十三日の零時から十四日の一時までの間に、何者かに殴られて、そのうえ腹部まで刺されてた。その当時、警察からは『確実に仕留めるために刺したんだろう』って言われてさ。母親は病院に運ばれたけど、結局、出血多量で死んだ」
陽馬の声は徐々に震え出す。僕は陽馬の目を、姿を、直視することができなかった。
「少しだけ話が逸れるんだけど、俺、パンケーキだけ食べるようにしてるって話しただろ? あれは、大切な母親の存在を忘れないた
めに、母親の誕生日と、母親の月命日には、パンケーキを食べることにしてるからなんだ。僕、幼い頃から甘いもの苦手だったんだけど、母親が家で焼いてくれるパンケーキだけは、砂糖使ってるのになぜか甘くなくて、食べることができたんだ。仕事で忙しかった母親との数少ない思い出のひとつがパンケーキなんだ。母親との思い出や記憶は、年を重ねるにつれて忘れていってしまう。だからこそ、母親を少しでも近くに感じたくて、パンケーキだけは、食べるようにしてる」
なぜあの店のパンケーキを陽馬が選んだのか、何となくわかった気がした。
「パンケーキは、陽馬にとっては大切な存在なんだね」
陽馬は優しく、数回頷いた。
「パンケーキをなぜ食べるかについての話は終わり」
水道から垂れた一滴の水。シンクに到着し、ぼたっという、可愛らしい音を立てる。
「三日後、母親を殺した犯人が逮捕された。これで終わった、終わりだって思ったんだ。でも、この事件の終わりはまだ迎えていなかった」
陽馬の話し方のせいなのか、内容のせいなのか、口の中がどんどん乾いていく。ガラスコップに入っているお茶を流し込む。氷はいつの間にか溶け、お茶と融合していた。陽馬はコップに入ったお茶を喉を鳴らしながら飲む。コップから水滴が滴り落ち、机に着地する。
「僕を殴ってきた奴、母親を殺した犯人の仲間だった。同じ犯罪グループに所属してる奴」
「同じ、グループ、に……」
「警察から話聞いたときに、犯罪グループの主要メンバーの顔写真を見せられたんだけど、殴ってきた奴がその中の一人だった。ソイツは殺人事件に直接関与してないみたいでさ、逮捕されなかったんだよ。俺を見つけたとき、ソイツは『みーつけた』って言いながら近づいてきてさ。なんでこの町にいるのかも、なんで俺を探してたのかも理由はわからないけど、まあ、母親の息子だから、どうせ俺のことが気に食わないとかそんな理由で殴ったんだろうな」
「そ、そん、な、な、んで…陽馬のこ、と」
話そうとしても、途中で言葉が詰まって上手く話せない。絶句した、とはこのことを指すのだろうか。
陽馬はからのガラスコップを手にキッチンに向かう。僕は俯いたまま、止まらない涙を服で拭う。
「悪かったな、こんな暗い話、聞きたくねぇよな。話しといてなんだけど」
コップにお茶を入れながら言う。向けられた背中は悲しそうだった。陽馬は注いだばかりのお茶を飲みながら床に座る。強がっている
のか、涙目になりながらも、零さないようにしているように見えた。
「もう、我慢できない」
僕は後ろからそっと、優しく陽馬を抱きしめる。驚いたのか、陽馬の身体が少し跳ねる。
「陽馬、僕の前では強がらないで。泣きたいときは泣いていいんだよ」
歯を食いしばる陽馬。小刻みに震える身体。僕の手に一粒の雫が落ちる。それはダイヤモンドのように輝きを放つものだった。
陽馬は声を押し殺しながら、しばらく泣いた。僕は陽馬が落ち着くまで、ずっと抱き続けた。
「ごめん、もう大丈夫」
服の袖で零れた涙を拭く。
「ごめんね、突然抱いて。どうしても放っておけなくて」
「謝んなよ。なんか誰かに抱きしめてもらうなんて初めてでさ、驚いたけど嬉しかった」
「はじめて?」
「実は、両親との関係はずっと前から冷めててさ。どう甘えていいのかもわからなかった。でも、勇希に『泣いていい』って言われた
刹那、涙が止まらなくなった。甘えるってこういうことなのかな、って」
陽馬は誰にも甘えることなく今まで生きてきたんだと思うと、胸が締め付けられる。
「これからは僕に甘えて。大丈夫、陽馬のこと受け止めるから」
「ありがとな。勇希」
出会って初めて、本当の陽馬のことを知れた気がした。
陽馬の涙に、僕までも泣きそうになっていたとき、母から一件の電話連絡を受け、一度家に戻ることになった。
「待ってる間に気持ち戻しとく」
「わかった。すぐ戻って来るから」
「おう。待ってるからな」
雨上がりの階段は、少しだけ滑りやすくなっていた。一段ずつ丁寧に降り、家までの道路は全力で走る。
「ただいま」
返事が聞こえなかった代わりに、母と叔母さんが仲良さそうに話している声が聞こえてきた。
「ただいま」
「あら、おかえり」
母は呑気に言う。叔母さんは優雅に紅茶を飲んでいた。
「勇希君、久しぶり」
「はい、久しぶりですね」
叔母さんと会うのは半年ぶりで、どんな口調で話せばいいのか、その都度、距離感がわからなくなる。
「お姉ちゃん、これ。たのまれてたカモミールティーの。三袋でいいんだよね」
「ありがとう。しばらく持ちそうだわ」
「それなに?」
「カモミールっていう花の茶葉。リンとみたいな匂いがしてね、飲んだときにスッキリするのよ」
叔母さんはカモミールの花の画像と共に説明する。
「勇希も一度飲んでみたら?」
「これ、陽馬と一緒に飲んでもいい? 一人じゃ飲めそうにない」
「いいけど、今、持っていく? 小袋になら入れてあげられるよ」
「うん。持ってく」
「わかった。準備するから待ってて」
母はキッチンの戸棚を開け、茶葉を詰めていく。待つ間、叔母さんは僕に対して色々と質問してくる。それに対して僕は、丁寧語で話
したり、少し砕けた口調で話したりと、まとまりがないまま答え続けた。
「はい、できた」
「ありがと。もう一回陽馬ん家に行ってくる」
「はいはい」
茶葉が入った小袋を手に、僕は家を飛び出した。
陽馬の家の前に立ち、声を掛ける。陽馬はドアを開けて「おかえり」と微笑んだ。
「陽馬、これ叔母さんがくれたんだけど、よかったら飲まない?」
「なにそれ?」
「カモミールって花の茶葉。リンゴみたいな匂いで、スッキリとした味がするみたい。実は、僕もまだ飲んだことがないんだよね」
叔母さんから聞いたばかりのことを繰り返す。
「飲んでみたいかも。勇希と初めてを共有したい」
「わかった。じゃあ、ちょっと台所と電気ケトル借りるね」
「どうぞー」
蛇口をひねり、水を入れていると、陽馬は僕の背中に囁いた。
「俺の昔について、もう少し話してもいいか?」
ケトルをセットしてから、「うん、いいよ」と陽馬の目を見て答える。
陽馬と向かい合わせに座る。電源が入れられたケトルは、沸点に向かって走り出した。
「俺、母親がいなくなってから、周りの大人に可哀想な子って言われたり、同級生の親からは、あの子に近づいたらいけない、とか、陽馬君の親なら殺されてもしかたない、とか色んなことを言われ続けた。その当時は我慢して学校に行ってたんだけど、一か月経ったぐらいのときに、ついに精神が崩壊した。そんな俺を見た父親が『私の生まれ故郷で暮らしなさい 』って言われて、連れて来られたのがこの町だった。そのときは、祖父と伯父さんの家で暮らすって話だったんだけど、こんな子とは一緒に暮らせないって言われてさ。暮らせない理由もわからないまま、結局、隣の県にある親戚の家に招かれることになって。これで安定した生活ができるって思ってた」
ゴール間近の湯は、音を立てて僕に知らせる。
「でも、そうはならなかった。親戚の家に引っ越した翌日、父親は誰にも行き先を告げないまま、姿を消した。でも、行方不明届を警
察に出せなかった。祖父が頑なな態度を取ったからな。俺は、そんな祖父も、それに反対しない伯父さんも信じられなくなって。今の今までずっと連絡を取ってない。親戚の人は『きっと帰って来るわよ』と何度も俺を励ましてくれた。あの人は、本当に優しい人だった。表には出さない優しさに憧れるぐらい」
カモミールの茶葉をスプーンで掬い、熱湯を注ぐ。
「中学一年生のときだけ、親戚の家から通える中学に行ってたんだけど、伯父さんの友達の息子が変な噂を流したせいで、ある日から俺の居場所は無くなってた。引きこもる毎日は、楽しいなんて言える状況じゃなかった。そんな俺に、親戚の人は『あなたは一人暮らしをした方がいい』って言ってきた。それで、学生時代の友人を頼って、あの大家さんが経営してるアパートの一室を紹介してもらった。一目見た瞬間にこの部屋を気に入って。この町なら俺はやっていけるって、なんかわかんないけど、自信を手にした気分だった。それがなんだか嬉しくて」
カモミールティーの甘い匂いが部屋いっぱいに立ち込める。
「母親が殺されなければ、冷めきった関係も取り戻せてたのかなって考える日もあった。でも、こんなことが無かったら、俺は今みたいな、勇希と一緒に過ごせる幸せを感じることはできなかったと思う。だから、これは前向きに出来事を捉えないといけないのかなって」
陽馬の目から溢れ出した涙。頬を伝って落ちていく。
「逆境に耐えてきた陽馬は強いよ」
「……え、どういうこと?」
「逆境に耐えたから今の陽馬がいるんだよ? 耐えてなかったら、今みたいに強い陽馬は存在しない」
「そんなこと」
「そんなことあるよ。ほら、カモミールティーも淹れたし、一緒に飲もう、ね?」
「うん。飲む」
ガラスコップにカモミールティーを注ぐ。陽馬は入れたてを口に含み、「ほんとだ、スッキリする」と涙目のまま頬を緩ます。
「ストレスによる疲れとかもほぐしてくれるんだって。どう?」
「うん、新しい感じがいい。たまに飲むのもアリかも」
「だね」
「そのときは、また俺と一緒に飲んでくれよな」
「もちろん」
カモミールの花は、逆境の中で生まれた陽馬そのものだと思った。