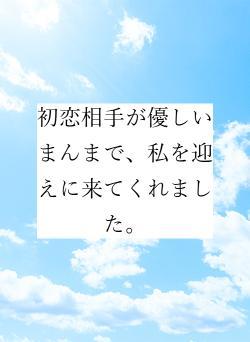合格発表の結果を受けて、僕らは学校に行き、そのまま体育館に集められた。時間になるまでの間は、志望校に合格できたかどうかの話で盛り上がっていた。届く会話を聞く限りでは、皆が合格していたようで、それを嬉しそうに聞く教師の姿もある。式の練習が開始されるまであと五分。僕と陽馬は仲間が来るのを待っていた。
「勇ちゃん、転校生君!」
遠くから呼ばれた。声がした方を振り返ると、千夏が嬉しそうな顔で入口から走ってきているのが瞳に映る。
「来たな」
「うん。間に合ってよかった」
キラキラとした表情を浮かべ、僕と陽馬の前に立った。
「私! 合格してたよ!」
千夏は両手を上げ、僕に抱き付いてきた。驚きと、申し訳なさが入り混じり、千夏の背中に腕を回すことができない。隣の陽馬は、僕から顔を逸らしている。
「千夏、おめでとう。凄いな」
「おめでとう」
「ありがとう」
周りは千夏が僕に抱き着いたことをテンション高く盛り上げる。
「あっ! ごめん、つい」
「だ、大丈夫。それほど嬉しかったんだね」
千夏はすぐに僕の背中から手を離した。陽馬は何も語ろうとしない。
普段から仲の良い女子グループが「千夏! おめでとー!」などと言いながら、周りを囲む。千夏は「ありがと!」と言って、女子たちの輪の中へ染まっていった。
千夏が遠ざかっても、陽馬はただ俯いたまま、僕と目を合わせようとしない。
「陽馬、ごめん。僕も突然のことで、どうしていいかわからなくて」
「いいよ。別に」
「ほんと、ごめん」
「許すからさ、今、頭撫でて」
甘えだした陽馬。人目を避けることは難しいけれど、合格したことを喜んでいる風に見せれば、変な意味で捉えられることはないだろう。そんな思いで陽馬の頭に優しく手を置き、撫でる。陽馬は「俺の方こそ、ごめん」と耳元で囁いた。「いいよ」と僕も陽馬の耳元に囁いた。
「はい、今から練習するから、自分の席に座ってくださーい」
教師が大声で生徒に呼びかける。それに応じた生徒は会話を止め、急いでパイプ椅子に腰かける。座ったことを確認した教師が、式の流れを初めから通しで確認する旨の話をした。そして、十時過ぎから始まった全体練習。明日に控える卒業式。まだ実感が湧かない。
「全体練習お疲れ様でした。今から教師陣の感想を伝えます」
隣のクラスの担任がマイクを通して総評を話し始めた。そのどれもが、改善すべき点として挙げられている。
「改善すべきところも含めて、もう一度最初からやります。次は今指摘された点にも重きを置きましょう」
生徒からは簡単の声がしていた。そのことに対して教師は喝を入れる。
全体練習を終え、重い足取りのまま教室に戻る。午後からも式の通し練習が待っている。それを前にして卒業生たちは項垂れていた。
「給食だって、食べれるの今日が最後の日なのにな。みんなともっと明るい気分で、食べたかった」
千夏がクラスメイトの心の声を代表して嘆く。周りからは同情の声が掛かる。
「午後からは一度通しの練習をしたあと、特に注意を受けた、証書をもらう流れ中心に最終確認します。そのあと、歌の練習もします。いいですか」
給食の準備をする教室に響いた三条先生の声。生徒の過半数が真面目に返事する。
「合格発表のあと、学校に帰ってすぐ練習って。なんか隣のクラスに落ちた人もいるって話聞いたし、その人のこと考えればさ、どん
な気分で臨めばいいんだよって思わねぇか?」
陽馬が僕にしか聞こえないような声で呟いた。
「そうだよね。僕たちのクラスメイトにはいなかったけど、気まずいよね」
「だよな」
「小学生のときなんて、そんな別れを惜しむ感じじゃなかったし、合否で一喜一憂もしなかったから、ただ何の感情もないまま練習に
参加してたけど、中学になるとさ、こんな複雑な感情を抱いたままで練習することになるんだね」
「俺は小学校の卒業式に出なかったんだよ。人前に立つのも嫌いだったからな。でもこんな思いするなら、小学生のときぐらい笑って卒業すればよかった」
笑って卒業すればよかった…。この言葉が胸の中で引っかかる。
給食配膳の列に並ぶ。今日のメニューは人気上位のカレーだ。
「あ、ルーの量少なめで」
当番の千夏は「仕方ないな」と言ってご飯が盛られた器に注ぐ。
「相変わらず陽馬ってカレーだけは苦手だよね」
「パンケーキ以外の甘いものと同等。ほかの辛いものはイケるけどさ、カレーだけは食えないんだよな、なぜかわかんないけど」
副采の酢の物を受け取る。
「僕、陽馬のそういうとこ好きだよ」
「いやっ、どんなとこ好きになってんだよ」
椅子に座る。いつの間にか机には牛乳パックが置かれていた。
「だって、可愛いじゃん。その見た目でカレーが苦手です、って」
陽馬は三年生になったばかりの頃よりも、顔の完成度が増していて、声変わりをしてもなお、少し高い声とのギャップにやられる生徒が多かった。
「いただきます」
生徒は大好物のカレーを、幸せそうに頬張る。陽馬はルーだけを一目散に食べ進めていた。まるで何かに追われているかのように。
「あー、辛い」
陽馬はルーだけを食べ終わり、残すはご飯と酢の物だけになっていた。
「よく食べたね。陽馬、偉いよ」
「こんなことで褒めんなよ、恥ずかしいだろ」
「いいじゃん。なんならもっと声を大にして言ってもいいんだよ?」
「それは困るから、褒めるなら俺にしか聞き取れない声にしてくれよ」
「はいはい」
僕は残りのルーとご飯を混ぜながら食べる。食べ終えた生徒たちは、給食との別れを悲しんでいた。
午後の練習も終わり、最後の練習に対して、教師陣が熱く語った。練習漬けだった今日は式前日にも拘わらず、ハードな内容だった。教室に戻った僕らは、明日の注意事項を聞かされた。
「最後に。明日は皆さんがこの学校に来る最後の日となります。それぞれ色んな想いを抱いていると思いますが、卒業式では気を緩めず、保護者の方や来賓の方々に立派に成長した皆さんの姿を見ていただけるよう、式に臨みましょう」
「はい」
生徒は疲れた表情のまま教室を出て行った。空になったロッカー。紙が剝がされた掲示板。この景色をみても、明日が卒業式だとは思えない。千夏は仲の良い友人と手を振って別れたあと、僕の元へとやってきた。手に何かを握っている。
「勇ちゃん、お願いがあるんだけど」
「なんだよ」
「これ、こないだ言い忘れてたこと」
そう言って僕の手を無理やり広げ、紙を握らせた。
「誰にも見せないでね。これは勇ちゃんと私にしか、わからないことなんだから」
陽馬は一人でグラウンドを眺め、黄昏ている。
「わかった」
千夏は上達しないままのウインクを返し、教室を出ていった。手の中から紙の感触が伝わる。
「今見ろよ。俺、何も邪魔しないから」
僕は陽馬に背を向けて、そっと指をほぐす。罫線入りノートの切れ端に書かれていた文字。グラウンドで練習中のサッカー部。聞こえ
てきた雄叫び。陽馬は一人眺め、「すげぇ」と言って拍手を送っていた。
「ただいま」
背負っていたバッグを玄関に置く。リビングから出てきた母。
「おかえり。はい、これ。買ってきて欲しい食材のメモと、お金。ちゃんとこの金額に収まるように買い物してきてね」
「わかった。じゃ、行ってきまーす」
制服を着たまま、僕と陽馬は徒歩で七分の距離にあるスーパーに向かった。夕方のスーパーは主婦たちで混雑していて、陽馬と離れないように、くっつきながらメモに書かれた食材を探し、渡されたお金で収まるよう計算しながら買い物をした。
「じゃ、俺、帰って着替えてくるから」
「わかった。待ってるね」
買った食材が入った袋を手に、僕は家に帰った。
「ただいま」
「おかえり、買い物できた?」
「うん、合ってると思うんだけど」
買い物袋の中から一つずつを取り出し、買ってきた食材をテーブルの上に広げる。
「よし、全部合ってる。じゃあ、陽馬くんが来たら作ろうか」
「じゃあ、手洗ったら着替えてくる」
「汚れてもいい服選んで着てよ」
「わかってるよ」
洗面所で手を洗う。階段を駆け上がり、料理用と決めている服を引っ張り出し、袖を通す。開いていたカーテンを閉める。それによって舞い上がった埃を見て、三週間近く掃除をしていないことを思い出した。明後日掃除すればいいや。そう思いながら部屋のドアを閉めた。
「はい、ちゃんと料理用の服に着替えてきた」
「はいはい、じゃあ、料理する前に手を洗って―」
特定のリズムでチャイムが鳴る。
「お邪魔します」
「陽馬、さっき振り」
僕は片手を胸の位置に挙げる。すると陽馬も手を挙げた。
「おう、さっき振りだな」
「おかえり、陽馬くん」
「ただいまです。勇希ママ」
「揃ったところで、二人とも手洗って、唐揚げ作ってくよ」
「はーい」
僕と陽馬は横で副采を調理する母に教わりながら、唐揚げを作っていく。中々切れない鶏肉に苦戦したり、まぶす粉の量が多すぎたりと、結局作り終えるまでに二時間近くもかかっていた。途中で帰ってきた父も、僕らが料理する姿を時折眺めながら、テレビを付けて録画していたドラマを観ていた。
「じゃあ、食べましょ」
「そうだな。いただきます」
父の掛け声のあと、僕たちも続いて「いただきます」と言う。
「おぉ、唐揚げ美味そうにできてるな」
「ぜひ、勇希パパとママから先に食べてみてください」
「じゃあ、美味しそうなこれを」
「お言葉に甘えて、私も」
ひと口、唐揚げを齧る父。それを見て母も唐揚げを食べる。カリッという音が僕らにも聞こえる。
「おっ、美味いな。上手にできてる」
「うん、美味しい」
「やったぜ、勇希」
「やったな、陽馬」
僕らはハイタッチをする。その様子を微笑ましく見る両親。
「サイズバラバラだけど、これもご愛嬌ってことで」
「お許しください!」
「最初はそんなものよ。一個ずつ個性があっていいじゃないの。それに、これからも料理を続けていくことが大事なのよ」
「うん。わかった」
「頑張ります」
唐揚げの衣はカリカリで、中から溢れる肉汁に満足感を得る。これからも陽馬と一緒に、色んな料理を作りたい。そして、いつかは陽馬の家庭の味も教えてもらおう。
「おはよう。今日は寒いね」
「おはよ。俺なんか、寒すぎてコート羽織ってきた。でも勇希が着てるアウターも、少しは温かそうじゃん」
「これ? 全然温かくないんだよ。寒いから、取りあえずクローゼットから引っ張り出して着てるだけ」
「そっか。にしても、昨日まで温かったのに、なんで今日はこんなに寒いんだろな」
「気温にも今日までは頑張って欲しかったな」
「だな。でも、寒いから勇希とくっつけるのは嬉しいけどな」
「うん。僕もだよ。いっぱいくっつき合おうね」
陽馬といつもの時間に待ち合わせて学校に行く、三月中旬なのに、季節外れの寒さが痛みとして頬に突き刺さる。つい先日までは蕾の状態だったチューリップも、昨日の暖かさからか、早くも花を咲かせていた。
今日は三月十五日、金曜日。僕らは、人生の節目を迎えようとしていた。
「俺らもいよいよ卒業だな」
「だね」
黒板に書かれた、卒業おめでとうございます! の文字は、僕らに現実を教える。
「陽馬は泣く予定ある?」
「あるわけないだろ。ってか、俺が泣いたらカッコ悪いって」
「女子たちに何言われるかわからないもんね」
陽馬は右手で耳を触りながら「違うから」と言う。
普段より五分早い時間にチャイムが鳴る。生徒らは浮かれた気分のまま席に座り、三条先生が来るのを待つ。「おはようございます」と、いつもより明るい声で教室に入ってきたのは、赤に近い紫色の袴に身を包んだ三条先生だった。普段の雰囲気とは異なる装いに、生徒たちのボルテージが上がる。
「いよいよ卒業式ですね。このあと、二年生がコサージュを付けに来てくれるので、それまで―」
「失礼します。先輩方にコサージュを付けに来ました」
「はーい。どうぞ」
二年生は教室にぞろぞろ入り、目当ての先輩のところへと向かう。その中にあの三人がいた。理貴は陽馬の元へ、和香菜は顔をぐしゃぐしゃにしながら千夏に抱き付いていた。直音は僕を見つけるなり、「勇希先輩!」と駆けてきた。
「先輩、自分から付けさせてもらってもいいですか」
「もちろん」
直音は不器用ながらに、色の濃さが違う赤二色のバラのコサージュを付ける。
「できました」
「ありがとな」
「はい、失礼します」
泣いている和香菜を揶揄う理貴と直音。去り行く三人の姿を見た陽馬が、「俺ら、アイツらの役に立てたのかな」と、少し感慨深そうに話す。
「うん。役に立ってるよ、きっと」
体育館を出て教室へと繋がる廊下には、退場時に舞い踊った花吹雪が落ちていて、さらに受け取った花束を包むビニールが擦れる音と、泣く女子生徒の声が融合し、妙に共鳴している。
「勇ちゃん!」
僕の少し前を行く千夏は、その場に立ち止まって笑顔と涙で崩れた顔を見せている。
「千夏は昔から涙脆いから、やっぱり泣いたな」
「勇ちゃんだって、泣いてるじゃん」
「いや、まぁ、そりゃ」
「俺、ずっと隣で見てたけど、最後の歌で涙流してた。だから、勇希は泣いてる」
陽馬は花束片手に頷く。
「そういう陽馬だって涙流してるじゃんか」
「へぇ、転校生君も泣くんだ。意外だなぁ」
「俺だって泣くときもある」
出席番号が最後の男子生徒は、僕らを横目に追い抜いた。それに気付いた千夏が、「置いて行かれる! ほら、早く行くよ!」と走り出した。僕らも千夏を追って廊下を走った。
最後のホームルームが終わるとスマホを取り出し、一斉に写真を撮り始めた生徒。千夏はイツメンに声を掛けたと思ったら、教室を足早に出て行った。
「陽馬、僕ちょっと千夏に呼ばれてて。行ってきてもいい?」
「おう。俺はここで待ってっから」
少し前に千夏から渡された紙切れに書かれていた場所を目指す。誰もいない階段を上る。普段は立入が禁止されている場所へと向かう感情と、なぜ千夏に呼ばれたのかわからないドキドキとが入り混じり、胸が高鳴る。
「あっ、来た」
「なんだよ、こんなところに呼び出して」
「……」
「クッキーと一緒に手渡してきた、アレのことだろ?」
「うん」
「なんだよ、改まって」
屋上に繋がる扉から差し込む太陽の光が、千夏の茶色い髪を輝かせる。
「私ね、勇ちゃんのこと、ずっと大好きだった。勇ちゃんと付き合うことが夢でね。でも、転校生君と過ごしてる日々を見て、私は勇ちゃんと転校生君との恋を応援する側に回ろうって決めた。勇ちゃんのこと、大好きで、大切な幼馴染っていう気持ちで接するから。今日までありがとう。今後もよろしくね」
千夏の目から落ちたダイヤモンドのような涙。拭ってあげたいけど、手を出す勇気が出なかった。
「千夏の気持ちに応えてあげられなくてごめん。千夏は僕にとって大切な幼馴染ってことに違いないから。気持ち伝えてくれてありがとう。これからもよろしく、千夏」
千夏は僕の腕を抓り、歯を見せて悪戯に笑う。元気に階段を駆け下りる背中に、声を掛けた。太陽は、僕にも光を届ける。
陽馬はコートを羽織り、卒業生の撮影スポットとなっている中庭を眺めていた。外から聞こえる生徒や教師、保護者の声。その中からは、五分前に僕の前にいた千夏の声も聞こえてくる。
「お待たせ」
「待たせすぎ」
陽馬は突然甘い声を出す。
「ごめん、ちょっと感慨深いものがあって、つい」
美術部によって描かれた黒板アート。可愛く描かれた卒業生の似顔絵に目を細める。
「みんな写真好きだよね」
「俺は嫌いだけどな」
「わかってる。っていうか、それは周知の事実だよ」
陽馬は少し恥ずかしそうに笑いながらも、「中庭行くか」と指を差す。
「え、どうしたの急に。僕はいいけど、あの雰囲気だから写真撮りたいって言われるかもよ?」
「だよな。でも、今日だけは許すかって思ってんだ」
取りあえずで選んだアウターを羽織る。
「卒業だから?」
「あぁ。もうアイツラと会うことは無いだろうから。最後ぐらいはな」
「カッコいいじゃん」
このあと、急に会話が途切れた。まるで充電の切れたパソコンのように。中庭で誰かが泣き叫んでいる。その様子を静かに見るだけじゃ、パソコンの再起動はできない。充電のために陽馬の名前を呼ぼう。そして、あの場所に…。
「陽馬、これからどっか行かない?」
陽馬は目を丸くするも、「楽しそうだな。行こうぜ」とゴーサインを出した。
「陽馬はどっか行きたい場所ある?」
「俺一人じゃ決められねぇ。せーので行きたいところ言わないか?」
「いいね。揃っても揃わなくても面白いかも」
「じゃあ、いくぞ。っせーの!」
舞い落ちた花びらが散らばる廊下を歩く。陽馬の胸元に付けられたコサージュが、逃げたそうに斜めになっている。
「俺らが最後みたいだな」
「そうみたい。靴箱も空だし」
卒業生を中心に賑わっていたフォトスポットは、生徒らが帰ったせいか、数人の教師らによって撤去作業が進められていた。
「もう撤去されてんのか。早いな」
「準備には時間かかっても、片付くのは意外と早かったりするんだよね。何でもそうだけど」
「それって、どういうことだ?」
一枚の小さな花びらがひらひらと舞っていく。
「例えば、恋愛とかね。まず、付き合う前にお互いのことを色々と探り合うじゃん。それで、互いに気に入って付き合うとする。なのに、何か違うとなると別れることもある。準備には時間かかっても、後片付けは時間がかからないって話」
微かに聞こえる陽馬の吐息は、甘く僕を誘う。
「俺らも、そういうことなのか?」
「陽馬と僕の関係は、簡単には崩れない。崩れさせないから」
僕らは手を握る。
「繋いだ手をもう離したくない。陽馬、好きだよ」
「俺も、勇希のことが好きだ」
羽織っているチェックのコートからは、イチゴのような甘酸っぱい匂いがしていた。
正門の前に立ち、聞き馴染みのある声で僕らの名前を呼ぶ二人。陽馬はその声に手を挙げる。二人は後ろに何かを隠し持っているように見える。
「先輩! 待ってましたよ」
「ごめんな、遅くなって」
「大丈夫です!」
理貴は指でオッケーマークを作る。
「事前に連絡くれてありがとね」
直音に声をかける。すると直音は「いえいえ」と首を左右に振った。
「陽馬先輩! 勇希先輩!」と、理貴と直音が声を揃える。小さな声で「せーの」と言う。
「合格と御卒業おめでとうございます!」
理貴は陽馬に、オレンジを基調とした花束を、直音は僕に、白色を基調とした花束を差し出してきた。
「ありがとう、直音」
「理貴、ありがとな」
受け取った花束の中には、小さなメッセージカードも入っている。二人の思いに胸が熱くなる。
「よかったです、無事に渡せて」
「陽馬先輩も、勇希先輩も、来るの遅かったから、もしかして、なんて思ったぐらいです」
「待たせて悪かった。でも、待っててくれてありがとな」
陽馬がそう声をかけると、理貴と直音は嬉しそうに微笑んだ。
「あっ、陽馬先輩。ちょっといいですか」
陽馬と理貴は二人で話を始めた。そんな理貴の背中を見ながら直音が、「自分たちも先輩のあとを追うことにしました。明自学高校を受験しようって話してて」と、頬を赤らめながら囁いた。
「そっか。頑張りなよ」
「ありがとうございます。待っててくださいね、追いつきますから」
「その気合じゃ、追い抜かれそうだよ」
直音は静かに笑みを浮かべる、肩にそっと手を置く。直音は少しだけ肩を震わせた。
白を基調とした花の中で、ひと際僕の目を引く青い花。無意識にその花だけを見ていたのか、直音が話しかけてきた。
「やっぱり、その花綺麗ですよね」
「なんて言うか知ってんの?」
「カランコエって言う花です」
「へぇ、綺麗だね」
陽馬の方に目を向ける。お日様のように微笑む姿がそこにはあった。
「ちなみに、陽馬先輩の花束にもカランコエ入ってますよ。白色なんですけどね」
「そうなんだ。わざわざありがとね」
「いえ、先輩にはお世話になったので、これからもお願いします」
「こちらこそ、よろしく」
花束に結ばれたオレンジのリボン。風に靡く姿は麗しかった。
「勇ちゃん、転校生君!」
遠くから呼ばれた。声がした方を振り返ると、千夏が嬉しそうな顔で入口から走ってきているのが瞳に映る。
「来たな」
「うん。間に合ってよかった」
キラキラとした表情を浮かべ、僕と陽馬の前に立った。
「私! 合格してたよ!」
千夏は両手を上げ、僕に抱き付いてきた。驚きと、申し訳なさが入り混じり、千夏の背中に腕を回すことができない。隣の陽馬は、僕から顔を逸らしている。
「千夏、おめでとう。凄いな」
「おめでとう」
「ありがとう」
周りは千夏が僕に抱き着いたことをテンション高く盛り上げる。
「あっ! ごめん、つい」
「だ、大丈夫。それほど嬉しかったんだね」
千夏はすぐに僕の背中から手を離した。陽馬は何も語ろうとしない。
普段から仲の良い女子グループが「千夏! おめでとー!」などと言いながら、周りを囲む。千夏は「ありがと!」と言って、女子たちの輪の中へ染まっていった。
千夏が遠ざかっても、陽馬はただ俯いたまま、僕と目を合わせようとしない。
「陽馬、ごめん。僕も突然のことで、どうしていいかわからなくて」
「いいよ。別に」
「ほんと、ごめん」
「許すからさ、今、頭撫でて」
甘えだした陽馬。人目を避けることは難しいけれど、合格したことを喜んでいる風に見せれば、変な意味で捉えられることはないだろう。そんな思いで陽馬の頭に優しく手を置き、撫でる。陽馬は「俺の方こそ、ごめん」と耳元で囁いた。「いいよ」と僕も陽馬の耳元に囁いた。
「はい、今から練習するから、自分の席に座ってくださーい」
教師が大声で生徒に呼びかける。それに応じた生徒は会話を止め、急いでパイプ椅子に腰かける。座ったことを確認した教師が、式の流れを初めから通しで確認する旨の話をした。そして、十時過ぎから始まった全体練習。明日に控える卒業式。まだ実感が湧かない。
「全体練習お疲れ様でした。今から教師陣の感想を伝えます」
隣のクラスの担任がマイクを通して総評を話し始めた。そのどれもが、改善すべき点として挙げられている。
「改善すべきところも含めて、もう一度最初からやります。次は今指摘された点にも重きを置きましょう」
生徒からは簡単の声がしていた。そのことに対して教師は喝を入れる。
全体練習を終え、重い足取りのまま教室に戻る。午後からも式の通し練習が待っている。それを前にして卒業生たちは項垂れていた。
「給食だって、食べれるの今日が最後の日なのにな。みんなともっと明るい気分で、食べたかった」
千夏がクラスメイトの心の声を代表して嘆く。周りからは同情の声が掛かる。
「午後からは一度通しの練習をしたあと、特に注意を受けた、証書をもらう流れ中心に最終確認します。そのあと、歌の練習もします。いいですか」
給食の準備をする教室に響いた三条先生の声。生徒の過半数が真面目に返事する。
「合格発表のあと、学校に帰ってすぐ練習って。なんか隣のクラスに落ちた人もいるって話聞いたし、その人のこと考えればさ、どん
な気分で臨めばいいんだよって思わねぇか?」
陽馬が僕にしか聞こえないような声で呟いた。
「そうだよね。僕たちのクラスメイトにはいなかったけど、気まずいよね」
「だよな」
「小学生のときなんて、そんな別れを惜しむ感じじゃなかったし、合否で一喜一憂もしなかったから、ただ何の感情もないまま練習に
参加してたけど、中学になるとさ、こんな複雑な感情を抱いたままで練習することになるんだね」
「俺は小学校の卒業式に出なかったんだよ。人前に立つのも嫌いだったからな。でもこんな思いするなら、小学生のときぐらい笑って卒業すればよかった」
笑って卒業すればよかった…。この言葉が胸の中で引っかかる。
給食配膳の列に並ぶ。今日のメニューは人気上位のカレーだ。
「あ、ルーの量少なめで」
当番の千夏は「仕方ないな」と言ってご飯が盛られた器に注ぐ。
「相変わらず陽馬ってカレーだけは苦手だよね」
「パンケーキ以外の甘いものと同等。ほかの辛いものはイケるけどさ、カレーだけは食えないんだよな、なぜかわかんないけど」
副采の酢の物を受け取る。
「僕、陽馬のそういうとこ好きだよ」
「いやっ、どんなとこ好きになってんだよ」
椅子に座る。いつの間にか机には牛乳パックが置かれていた。
「だって、可愛いじゃん。その見た目でカレーが苦手です、って」
陽馬は三年生になったばかりの頃よりも、顔の完成度が増していて、声変わりをしてもなお、少し高い声とのギャップにやられる生徒が多かった。
「いただきます」
生徒は大好物のカレーを、幸せそうに頬張る。陽馬はルーだけを一目散に食べ進めていた。まるで何かに追われているかのように。
「あー、辛い」
陽馬はルーだけを食べ終わり、残すはご飯と酢の物だけになっていた。
「よく食べたね。陽馬、偉いよ」
「こんなことで褒めんなよ、恥ずかしいだろ」
「いいじゃん。なんならもっと声を大にして言ってもいいんだよ?」
「それは困るから、褒めるなら俺にしか聞き取れない声にしてくれよ」
「はいはい」
僕は残りのルーとご飯を混ぜながら食べる。食べ終えた生徒たちは、給食との別れを悲しんでいた。
午後の練習も終わり、最後の練習に対して、教師陣が熱く語った。練習漬けだった今日は式前日にも拘わらず、ハードな内容だった。教室に戻った僕らは、明日の注意事項を聞かされた。
「最後に。明日は皆さんがこの学校に来る最後の日となります。それぞれ色んな想いを抱いていると思いますが、卒業式では気を緩めず、保護者の方や来賓の方々に立派に成長した皆さんの姿を見ていただけるよう、式に臨みましょう」
「はい」
生徒は疲れた表情のまま教室を出て行った。空になったロッカー。紙が剝がされた掲示板。この景色をみても、明日が卒業式だとは思えない。千夏は仲の良い友人と手を振って別れたあと、僕の元へとやってきた。手に何かを握っている。
「勇ちゃん、お願いがあるんだけど」
「なんだよ」
「これ、こないだ言い忘れてたこと」
そう言って僕の手を無理やり広げ、紙を握らせた。
「誰にも見せないでね。これは勇ちゃんと私にしか、わからないことなんだから」
陽馬は一人でグラウンドを眺め、黄昏ている。
「わかった」
千夏は上達しないままのウインクを返し、教室を出ていった。手の中から紙の感触が伝わる。
「今見ろよ。俺、何も邪魔しないから」
僕は陽馬に背を向けて、そっと指をほぐす。罫線入りノートの切れ端に書かれていた文字。グラウンドで練習中のサッカー部。聞こえ
てきた雄叫び。陽馬は一人眺め、「すげぇ」と言って拍手を送っていた。
「ただいま」
背負っていたバッグを玄関に置く。リビングから出てきた母。
「おかえり。はい、これ。買ってきて欲しい食材のメモと、お金。ちゃんとこの金額に収まるように買い物してきてね」
「わかった。じゃ、行ってきまーす」
制服を着たまま、僕と陽馬は徒歩で七分の距離にあるスーパーに向かった。夕方のスーパーは主婦たちで混雑していて、陽馬と離れないように、くっつきながらメモに書かれた食材を探し、渡されたお金で収まるよう計算しながら買い物をした。
「じゃ、俺、帰って着替えてくるから」
「わかった。待ってるね」
買った食材が入った袋を手に、僕は家に帰った。
「ただいま」
「おかえり、買い物できた?」
「うん、合ってると思うんだけど」
買い物袋の中から一つずつを取り出し、買ってきた食材をテーブルの上に広げる。
「よし、全部合ってる。じゃあ、陽馬くんが来たら作ろうか」
「じゃあ、手洗ったら着替えてくる」
「汚れてもいい服選んで着てよ」
「わかってるよ」
洗面所で手を洗う。階段を駆け上がり、料理用と決めている服を引っ張り出し、袖を通す。開いていたカーテンを閉める。それによって舞い上がった埃を見て、三週間近く掃除をしていないことを思い出した。明後日掃除すればいいや。そう思いながら部屋のドアを閉めた。
「はい、ちゃんと料理用の服に着替えてきた」
「はいはい、じゃあ、料理する前に手を洗って―」
特定のリズムでチャイムが鳴る。
「お邪魔します」
「陽馬、さっき振り」
僕は片手を胸の位置に挙げる。すると陽馬も手を挙げた。
「おう、さっき振りだな」
「おかえり、陽馬くん」
「ただいまです。勇希ママ」
「揃ったところで、二人とも手洗って、唐揚げ作ってくよ」
「はーい」
僕と陽馬は横で副采を調理する母に教わりながら、唐揚げを作っていく。中々切れない鶏肉に苦戦したり、まぶす粉の量が多すぎたりと、結局作り終えるまでに二時間近くもかかっていた。途中で帰ってきた父も、僕らが料理する姿を時折眺めながら、テレビを付けて録画していたドラマを観ていた。
「じゃあ、食べましょ」
「そうだな。いただきます」
父の掛け声のあと、僕たちも続いて「いただきます」と言う。
「おぉ、唐揚げ美味そうにできてるな」
「ぜひ、勇希パパとママから先に食べてみてください」
「じゃあ、美味しそうなこれを」
「お言葉に甘えて、私も」
ひと口、唐揚げを齧る父。それを見て母も唐揚げを食べる。カリッという音が僕らにも聞こえる。
「おっ、美味いな。上手にできてる」
「うん、美味しい」
「やったぜ、勇希」
「やったな、陽馬」
僕らはハイタッチをする。その様子を微笑ましく見る両親。
「サイズバラバラだけど、これもご愛嬌ってことで」
「お許しください!」
「最初はそんなものよ。一個ずつ個性があっていいじゃないの。それに、これからも料理を続けていくことが大事なのよ」
「うん。わかった」
「頑張ります」
唐揚げの衣はカリカリで、中から溢れる肉汁に満足感を得る。これからも陽馬と一緒に、色んな料理を作りたい。そして、いつかは陽馬の家庭の味も教えてもらおう。
「おはよう。今日は寒いね」
「おはよ。俺なんか、寒すぎてコート羽織ってきた。でも勇希が着てるアウターも、少しは温かそうじゃん」
「これ? 全然温かくないんだよ。寒いから、取りあえずクローゼットから引っ張り出して着てるだけ」
「そっか。にしても、昨日まで温かったのに、なんで今日はこんなに寒いんだろな」
「気温にも今日までは頑張って欲しかったな」
「だな。でも、寒いから勇希とくっつけるのは嬉しいけどな」
「うん。僕もだよ。いっぱいくっつき合おうね」
陽馬といつもの時間に待ち合わせて学校に行く、三月中旬なのに、季節外れの寒さが痛みとして頬に突き刺さる。つい先日までは蕾の状態だったチューリップも、昨日の暖かさからか、早くも花を咲かせていた。
今日は三月十五日、金曜日。僕らは、人生の節目を迎えようとしていた。
「俺らもいよいよ卒業だな」
「だね」
黒板に書かれた、卒業おめでとうございます! の文字は、僕らに現実を教える。
「陽馬は泣く予定ある?」
「あるわけないだろ。ってか、俺が泣いたらカッコ悪いって」
「女子たちに何言われるかわからないもんね」
陽馬は右手で耳を触りながら「違うから」と言う。
普段より五分早い時間にチャイムが鳴る。生徒らは浮かれた気分のまま席に座り、三条先生が来るのを待つ。「おはようございます」と、いつもより明るい声で教室に入ってきたのは、赤に近い紫色の袴に身を包んだ三条先生だった。普段の雰囲気とは異なる装いに、生徒たちのボルテージが上がる。
「いよいよ卒業式ですね。このあと、二年生がコサージュを付けに来てくれるので、それまで―」
「失礼します。先輩方にコサージュを付けに来ました」
「はーい。どうぞ」
二年生は教室にぞろぞろ入り、目当ての先輩のところへと向かう。その中にあの三人がいた。理貴は陽馬の元へ、和香菜は顔をぐしゃぐしゃにしながら千夏に抱き付いていた。直音は僕を見つけるなり、「勇希先輩!」と駆けてきた。
「先輩、自分から付けさせてもらってもいいですか」
「もちろん」
直音は不器用ながらに、色の濃さが違う赤二色のバラのコサージュを付ける。
「できました」
「ありがとな」
「はい、失礼します」
泣いている和香菜を揶揄う理貴と直音。去り行く三人の姿を見た陽馬が、「俺ら、アイツらの役に立てたのかな」と、少し感慨深そうに話す。
「うん。役に立ってるよ、きっと」
体育館を出て教室へと繋がる廊下には、退場時に舞い踊った花吹雪が落ちていて、さらに受け取った花束を包むビニールが擦れる音と、泣く女子生徒の声が融合し、妙に共鳴している。
「勇ちゃん!」
僕の少し前を行く千夏は、その場に立ち止まって笑顔と涙で崩れた顔を見せている。
「千夏は昔から涙脆いから、やっぱり泣いたな」
「勇ちゃんだって、泣いてるじゃん」
「いや、まぁ、そりゃ」
「俺、ずっと隣で見てたけど、最後の歌で涙流してた。だから、勇希は泣いてる」
陽馬は花束片手に頷く。
「そういう陽馬だって涙流してるじゃんか」
「へぇ、転校生君も泣くんだ。意外だなぁ」
「俺だって泣くときもある」
出席番号が最後の男子生徒は、僕らを横目に追い抜いた。それに気付いた千夏が、「置いて行かれる! ほら、早く行くよ!」と走り出した。僕らも千夏を追って廊下を走った。
最後のホームルームが終わるとスマホを取り出し、一斉に写真を撮り始めた生徒。千夏はイツメンに声を掛けたと思ったら、教室を足早に出て行った。
「陽馬、僕ちょっと千夏に呼ばれてて。行ってきてもいい?」
「おう。俺はここで待ってっから」
少し前に千夏から渡された紙切れに書かれていた場所を目指す。誰もいない階段を上る。普段は立入が禁止されている場所へと向かう感情と、なぜ千夏に呼ばれたのかわからないドキドキとが入り混じり、胸が高鳴る。
「あっ、来た」
「なんだよ、こんなところに呼び出して」
「……」
「クッキーと一緒に手渡してきた、アレのことだろ?」
「うん」
「なんだよ、改まって」
屋上に繋がる扉から差し込む太陽の光が、千夏の茶色い髪を輝かせる。
「私ね、勇ちゃんのこと、ずっと大好きだった。勇ちゃんと付き合うことが夢でね。でも、転校生君と過ごしてる日々を見て、私は勇ちゃんと転校生君との恋を応援する側に回ろうって決めた。勇ちゃんのこと、大好きで、大切な幼馴染っていう気持ちで接するから。今日までありがとう。今後もよろしくね」
千夏の目から落ちたダイヤモンドのような涙。拭ってあげたいけど、手を出す勇気が出なかった。
「千夏の気持ちに応えてあげられなくてごめん。千夏は僕にとって大切な幼馴染ってことに違いないから。気持ち伝えてくれてありがとう。これからもよろしく、千夏」
千夏は僕の腕を抓り、歯を見せて悪戯に笑う。元気に階段を駆け下りる背中に、声を掛けた。太陽は、僕にも光を届ける。
陽馬はコートを羽織り、卒業生の撮影スポットとなっている中庭を眺めていた。外から聞こえる生徒や教師、保護者の声。その中からは、五分前に僕の前にいた千夏の声も聞こえてくる。
「お待たせ」
「待たせすぎ」
陽馬は突然甘い声を出す。
「ごめん、ちょっと感慨深いものがあって、つい」
美術部によって描かれた黒板アート。可愛く描かれた卒業生の似顔絵に目を細める。
「みんな写真好きだよね」
「俺は嫌いだけどな」
「わかってる。っていうか、それは周知の事実だよ」
陽馬は少し恥ずかしそうに笑いながらも、「中庭行くか」と指を差す。
「え、どうしたの急に。僕はいいけど、あの雰囲気だから写真撮りたいって言われるかもよ?」
「だよな。でも、今日だけは許すかって思ってんだ」
取りあえずで選んだアウターを羽織る。
「卒業だから?」
「あぁ。もうアイツラと会うことは無いだろうから。最後ぐらいはな」
「カッコいいじゃん」
このあと、急に会話が途切れた。まるで充電の切れたパソコンのように。中庭で誰かが泣き叫んでいる。その様子を静かに見るだけじゃ、パソコンの再起動はできない。充電のために陽馬の名前を呼ぼう。そして、あの場所に…。
「陽馬、これからどっか行かない?」
陽馬は目を丸くするも、「楽しそうだな。行こうぜ」とゴーサインを出した。
「陽馬はどっか行きたい場所ある?」
「俺一人じゃ決められねぇ。せーので行きたいところ言わないか?」
「いいね。揃っても揃わなくても面白いかも」
「じゃあ、いくぞ。っせーの!」
舞い落ちた花びらが散らばる廊下を歩く。陽馬の胸元に付けられたコサージュが、逃げたそうに斜めになっている。
「俺らが最後みたいだな」
「そうみたい。靴箱も空だし」
卒業生を中心に賑わっていたフォトスポットは、生徒らが帰ったせいか、数人の教師らによって撤去作業が進められていた。
「もう撤去されてんのか。早いな」
「準備には時間かかっても、片付くのは意外と早かったりするんだよね。何でもそうだけど」
「それって、どういうことだ?」
一枚の小さな花びらがひらひらと舞っていく。
「例えば、恋愛とかね。まず、付き合う前にお互いのことを色々と探り合うじゃん。それで、互いに気に入って付き合うとする。なのに、何か違うとなると別れることもある。準備には時間かかっても、後片付けは時間がかからないって話」
微かに聞こえる陽馬の吐息は、甘く僕を誘う。
「俺らも、そういうことなのか?」
「陽馬と僕の関係は、簡単には崩れない。崩れさせないから」
僕らは手を握る。
「繋いだ手をもう離したくない。陽馬、好きだよ」
「俺も、勇希のことが好きだ」
羽織っているチェックのコートからは、イチゴのような甘酸っぱい匂いがしていた。
正門の前に立ち、聞き馴染みのある声で僕らの名前を呼ぶ二人。陽馬はその声に手を挙げる。二人は後ろに何かを隠し持っているように見える。
「先輩! 待ってましたよ」
「ごめんな、遅くなって」
「大丈夫です!」
理貴は指でオッケーマークを作る。
「事前に連絡くれてありがとね」
直音に声をかける。すると直音は「いえいえ」と首を左右に振った。
「陽馬先輩! 勇希先輩!」と、理貴と直音が声を揃える。小さな声で「せーの」と言う。
「合格と御卒業おめでとうございます!」
理貴は陽馬に、オレンジを基調とした花束を、直音は僕に、白色を基調とした花束を差し出してきた。
「ありがとう、直音」
「理貴、ありがとな」
受け取った花束の中には、小さなメッセージカードも入っている。二人の思いに胸が熱くなる。
「よかったです、無事に渡せて」
「陽馬先輩も、勇希先輩も、来るの遅かったから、もしかして、なんて思ったぐらいです」
「待たせて悪かった。でも、待っててくれてありがとな」
陽馬がそう声をかけると、理貴と直音は嬉しそうに微笑んだ。
「あっ、陽馬先輩。ちょっといいですか」
陽馬と理貴は二人で話を始めた。そんな理貴の背中を見ながら直音が、「自分たちも先輩のあとを追うことにしました。明自学高校を受験しようって話してて」と、頬を赤らめながら囁いた。
「そっか。頑張りなよ」
「ありがとうございます。待っててくださいね、追いつきますから」
「その気合じゃ、追い抜かれそうだよ」
直音は静かに笑みを浮かべる、肩にそっと手を置く。直音は少しだけ肩を震わせた。
白を基調とした花の中で、ひと際僕の目を引く青い花。無意識にその花だけを見ていたのか、直音が話しかけてきた。
「やっぱり、その花綺麗ですよね」
「なんて言うか知ってんの?」
「カランコエって言う花です」
「へぇ、綺麗だね」
陽馬の方に目を向ける。お日様のように微笑む姿がそこにはあった。
「ちなみに、陽馬先輩の花束にもカランコエ入ってますよ。白色なんですけどね」
「そうなんだ。わざわざありがとね」
「いえ、先輩にはお世話になったので、これからもお願いします」
「こちらこそ、よろしく」
花束に結ばれたオレンジのリボン。風に靡く姿は麗しかった。