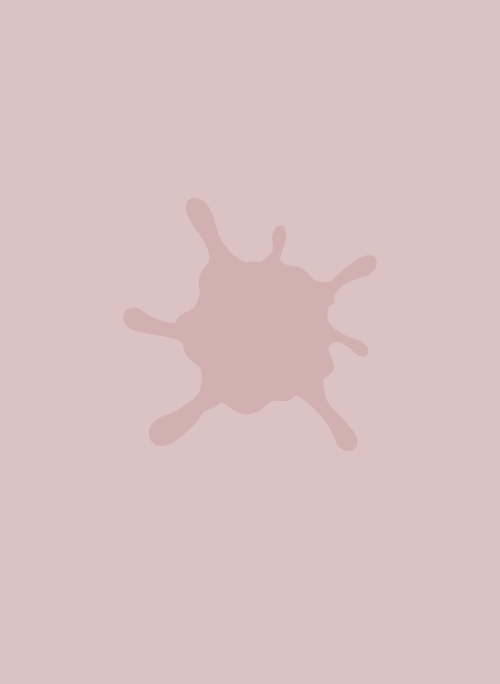勿論、ここにいるのは本物の彼女じゃない。
僕の中にある彼女の魂が、幻影を作り出して現れた、所詮は偽物の身体。
触れることは出来る。温もりを感じることも。
だけど、それは僕の記憶にある「情報」が、彼女の姿を模して映しているだけ。
虚しい、空っぽの身体。
それでもやはり、そこに宿るのが彼女の魂そのものであることに、変わりはない。
だから僕は、ここに来ると安らぎを覚えるのだ。
まるで、生きていた頃の彼女に再会出来たようで。
…今までの辛いことや寂しいこと全部、なかったことに出来る気がして。
そんなはずはないのにね。
そんな風に考えてしまうんだよ。
僕は弱いから。
他の人みたいに、僕は強くないから。
心の中に残る記憶に、頼ることしか出来ないほどに。
「…また寂しくなっちゃった?」
そんな僕の心を案じてか、リリスがそう聞いた。
「…僕はあなたを失ってから、ずっと寂しいですよ…」
「ふふ。そっかー。そうだね、私も寂しい」
全く、リリスと来たら。
笑い事じゃないっての。
「…ずっと傍にいるのに…」
ずっと、誰よりも僕の近くにいるのに。
それなのに、一度も触れられなかった。
その孤独は、簡単に埋められるものではない。
だから、こうして精神世界で一緒にいるときは。
もうこのまま、永遠に僕達の時間が止まってしまえば良いのにと思う。
でも出来ないんだよね。
僕達には、まだ許されない。
「…ごめんね」
リリスは、僕の頬を包み込むように撫でた。
その温もりは本物なのか、僕が勝手に作り出したものなのか。
きっと後者なのだろうけど、今は前者だと信じたい。
「君に罪を背負わせたのは、全部私のせい」
「…あなたの、せいじゃ」
「ううん、私が悪いの。私は、君を失いたくなかった…」
「…」
その気持ちは、よく分かる。
リリスは僕を失えば、また一人ぼっちになってしまう。
だから怖かったんだよね。
孤独に耐えられなくて、それで僕と融合することで、僕の中で生き続けて…。
結局そのせいで、またお互い、一人ぼっちになっちゃったんだから、意味がないのかもしれないけど。
僕達は、似た者同士だ。
お互い、ただ、永遠に一緒だと誓い合える相手が欲しかった。
ただ、それだけの話なのだ。
その為に、どれだけの命が犠牲になったとしても。
そんなこと、どうでも良いって。
かつてシルナ・エインリーがそうであったように。
世界のこととか、他人のこととかどうでも良いから。
ただ、愛する人の傍に、ずっといたかっただけなのだ。
僕の中にある彼女の魂が、幻影を作り出して現れた、所詮は偽物の身体。
触れることは出来る。温もりを感じることも。
だけど、それは僕の記憶にある「情報」が、彼女の姿を模して映しているだけ。
虚しい、空っぽの身体。
それでもやはり、そこに宿るのが彼女の魂そのものであることに、変わりはない。
だから僕は、ここに来ると安らぎを覚えるのだ。
まるで、生きていた頃の彼女に再会出来たようで。
…今までの辛いことや寂しいこと全部、なかったことに出来る気がして。
そんなはずはないのにね。
そんな風に考えてしまうんだよ。
僕は弱いから。
他の人みたいに、僕は強くないから。
心の中に残る記憶に、頼ることしか出来ないほどに。
「…また寂しくなっちゃった?」
そんな僕の心を案じてか、リリスがそう聞いた。
「…僕はあなたを失ってから、ずっと寂しいですよ…」
「ふふ。そっかー。そうだね、私も寂しい」
全く、リリスと来たら。
笑い事じゃないっての。
「…ずっと傍にいるのに…」
ずっと、誰よりも僕の近くにいるのに。
それなのに、一度も触れられなかった。
その孤独は、簡単に埋められるものではない。
だから、こうして精神世界で一緒にいるときは。
もうこのまま、永遠に僕達の時間が止まってしまえば良いのにと思う。
でも出来ないんだよね。
僕達には、まだ許されない。
「…ごめんね」
リリスは、僕の頬を包み込むように撫でた。
その温もりは本物なのか、僕が勝手に作り出したものなのか。
きっと後者なのだろうけど、今は前者だと信じたい。
「君に罪を背負わせたのは、全部私のせい」
「…あなたの、せいじゃ」
「ううん、私が悪いの。私は、君を失いたくなかった…」
「…」
その気持ちは、よく分かる。
リリスは僕を失えば、また一人ぼっちになってしまう。
だから怖かったんだよね。
孤独に耐えられなくて、それで僕と融合することで、僕の中で生き続けて…。
結局そのせいで、またお互い、一人ぼっちになっちゃったんだから、意味がないのかもしれないけど。
僕達は、似た者同士だ。
お互い、ただ、永遠に一緒だと誓い合える相手が欲しかった。
ただ、それだけの話なのだ。
その為に、どれだけの命が犠牲になったとしても。
そんなこと、どうでも良いって。
かつてシルナ・エインリーがそうであったように。
世界のこととか、他人のこととかどうでも良いから。
ただ、愛する人の傍に、ずっといたかっただけなのだ。