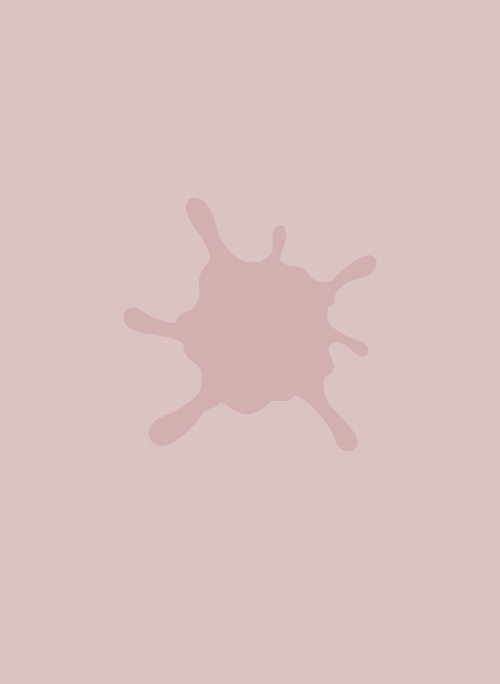気づいた途端に、寂しさと郷愁に襲われた。
いきなりの環境の変化。ましてやカリナから突然王都じゃ、他の国に来たのかってくらいカルチャーショックもあるだろう。
そもそも彼女は、まだ子供なのだ。
親元から離れるには、まだ早い。
イーニシュフェルトに来ている多くの生徒は、幼い頃からイーニシュフェルト魔導学院に憧れ、寮生活にも憧れを抱いて入学してくる。
だから大半の生徒は、親元から離れる覚悟をして、入学の日を迎える。
それでも全くホームシックにならない訳じゃないが、シャーロットのように、部屋から出られないほどではない。
けれどシャーロットの場合、お試し受験で受かってしまって、まだ心の準備が出来ないまま、入学してしまった。
そりゃホームシックにもなる。
おまけに。
「皆頭が良くて…。授業もレベルが高くて…」
「…」
「私は分からないのに、皆すぐに新しいことを覚えて…。私には、とてもついていけなくて…」
イーニシュフェルト魔導学院新入生あるある、その二だ。
入学したは良いものの、授業のレベルの高さが予想以上で、自信をなくしてしまう。
余程自分に自信のある生徒ならともかく。
「元々自分は、イーニシュフェルト魔導学院に入学出来るほどの能力はない」と思い込んで入学したシャーロットは、イーニシュフェルト魔導学院の「洗礼」を、まともに受けてしまった。
自分にはレベルが高過ぎる。ついていけない。
生活に慣れるだけでも大変なのに、更に学校での授業。
彼女はもう、いっぱいいっぱいなのだ。
成程、それで登校拒否…。
教師にとっては、特に珍しいことではない。
2~3年に一人は、そういう生徒がいる。
だが生徒にとっては、この世の終わりのように辛いことなのだろう。
故郷というものを持たない俺にとっては、いまいちピンと来ない話だ。
「イーニシュフェルト魔導学院なんて、やっぱり私には無理だったんです。私みたいな田舎者が来るところじゃなかったんです…」
すっかり自信をなくしたシャーロットは、目に一杯涙を溜めていた。
「今でさえ授業についていけないのに、これから学年が上がったら、もっとついていけなくなる…。そんな辛いの、無理です。私には耐えられない。私はイーニシュフェルト魔導学院には相応しくない人間だったんです…」
「…そっか」
シャーロットの苦しい胸のうちを、シルナは余さず受け止め。
そして、彼女に言うべき言葉を探した。
「…君が本当にイーニシュフェルト魔導学院に相応しくない生徒なら、そもそも入学出来てないと思うよ」
まずは、ド正論から。
いきなりの環境の変化。ましてやカリナから突然王都じゃ、他の国に来たのかってくらいカルチャーショックもあるだろう。
そもそも彼女は、まだ子供なのだ。
親元から離れるには、まだ早い。
イーニシュフェルトに来ている多くの生徒は、幼い頃からイーニシュフェルト魔導学院に憧れ、寮生活にも憧れを抱いて入学してくる。
だから大半の生徒は、親元から離れる覚悟をして、入学の日を迎える。
それでも全くホームシックにならない訳じゃないが、シャーロットのように、部屋から出られないほどではない。
けれどシャーロットの場合、お試し受験で受かってしまって、まだ心の準備が出来ないまま、入学してしまった。
そりゃホームシックにもなる。
おまけに。
「皆頭が良くて…。授業もレベルが高くて…」
「…」
「私は分からないのに、皆すぐに新しいことを覚えて…。私には、とてもついていけなくて…」
イーニシュフェルト魔導学院新入生あるある、その二だ。
入学したは良いものの、授業のレベルの高さが予想以上で、自信をなくしてしまう。
余程自分に自信のある生徒ならともかく。
「元々自分は、イーニシュフェルト魔導学院に入学出来るほどの能力はない」と思い込んで入学したシャーロットは、イーニシュフェルト魔導学院の「洗礼」を、まともに受けてしまった。
自分にはレベルが高過ぎる。ついていけない。
生活に慣れるだけでも大変なのに、更に学校での授業。
彼女はもう、いっぱいいっぱいなのだ。
成程、それで登校拒否…。
教師にとっては、特に珍しいことではない。
2~3年に一人は、そういう生徒がいる。
だが生徒にとっては、この世の終わりのように辛いことなのだろう。
故郷というものを持たない俺にとっては、いまいちピンと来ない話だ。
「イーニシュフェルト魔導学院なんて、やっぱり私には無理だったんです。私みたいな田舎者が来るところじゃなかったんです…」
すっかり自信をなくしたシャーロットは、目に一杯涙を溜めていた。
「今でさえ授業についていけないのに、これから学年が上がったら、もっとついていけなくなる…。そんな辛いの、無理です。私には耐えられない。私はイーニシュフェルト魔導学院には相応しくない人間だったんです…」
「…そっか」
シャーロットの苦しい胸のうちを、シルナは余さず受け止め。
そして、彼女に言うべき言葉を探した。
「…君が本当にイーニシュフェルト魔導学院に相応しくない生徒なら、そもそも入学出来てないと思うよ」
まずは、ド正論から。