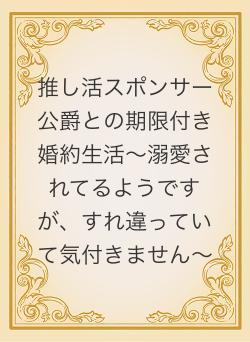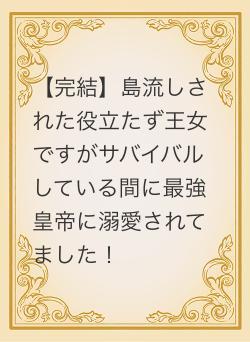すぐに本性を出してきたシャーリーには笑ってしまう。
ディアンヌはシャーリーの本音を聞いて、ため息を吐き出す。
(やっぱり誤解を解きたいなんて嘘だったのね)
やはりお茶会の誘いも、ディアンヌを失脚させるためのものだったのだろう。
「それを言うためだけに、わざわざここに呼び出したのですか?」
「……」
「もうよろしいでしょうか?」
ディアンヌが平然とそう言うとシャーリーの顔が大きく歪む。
しかしリュドヴィックたちの視線があるからか、掴みかかるようなことはなかった。
(わたしに文句を言うだけだったら、もう聞く価値はないわ。時間がもったいないもの)
やはり彼女とは決別して、もう二度と関わらないようにしようと思っていた。
ディアンヌが立ち去ろうとすると、出口を塞ぐようにシャーリーが前に立つ。
「お茶会も断るなんてどういうつもり!? このわたくしが誘ってあげているのにっ」
「……どういう意味でしょうか? 手紙の返信はしましたわ」
「くっ……元男爵令嬢のくせに公爵夫人ぶりやがって! 調子乗ってんじゃないわよ」
鼻息荒く暴言を吐くシャーリー。
その姿を見て、ディアンヌはため息を吐く。
ディアンヌの冷めた様子にシャーリーの怒りは増していくばかりだ。
シャーリーはただディアンヌが『ベルトルテ公爵夫人』としてここに立っていることが、余程気に入らないのだろう。
(〝ディアンヌ〟が、自分より上にいるのが許せないのね)
だからジェルマンの顔がみるみるうちに青ざめていくことも、リュドヴィックとピーターが怒りに顔を歪めていることも、周囲の貴族たちの軽蔑した眼差しも、彼女には見えていないのだろう。
「わたしとはもう友人ではないと言ったではありませんか」
「……っ!」
「これ以上は関わらないでください」