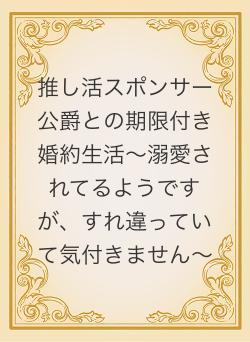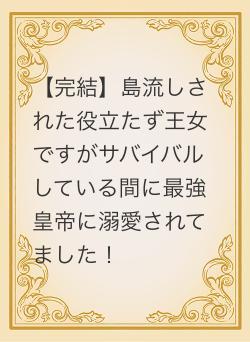馬車に乗っても、ディアンヌの頭には先ほどの言葉がぐるぐると回っていた。
何故かいつものように話すことができないでいると、リュドヴィックから声が掛かる。
「すまない……迷惑だっただろうか?」
「……え?」
ディアンヌはリュドヴィックを勘違いさせてしまったと気づいて、弁解するために口を開く。
「違うんです。その……」
「……?」
「な、なんでもありません!」
ディアンヌはうまく気持ちを伝えることができずに口ごもる。
「まさか何か嫌なことがあったのか?」
「そうではありません! 皆様、とてもよくしてくださって勉強になりました。それにまだまだわたしが力不足だと知ることもできましたから……」
ディアンヌは夫人たちを間近で見たことで、己の力不足をヒシヒシと感じていた。
こんなところで諦めるつもりはないと思いつつも、その差は歴然だ。
けれど時間もないため、悔しい思いばかりが募る。
ディアンヌは無意識に膝の上で手のひらをギュッと握りしめる。
何故かいつものように話すことができないでいると、リュドヴィックから声が掛かる。
「すまない……迷惑だっただろうか?」
「……え?」
ディアンヌはリュドヴィックを勘違いさせてしまったと気づいて、弁解するために口を開く。
「違うんです。その……」
「……?」
「な、なんでもありません!」
ディアンヌはうまく気持ちを伝えることができずに口ごもる。
「まさか何か嫌なことがあったのか?」
「そうではありません! 皆様、とてもよくしてくださって勉強になりました。それにまだまだわたしが力不足だと知ることもできましたから……」
ディアンヌは夫人たちを間近で見たことで、己の力不足をヒシヒシと感じていた。
こんなところで諦めるつもりはないと思いつつも、その差は歴然だ。
けれど時間もないため、悔しい思いばかりが募る。
ディアンヌは無意識に膝の上で手のひらをギュッと握りしめる。