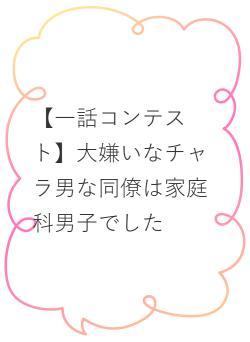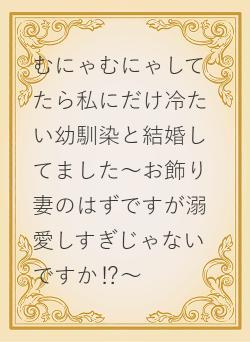「千奈」
「ゼノン? どうぞ、開いてますよ」
丁度眠ろうとしていた頃、私の部屋をゼノンが訪れた。
私とゼノンは結婚したとはいえ寝所は別だ。
まぁ、強制的な形だけの結婚だし、仕方ないといえば仕方ないのだけれど、最近、少しだけモヤモヤしている自分がいる。
このまま、ゼノンとは形だけの夫婦なんだろうか、と。
思った以上に、私はゼノンのことが好きみたいだ。
魔王なのに、人間である私なんかよりずっと優しくて、お人好しで、あったかい人。
惹かれない方がおかしい。
だけどゼノンは……うん、多分ただ義弟に押し付けられた鬼嫁としか思っていないだろう。
きっとこれから先も──。
「失礼する」
そう言って私の部屋に入って来たゼノンの表情は、どこか硬いように思える。
「どうしたんですか? こんな夜遅くに」
「すまない。仮にも女性の部屋に、こんな時間に尋ねるものではないことは承知していたのだが……」
「仮にもじゃなくても私は真の女性です」
今のではっきりわかった気がする。
完全に私、アウトオブ眼中だ……!!
わかってた、わかってたよ。
私みたいなすぐ人間滅ぼそうとか言う狂暴女嫌よね。
国王だって私のこと散々口うるさい鬱陶しい女だとか言ってたし。
「あ、あぁ。それは承知だ」
……本当か?
まあいいわ。流しておいてあげましょう。
「どうぞソファへ。それで、どういうご用件で?」
私はゼノンをソファへ座るよう促すと、用件を尋ねた。
我ながらツンツンとした言い方になってしまったと気にはなったけれど、それを訂正するほど心の余裕はなかった。
「あ、あぁ。……まず、千奈に礼を言いたかった」
「お礼? えっと、一体何の?」
全く身に覚えがない私が首をかしげると、ゼノンは座ったばかりのソファから立ち上がり、向かいの私の隣に腰かけると、ゆっくりと口を開いた。
「人と……魔族が、手を取り合うなど、考えたこともなかった。私は一生、この暗い魔界で、人間として生まれたにもかかわらず人間と関わることも許されないままに生きるのだと……。魔族も閉じ込められた空間の中で、不自由に暮らしてきた者たちばかりだ。それが君のおかげで、魔界の外に出ることができた。もう一度、青い空の下を歩くことができた。人と、魔物が共存することができた。感謝してもしきれない。本当に、ありがとう」
そう言ってゼノンは深く頭を下げた。
そうか……。
ゼノンだってたまたま闇の力を持って生まれて、魔界に追放されて魔王と呼ばれているだけで、元は人間として生まれてきたんだ。
人として生まれながら人に蔑まれ追放され、青い空や日差しを見ることも許されず、とはいえ魔族にもなり切れない存在。
その心はどれだけ孤独だっただろう。
いくら魔族が皆心優しいとはいえ、やるせない思いを抱えて生きてきたことだろう。
気が付けば、私は彼の手を取っていた。
大きく、さらりとした、骨張った手。
私の好きな手だ。
「私の方こそ、ゼノンにお礼を言いたいです」
「私に、礼を?」
首をかしげるゼノンに、今度は私が彼をまっすぐ見つめて口を開く。
「はい。突然だまし討ちのように強制結婚させられた私なんかをここに置いてくれた。放っておくこともできたのに、毎食ちゃんと一緒に食べてくれた。怪我をして動けなくなっている私を探して助けてくれた。いつも、気にかけていてくれた。だから私、ここにいると暖かかった。ありがとうございます、ゼノン。あなたが私の旦那様で、よかった」
「千奈……。……やはり、このままにはしておけないな」
ぼそりとつぶやいてからゼノンはソファから腰を上げると、今度は私の足元に片膝をついて跪き、私の右手をそっとその手に取った。
「ちょ、ぜ、ゼノン!? どうしたんで──」
「最初は押し付けられての結婚だった」
静かに、一言一言大切に、ゆっくりと言葉が紡がれる。
「でも、今は違う。私は、君にずっと、私の妻でいてほしい」
「!!」
「君を愛してる。生涯ただ一人。君だけを──。私と、夫婦になってもらえないだろうか?」
愛してる。
その言葉が、全身に甘い痺れをもたらす。
私と同じ気持ちであることに歓喜して、心がうるさいくらいに騒ぎ出した。
心にはまだ、弟たちへの未練がある。
だけど──。
「私も、ゼノンが好きです。その……わ、私でよかったら、家族にしてくださいっ」
私のイエスの言葉に、いつもクールなゼノンの表情が目に見えて嬉しそうに和らいだ。
ほんの少し幼く見えるその微笑がなんだか可愛くて仕方がない。
「よかった……断られたらどうしようかと思っていた」
「陰キャですか!!」
「陰キャな旦那はダメだったか?」
あぁもう。
垂れた耳が見える……!!
何なんだこの可愛い生物は……!!
私はたまらなくなって、ゼノンの思い切って胸に飛び込んだ。
「!? せ、千──」
「駄目じゃないです」
「!!」
「私、陰キャなゼノンも、クールなゼノンも、カッコいいゼノンも、今みたいに可愛いゼノンも、全部好きですから」
「~~~~~~っ」
その後私たちはしばらくそのまま抱擁をし、お互いの思いとぬくもりを感じ合った後、ゼノンは顔を赤くして「部屋に戻る」と自分の部屋へ帰っていった。
曰く、『結婚式もまだなのに同衾することはできない。けじめはつけなければならん』とのことだった。
本当に、真面目で純朴で……素敵な旦那様だ。
結婚式をしてくれるつもりなのだということも驚いたけど、嬉しい。
それでもまだ心のどこかで弟たちを気にしているのは、ゼノンには黙っていよう。
どうにもならないことを言って不安にさせたくはないから──。
その翌日だった。
私が町で一人になったところを、何者かに後ろから殴られ攫われることになったのは──。
「ゼノン? どうぞ、開いてますよ」
丁度眠ろうとしていた頃、私の部屋をゼノンが訪れた。
私とゼノンは結婚したとはいえ寝所は別だ。
まぁ、強制的な形だけの結婚だし、仕方ないといえば仕方ないのだけれど、最近、少しだけモヤモヤしている自分がいる。
このまま、ゼノンとは形だけの夫婦なんだろうか、と。
思った以上に、私はゼノンのことが好きみたいだ。
魔王なのに、人間である私なんかよりずっと優しくて、お人好しで、あったかい人。
惹かれない方がおかしい。
だけどゼノンは……うん、多分ただ義弟に押し付けられた鬼嫁としか思っていないだろう。
きっとこれから先も──。
「失礼する」
そう言って私の部屋に入って来たゼノンの表情は、どこか硬いように思える。
「どうしたんですか? こんな夜遅くに」
「すまない。仮にも女性の部屋に、こんな時間に尋ねるものではないことは承知していたのだが……」
「仮にもじゃなくても私は真の女性です」
今のではっきりわかった気がする。
完全に私、アウトオブ眼中だ……!!
わかってた、わかってたよ。
私みたいなすぐ人間滅ぼそうとか言う狂暴女嫌よね。
国王だって私のこと散々口うるさい鬱陶しい女だとか言ってたし。
「あ、あぁ。それは承知だ」
……本当か?
まあいいわ。流しておいてあげましょう。
「どうぞソファへ。それで、どういうご用件で?」
私はゼノンをソファへ座るよう促すと、用件を尋ねた。
我ながらツンツンとした言い方になってしまったと気にはなったけれど、それを訂正するほど心の余裕はなかった。
「あ、あぁ。……まず、千奈に礼を言いたかった」
「お礼? えっと、一体何の?」
全く身に覚えがない私が首をかしげると、ゼノンは座ったばかりのソファから立ち上がり、向かいの私の隣に腰かけると、ゆっくりと口を開いた。
「人と……魔族が、手を取り合うなど、考えたこともなかった。私は一生、この暗い魔界で、人間として生まれたにもかかわらず人間と関わることも許されないままに生きるのだと……。魔族も閉じ込められた空間の中で、不自由に暮らしてきた者たちばかりだ。それが君のおかげで、魔界の外に出ることができた。もう一度、青い空の下を歩くことができた。人と、魔物が共存することができた。感謝してもしきれない。本当に、ありがとう」
そう言ってゼノンは深く頭を下げた。
そうか……。
ゼノンだってたまたま闇の力を持って生まれて、魔界に追放されて魔王と呼ばれているだけで、元は人間として生まれてきたんだ。
人として生まれながら人に蔑まれ追放され、青い空や日差しを見ることも許されず、とはいえ魔族にもなり切れない存在。
その心はどれだけ孤独だっただろう。
いくら魔族が皆心優しいとはいえ、やるせない思いを抱えて生きてきたことだろう。
気が付けば、私は彼の手を取っていた。
大きく、さらりとした、骨張った手。
私の好きな手だ。
「私の方こそ、ゼノンにお礼を言いたいです」
「私に、礼を?」
首をかしげるゼノンに、今度は私が彼をまっすぐ見つめて口を開く。
「はい。突然だまし討ちのように強制結婚させられた私なんかをここに置いてくれた。放っておくこともできたのに、毎食ちゃんと一緒に食べてくれた。怪我をして動けなくなっている私を探して助けてくれた。いつも、気にかけていてくれた。だから私、ここにいると暖かかった。ありがとうございます、ゼノン。あなたが私の旦那様で、よかった」
「千奈……。……やはり、このままにはしておけないな」
ぼそりとつぶやいてからゼノンはソファから腰を上げると、今度は私の足元に片膝をついて跪き、私の右手をそっとその手に取った。
「ちょ、ぜ、ゼノン!? どうしたんで──」
「最初は押し付けられての結婚だった」
静かに、一言一言大切に、ゆっくりと言葉が紡がれる。
「でも、今は違う。私は、君にずっと、私の妻でいてほしい」
「!!」
「君を愛してる。生涯ただ一人。君だけを──。私と、夫婦になってもらえないだろうか?」
愛してる。
その言葉が、全身に甘い痺れをもたらす。
私と同じ気持ちであることに歓喜して、心がうるさいくらいに騒ぎ出した。
心にはまだ、弟たちへの未練がある。
だけど──。
「私も、ゼノンが好きです。その……わ、私でよかったら、家族にしてくださいっ」
私のイエスの言葉に、いつもクールなゼノンの表情が目に見えて嬉しそうに和らいだ。
ほんの少し幼く見えるその微笑がなんだか可愛くて仕方がない。
「よかった……断られたらどうしようかと思っていた」
「陰キャですか!!」
「陰キャな旦那はダメだったか?」
あぁもう。
垂れた耳が見える……!!
何なんだこの可愛い生物は……!!
私はたまらなくなって、ゼノンの思い切って胸に飛び込んだ。
「!? せ、千──」
「駄目じゃないです」
「!!」
「私、陰キャなゼノンも、クールなゼノンも、カッコいいゼノンも、今みたいに可愛いゼノンも、全部好きですから」
「~~~~~~っ」
その後私たちはしばらくそのまま抱擁をし、お互いの思いとぬくもりを感じ合った後、ゼノンは顔を赤くして「部屋に戻る」と自分の部屋へ帰っていった。
曰く、『結婚式もまだなのに同衾することはできない。けじめはつけなければならん』とのことだった。
本当に、真面目で純朴で……素敵な旦那様だ。
結婚式をしてくれるつもりなのだということも驚いたけど、嬉しい。
それでもまだ心のどこかで弟たちを気にしているのは、ゼノンには黙っていよう。
どうにもならないことを言って不安にさせたくはないから──。
その翌日だった。
私が町で一人になったところを、何者かに後ろから殴られ攫われることになったのは──。