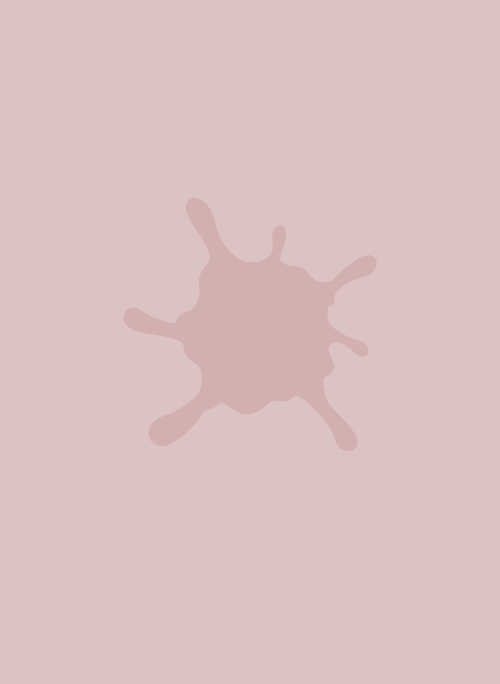萌音の母親は涙を流し、半狂乱になりながら、「もうこの子とは一緒に暮らせない」と言った。
この子とは、つまり萌音のことだ。
父親の前で萌音をモノのように指差して、そう言ったのだ。
事の経緯を聞いた萌音の父親は、母を何とか宥めようとした。
「萌音は何も悪くない」
「悪気があった訳じゃない」
「真理亜のことは、親が背負うべき責任だ」
と、もっともなことを訴えた。
しかし、最後の台詞に萌音母は激昂した。
「私が悪いって言うの!?」
「そうは言ってない。今日のことは、誰にも責任はない。無事だったんだから、別に誰も責めなくても、」
「じゃあ無事じゃなかったらどうするのよ?あの子がちゃんと見てくれてたら、こんなことにはならなったのに!皆あの子の責任よ!」
ヒステリックに叫ぶ萌音母。
俺がこの場にいたら、「いや、あんたの責任だよ」と容赦なく言っていたに違いない。
何で萌音のせいにするんだ。責任転嫁も甚だしい。
元はと言えば、あんたがちゃんと鍵を締めてなかったのが原因だろ?
自分の不注意が招いた事故なのに、どうして萌音のせいにするんだ。
「萌音のせいじゃない。萌音は何も…」
「あなたはいつもそうやって、あの子を庇うのね。そんなだからいつまで経っても、あの子は態度を改めないのよ」
今度は、父親を糾弾し始めた。
「あなたがちゃんと叱ってくれないから。甘やかしてばかりいるから!」
この女は、他人に責任を押し付けなければ気が済まないのか。
自分が悪者になりたくないばかりに。
「だから、あの子があんなに我儘になったのよ。あんな優しさの欠片もないような子に…」
「『あの子』じゃない。萌音だ」
萌音父は、はっきりとそう言った。
萌音母がさっきから、ずっと萌音のことを名前で呼ばず。
ひたすら「あの子」呼ばわりしていることに気づいていた。
「忘れちゃいけない。萌音だってまだ子供なんだ。真理亜のことと萌音のことは、別に考えてやらなきゃ、」
「嫌よ。もうまっぴらよ!あなたがそんなに『あの子』を庇いたいなら、好きにしたら良い。私はもう嫌!」
「…」
はっきりとした、拒絶の言葉だった。
萌音父は、まだ何か言おうとしたが…結局は何も言わなかった。
これほど酷く取り乱しているのだ。今何を言っても、まともな会話など出来そうになかった。
「もう、あの子の顔なんて見たくないわ!」
萌音母はそう叫ぶなり。
未だ泣き止まない真理亜を抱いて、別室に逃げた。
残された、萌音と父親は。
「…心配するな、萌音。今、母さんは動転してるだけなんだ」
萌音父は、優しくそう言ってくれた。
しかし、さすがに疲れた顔をしていた。
自分の妻のことを信じてやりたい。萌音のことも…味方をしてやりたい。
その板挟みになって、父親も疲れてるんだろうと思った。
やっぱり、父親だけは味方だ。
萌音はそう思った。
しかしそんな淡い希望は、うんざりしたような表情で漏らした、次の一言で打ち砕かれた。
「…お前が、もう少し上手く立ち回ってくれたらなぁ…」
「…!」
それは、決して言ってはいけない言葉だった。
この子とは、つまり萌音のことだ。
父親の前で萌音をモノのように指差して、そう言ったのだ。
事の経緯を聞いた萌音の父親は、母を何とか宥めようとした。
「萌音は何も悪くない」
「悪気があった訳じゃない」
「真理亜のことは、親が背負うべき責任だ」
と、もっともなことを訴えた。
しかし、最後の台詞に萌音母は激昂した。
「私が悪いって言うの!?」
「そうは言ってない。今日のことは、誰にも責任はない。無事だったんだから、別に誰も責めなくても、」
「じゃあ無事じゃなかったらどうするのよ?あの子がちゃんと見てくれてたら、こんなことにはならなったのに!皆あの子の責任よ!」
ヒステリックに叫ぶ萌音母。
俺がこの場にいたら、「いや、あんたの責任だよ」と容赦なく言っていたに違いない。
何で萌音のせいにするんだ。責任転嫁も甚だしい。
元はと言えば、あんたがちゃんと鍵を締めてなかったのが原因だろ?
自分の不注意が招いた事故なのに、どうして萌音のせいにするんだ。
「萌音のせいじゃない。萌音は何も…」
「あなたはいつもそうやって、あの子を庇うのね。そんなだからいつまで経っても、あの子は態度を改めないのよ」
今度は、父親を糾弾し始めた。
「あなたがちゃんと叱ってくれないから。甘やかしてばかりいるから!」
この女は、他人に責任を押し付けなければ気が済まないのか。
自分が悪者になりたくないばかりに。
「だから、あの子があんなに我儘になったのよ。あんな優しさの欠片もないような子に…」
「『あの子』じゃない。萌音だ」
萌音父は、はっきりとそう言った。
萌音母がさっきから、ずっと萌音のことを名前で呼ばず。
ひたすら「あの子」呼ばわりしていることに気づいていた。
「忘れちゃいけない。萌音だってまだ子供なんだ。真理亜のことと萌音のことは、別に考えてやらなきゃ、」
「嫌よ。もうまっぴらよ!あなたがそんなに『あの子』を庇いたいなら、好きにしたら良い。私はもう嫌!」
「…」
はっきりとした、拒絶の言葉だった。
萌音父は、まだ何か言おうとしたが…結局は何も言わなかった。
これほど酷く取り乱しているのだ。今何を言っても、まともな会話など出来そうになかった。
「もう、あの子の顔なんて見たくないわ!」
萌音母はそう叫ぶなり。
未だ泣き止まない真理亜を抱いて、別室に逃げた。
残された、萌音と父親は。
「…心配するな、萌音。今、母さんは動転してるだけなんだ」
萌音父は、優しくそう言ってくれた。
しかし、さすがに疲れた顔をしていた。
自分の妻のことを信じてやりたい。萌音のことも…味方をしてやりたい。
その板挟みになって、父親も疲れてるんだろうと思った。
やっぱり、父親だけは味方だ。
萌音はそう思った。
しかしそんな淡い希望は、うんざりしたような表情で漏らした、次の一言で打ち砕かれた。
「…お前が、もう少し上手く立ち回ってくれたらなぁ…」
「…!」
それは、決して言ってはいけない言葉だった。