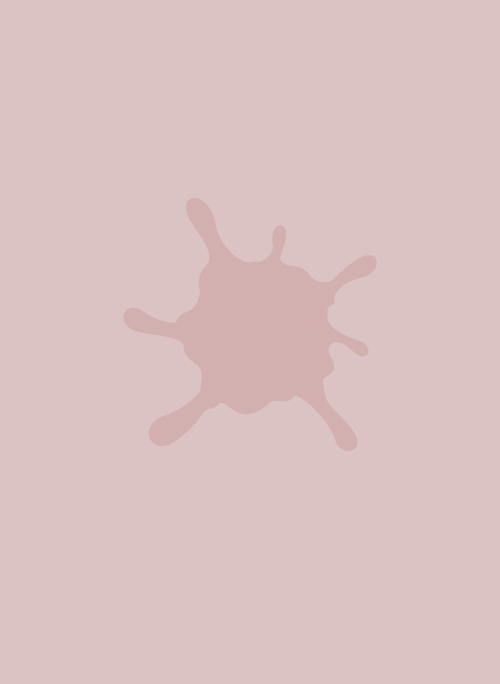こんな簡単なことだったんだぜ、ほたる。
ほたるも、ふぁにみたいにしてれば良かった。
いじめられることは、決して本人が悪いんじゃない。
いじめる馬鹿が悪いのだ。
「いじめられる奴にも責任がある」って、巷ではよく言われてるけど。
そりゃ確かにそうなのかもしれない。その言い分は分かる。
でもな、それは他人事だから言えるのだ。
仮に自分や、自分の大切な人がいじめられていたら、同じことを言えるか?
ふぁにには言えない。
だから、ほたるも…黙っていじめられている理由なんかなかったのだ。
もっと抵抗すれば良かった。ふぁにみたいにさ。
でも、出来なかったんだよな。
ほたるには、そうするだけの勇気も、心の余裕もなかった。
無理からぬことだ。
こればかりは、生まれ持った性格の問題だ。
それに…誰一人味方をしてやらなかった、妹尾家の家族のせいでもある。
ふぁにはこの世に生まれてから何度も、ほたるに声をかけ続けた。
ほたるがふぁにのことをどう思っているのかは知らない。
そもそも、ほたるは多分、身体の中にふぁにがいることさえ知らないのだろう。
だけどふぁににとって、ほたるは友達だった。
長年一緒にいた、これからも一緒にいる、大事なルームメイト。
いつだって同じものを見て、同じ音を聞いて、痛みも苦しみも、全部共有する仲間。家族。
人生のパートナーと言っても過言ではない。
だからふぁには、ほたると仲良くやって行きたかった。
ほたると身体を分け合って、協力して生きていきたかった。
一人で耐えられないことでも、二人なら耐えられるかもしれない。
多分その為に、ふぁにはこの世に生まれたんだと思うから。
だから、ふぁにはほたるに起きて欲しかった。
話をしたかった。ずっと傍に居たんだよ、って言ってやりたかった。
自分のことを一人ぼっちだと感じて、酷い孤独を感じていたに違いないほたるを、励ましてやりたかった。
でも、駄目だった。
ふぁにが生まれて、何年も経って、今日に至っても。
ほたるは、一向に目を覚ます気配がない。
この身体の中で、死んだように眠っているだけだ。
分かるのだ。…ほたるの気配を、全然感じない。
ほたるは未だに、自分が一人ぼっちだと思って、目を覚ますことを拒否している。
果たしていつか、ふぁにが生きている間に、ほたるが目を覚ます日が来るのだろうか。
分からない。正直、自信がない。
だって、目を覚ましたとしても、ふぁにとほたるの前に待っているのは、
いつだって、現実以上に悲劇的で、現実的な悪夢なのだから。
ほたるも、ふぁにみたいにしてれば良かった。
いじめられることは、決して本人が悪いんじゃない。
いじめる馬鹿が悪いのだ。
「いじめられる奴にも責任がある」って、巷ではよく言われてるけど。
そりゃ確かにそうなのかもしれない。その言い分は分かる。
でもな、それは他人事だから言えるのだ。
仮に自分や、自分の大切な人がいじめられていたら、同じことを言えるか?
ふぁにには言えない。
だから、ほたるも…黙っていじめられている理由なんかなかったのだ。
もっと抵抗すれば良かった。ふぁにみたいにさ。
でも、出来なかったんだよな。
ほたるには、そうするだけの勇気も、心の余裕もなかった。
無理からぬことだ。
こればかりは、生まれ持った性格の問題だ。
それに…誰一人味方をしてやらなかった、妹尾家の家族のせいでもある。
ふぁにはこの世に生まれてから何度も、ほたるに声をかけ続けた。
ほたるがふぁにのことをどう思っているのかは知らない。
そもそも、ほたるは多分、身体の中にふぁにがいることさえ知らないのだろう。
だけどふぁににとって、ほたるは友達だった。
長年一緒にいた、これからも一緒にいる、大事なルームメイト。
いつだって同じものを見て、同じ音を聞いて、痛みも苦しみも、全部共有する仲間。家族。
人生のパートナーと言っても過言ではない。
だからふぁには、ほたると仲良くやって行きたかった。
ほたると身体を分け合って、協力して生きていきたかった。
一人で耐えられないことでも、二人なら耐えられるかもしれない。
多分その為に、ふぁにはこの世に生まれたんだと思うから。
だから、ふぁにはほたるに起きて欲しかった。
話をしたかった。ずっと傍に居たんだよ、って言ってやりたかった。
自分のことを一人ぼっちだと感じて、酷い孤独を感じていたに違いないほたるを、励ましてやりたかった。
でも、駄目だった。
ふぁにが生まれて、何年も経って、今日に至っても。
ほたるは、一向に目を覚ます気配がない。
この身体の中で、死んだように眠っているだけだ。
分かるのだ。…ほたるの気配を、全然感じない。
ほたるは未だに、自分が一人ぼっちだと思って、目を覚ますことを拒否している。
果たしていつか、ふぁにが生きている間に、ほたるが目を覚ます日が来るのだろうか。
分からない。正直、自信がない。
だって、目を覚ましたとしても、ふぁにとほたるの前に待っているのは、
いつだって、現実以上に悲劇的で、現実的な悪夢なのだから。