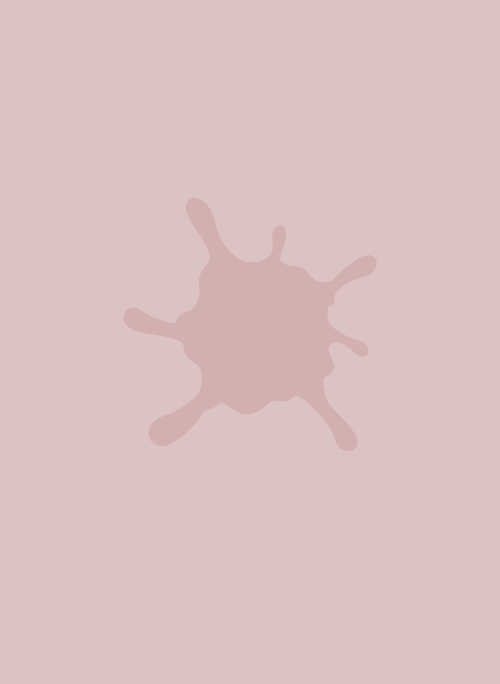…翌日は休み明けの月曜日だったが、俺は学校に行くことは出来なかった。
学校どころか。
自分のベッドから起き上がることさえ、非常に困難な有り様だった。
鎮痛剤を飲んでも、風邪薬を飲んでも、一切効き目のない酷い頭痛に加え。
夢の中で何度も殺されているせいで、現実を酷く「侵食」されていた。
ノイズが走るどころか、常に視界に黒いモヤがかかって、まともに物を見ることも出来ない。
人の声が妙にリアルに、生々しく聞こえたり。
あるいは、聞こえるはずのない声や音さえも聞こえてくるほどだった。
こんな状態で、外に出られるはずがない。
俺は引きこもりのようになって、ひたすらベッドに転がって、そして夜が来ることに怯えていた。
食事もろくに摂っていなかった。
眞沙は心配してくれているようだったが、眞沙にも何と言って良いのか分からなかった。
酷い頭痛のせいで、まともに物を考えられなくなっていた。
「…う…」
…学校に行かなくなって、何日が経っただろう。
昼間の俺は、ベッドに横たわって、ひたすらうつらうつらとして過ごしていた。
時間が過ぎるのが異様に遅く、そして速くも感じられた。
頭を押さえながら、ゆっくりと起き上がる。
…枕元に、開けたばかりの鎮痛剤の箱が置いてあった。
これは昨日、眞沙が薬局で買ってきてくれたものだ。
頭痛を訴える俺に、眞沙は家に置いてあったものよりも強い鎮痛剤を買ってきてくれた。
早速飲んで試してみたが、相変わらず効いていない。
でも、プラセボ効果くらいは期待出来るかと思って、一応ちゃんと飲むことにしている。
前回飲んでから、三時間ほどが経過している。
本当は、服薬には四時間以上の間隔を開けなければならないらしいが。
もう、そこまで我慢していられなかった。
冷静な判断が出来ないと、こうなる。
俺は薬の箱を持って、よろよろと立ち上がった。
「…っ…」
頭痛と、視界に広がるモヤのせいで、立ち上がるだけで酷くふらつく。
壁を手すり代わりに、自室を出て、水を汲む為にキッチンに向かおうとした。
…その時。
「…まったく、あの子は一体いつまで学校をサボってるのかしら」
…!
リビングから、叔母の呟く声が聞こえてきた。
思わず足を止めた。
「そういえば、この間も2週間くらい休んでたよね」
「そうよ。あの時は、しばらくしたらまた登校してたけど…」
「じゃあ、今回もそうなんじゃない?」
叔母に答える声は、眞沙の妹の眞未のものだった。
二人は俺が聞いていないと思って、大きな声で会話を続けた。
学校どころか。
自分のベッドから起き上がることさえ、非常に困難な有り様だった。
鎮痛剤を飲んでも、風邪薬を飲んでも、一切効き目のない酷い頭痛に加え。
夢の中で何度も殺されているせいで、現実を酷く「侵食」されていた。
ノイズが走るどころか、常に視界に黒いモヤがかかって、まともに物を見ることも出来ない。
人の声が妙にリアルに、生々しく聞こえたり。
あるいは、聞こえるはずのない声や音さえも聞こえてくるほどだった。
こんな状態で、外に出られるはずがない。
俺は引きこもりのようになって、ひたすらベッドに転がって、そして夜が来ることに怯えていた。
食事もろくに摂っていなかった。
眞沙は心配してくれているようだったが、眞沙にも何と言って良いのか分からなかった。
酷い頭痛のせいで、まともに物を考えられなくなっていた。
「…う…」
…学校に行かなくなって、何日が経っただろう。
昼間の俺は、ベッドに横たわって、ひたすらうつらうつらとして過ごしていた。
時間が過ぎるのが異様に遅く、そして速くも感じられた。
頭を押さえながら、ゆっくりと起き上がる。
…枕元に、開けたばかりの鎮痛剤の箱が置いてあった。
これは昨日、眞沙が薬局で買ってきてくれたものだ。
頭痛を訴える俺に、眞沙は家に置いてあったものよりも強い鎮痛剤を買ってきてくれた。
早速飲んで試してみたが、相変わらず効いていない。
でも、プラセボ効果くらいは期待出来るかと思って、一応ちゃんと飲むことにしている。
前回飲んでから、三時間ほどが経過している。
本当は、服薬には四時間以上の間隔を開けなければならないらしいが。
もう、そこまで我慢していられなかった。
冷静な判断が出来ないと、こうなる。
俺は薬の箱を持って、よろよろと立ち上がった。
「…っ…」
頭痛と、視界に広がるモヤのせいで、立ち上がるだけで酷くふらつく。
壁を手すり代わりに、自室を出て、水を汲む為にキッチンに向かおうとした。
…その時。
「…まったく、あの子は一体いつまで学校をサボってるのかしら」
…!
リビングから、叔母の呟く声が聞こえてきた。
思わず足を止めた。
「そういえば、この間も2週間くらい休んでたよね」
「そうよ。あの時は、しばらくしたらまた登校してたけど…」
「じゃあ、今回もそうなんじゃない?」
叔母に答える声は、眞沙の妹の眞未のものだった。
二人は俺が聞いていないと思って、大きな声で会話を続けた。