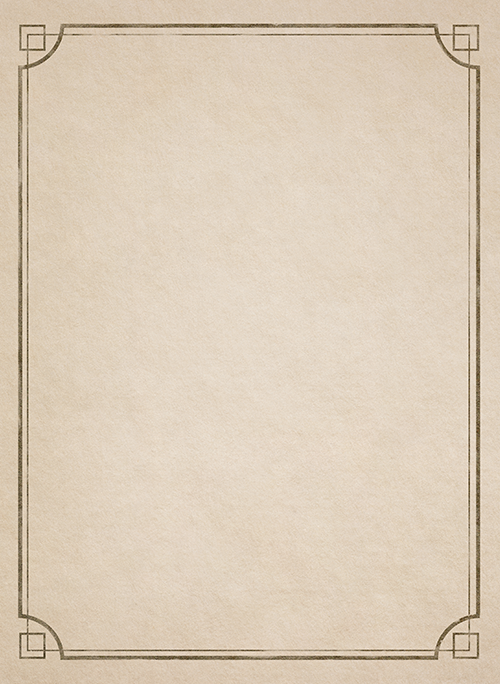おばあちゃんの家は、空港から車で30分ほどの場所にあった。
広い庭に、大きな木造の家。絵本に出てくるような、クラシカルでおしゃれな洋館。
「うわ〜……すっご……」
思わず声が出た。
玄関のドアにかけられた花のリースも、石畳の小道も、まるで映画の中みたい。
「ようこそ、我が家へ。さあ、どうぞ中へ」
おばあちゃんが優しく言ってくれて、みんなで家の中へ入った。
リビングに通されると、暖炉の上には家族写真がずらり。
どれも海外っぽい雰囲気で、写っている人たちはみんなモデルみたいに見える。
咲姉が写真のひとつを指さして、ぽつり。
「これ……もしかして、伊代さん?」
そこに写っていたのは、長い髪をなびかせた女の子。
整った顔立ちにグレーの髪、そしてどこかキリッとした雰囲気——
まるで、葵兄を女の子にしたみたい。
「そうよ。ステラが14歳のときの写真ね。今はもう少し大人っぽくなってるかしら」
「ステラって、ほんとに……本名になってるんだね」
私はそっとつぶやいた。
“伊代お姉ちゃん”は、今はもう“ステラ・スチュアート”。
名前も、国も、暮らしている世界も、私とはまるで違う。
そのとき、玄関のドアが「カチャ」と開く音がした。
「I’m home.(ただいま)」
——その声に、空気が一瞬で張りつめた。
おばあちゃんがぱっと立ち上がって、笑顔でドアのほうへ向かう。
「ステラ、!おかえりなさい!」
私たちも立ち上がって、廊下の先をのぞき込む。
そこに立っていたのは——。
長いストレートの銀髪、きれいに揃った前髪、黒いワンピースに白いカーディガン。
涼しげなグレーの瞳が、まっすぐこっちを見ていた。
「……!」
咲姉も、私も、言葉を失った。
だって、本当に“お姉ちゃん”だったから。
初めて会ったのに、なんだか懐かしいような、不思議な感じがした。
「Are you… Saku and Akane?(あなたたちが、咲と茜?)」
とてもきれいな発音の英語だった。
「えっ……う、うん!私は茜!で、こっちが咲姉!」
私があわてて答えると、ステラお姉ちゃんが、にこっと笑った。
「Nice to meet you. I’m your sister, Stella.(初めまして。私はあなたたちの姉、ステラよ)」
その瞬間——
咲姉がふらっと一歩前に出て、ぽつりと言った。
「……“さき”って、呼んでたって聞いたんだけど」
すると、ステラがちょっとだけ困った顔になって、でもすぐにふんわり笑った。
「うん。“さき”のほうが……響きが可愛いから、好き」
「そ、そう……」
咲姉の耳が、また真っ赤になっていた。
私はというと、ただただ見とれていた。
ステラお姉ちゃんの仕草も、声も、まるでプリンセスみたいだったから。
そのとき、後ろから葵兄が小さくため息をついて——
「……派手に出迎えしてんなぁ……」
とつぶやいた。
「……あら? 葵」
ステラお姉ちゃんが、すっと目を細める。
「あなた、相変わらずムスッとしてるわね。ちゃんと笑えるようになった?」
「は……? 余計なお世話だし」
「ふふふ。じゃあ、あいさつ代わりにハグする?」
「しねーよ!!」
全力で拒否したのに、咲姉と私はびっくりした。
……葵兄が、ちゃんと怒ってる!!
いや、なんかそれすらも新鮮だった。
いつもは「いい人モード」なのに、今の葵兄は、ちょっとだけ年相応に見えた。
お母さんがこっそり私の耳元で言った。
「ほらね、言ったとおりでしょ? ステラの前では“素”になるのよ、あの子」
「……すごっ」
私の夏休みは、ここから“家族再会物語”の本番に入るみたい。
まだちょっと緊張してるけど、
ステラお姉ちゃんのとなりにいると、少しだけ大人になった気がする。
ステラお姉ちゃんとのぎこちない再会がひと段落したとき。
リビングの奥のドアが「ギィ」と開いた。
そこから出てきたのは、背の高い男の人だった。
髪は真っ白で、でも背筋はまっすぐ。スーツ姿がきちんと似合っていて、映画に出てきそうなくらいダンディだった。
「……Grandpa!」
ステラが声をかけると、その人がにこっと笑った。
「Oh… so, you are… Saku and Akane?」
——おじいちゃんだ。
おばあちゃんよりも少し無口そうで、声は低くて落ち着いてる。
でも、私たちを見つめる目はすごく優しかった。
「えっと……は、はい! わたし、Akane!」
「わ、わたしはSakuです!」
思わず、英語っぽく自己紹介してしまった。
おじいちゃんは嬉しそうに「Good! Very good!」と拍手してくれる。
咲姉が小声で私の耳元でささやいた。
「……なんか、学校の英語の授業より緊張するんだけど」
「わかる……!」
おじいちゃんは、葵兄の方に目をやった。
「Aoi. You are tall now. Very cool.」
そう言って、がっしりした手で葵兄の肩をポンと叩く。
葵兄は「は、はぁ……」と苦笑いしてたけど、ちょっと嬉しそうに見えた。
そのあと、おじいちゃんはみんなを見回してから、静かに言った。
「Family… together. Very happy.」
——その言葉に、胸がじんわりした。
日本語はあんまり通じないけど、気持ちはちゃんと伝わってくる。
「Family」って言葉がこんなにあったかく聞こえたのは初めてかもしれない。
おばあちゃんが小さく笑った。
「この人ね、普段はあまり口数が多くないの。でも“家族”のことになると、とても情熱的なのよ」
「……似てるな」
ぽつりと呟いたのは葵兄だった。
「え?」私と咲姉が同時に聞き返す。
「……俺たちの父さんと」
おじいちゃんはその会話がわからないはずなのに、なぜかにっこり笑って、ゆっくりうなずいた。
——ああ、この人も、私たちの“おじいちゃん”なんだ。
それを実感して、胸の奥がじんわり温かくなるのを感じた
✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎
ステラお姉ちゃんの案内で、私たちはそれぞれの部屋に荷物を運び終えた。
広い家にはゲストルームもたくさんあって、姉妹で同じ部屋にしてもらった。
でも、今日はまだ寝られそうにない。
「……なんか、夢みたいだよね」
ベッドの上で、咲姉がポツリとつぶやく。
「ほんとにね……ロンドンにいて、おばあちゃんがいて、そして、あのステラお姉ちゃんが実在してるんだもん」
「実在って……」
思わず笑っちゃった。
でも、気持ちはすっごくわかる。
ステラお姉ちゃんって、完璧すぎてちょっと現実味がないんだよね。
そのとき、コンコン、とノックの音。
「May I come in?(入ってもいい?)」
聞こえてきたのは、もちろんステラお姉ちゃんの声。
「うん!どうぞ!」
ドアが開いて、ステラお姉ちゃんがティーカップを3つ持って入ってきた。
「眠れないでしょ? だから、ハーブティー淹れてきたわ。
子どもでも飲めるカモミールよ」
「わあ……ありがとう!」
私と咲姉はベッドの端にちょこんと座って、ティーカップを受け取る。
「こっちの生活って、やっぱり違う?」
「うん。街の匂いも、人の目も、みんな違う感じがする」
「私も最初はすごく戸惑ったわ。でも、慣れると快適よ。自由で、心地よくて。
……それに、ここには“もうひとつの家族”がいるから」
「もうひとつの家族……?」
ステラお姉ちゃんはちょっと微笑んで、ティーカップを口元に運んだ。
「もちろん、血のつながった“本当の家族”にも会いたかった。
だから今、こうして話せてるのが……ちょっと信じられないのよ、実は」
……え?
あの完璧そうに見えるお姉ちゃんが、
そんなふうに“寂しかった”って思ってたなんて。
「じゃあさ、これから一緒に過ごせるの、嬉しい?」
「……とても、ね」
ステラお姉ちゃんが、そっと私たちの手を包むように握った。
「これからの数日間、たくさん話しましょう? 姉妹として」
「うん!」
「うん、絶対!」
このとき私の胸の中に、ふわっと暖かい何かが芽生えた。
遠く離れていた家族が、また一緒になれた気がして——
まるで、ずっと探していたピースがはまったみたいだった。
広い庭に、大きな木造の家。絵本に出てくるような、クラシカルでおしゃれな洋館。
「うわ〜……すっご……」
思わず声が出た。
玄関のドアにかけられた花のリースも、石畳の小道も、まるで映画の中みたい。
「ようこそ、我が家へ。さあ、どうぞ中へ」
おばあちゃんが優しく言ってくれて、みんなで家の中へ入った。
リビングに通されると、暖炉の上には家族写真がずらり。
どれも海外っぽい雰囲気で、写っている人たちはみんなモデルみたいに見える。
咲姉が写真のひとつを指さして、ぽつり。
「これ……もしかして、伊代さん?」
そこに写っていたのは、長い髪をなびかせた女の子。
整った顔立ちにグレーの髪、そしてどこかキリッとした雰囲気——
まるで、葵兄を女の子にしたみたい。
「そうよ。ステラが14歳のときの写真ね。今はもう少し大人っぽくなってるかしら」
「ステラって、ほんとに……本名になってるんだね」
私はそっとつぶやいた。
“伊代お姉ちゃん”は、今はもう“ステラ・スチュアート”。
名前も、国も、暮らしている世界も、私とはまるで違う。
そのとき、玄関のドアが「カチャ」と開く音がした。
「I’m home.(ただいま)」
——その声に、空気が一瞬で張りつめた。
おばあちゃんがぱっと立ち上がって、笑顔でドアのほうへ向かう。
「ステラ、!おかえりなさい!」
私たちも立ち上がって、廊下の先をのぞき込む。
そこに立っていたのは——。
長いストレートの銀髪、きれいに揃った前髪、黒いワンピースに白いカーディガン。
涼しげなグレーの瞳が、まっすぐこっちを見ていた。
「……!」
咲姉も、私も、言葉を失った。
だって、本当に“お姉ちゃん”だったから。
初めて会ったのに、なんだか懐かしいような、不思議な感じがした。
「Are you… Saku and Akane?(あなたたちが、咲と茜?)」
とてもきれいな発音の英語だった。
「えっ……う、うん!私は茜!で、こっちが咲姉!」
私があわてて答えると、ステラお姉ちゃんが、にこっと笑った。
「Nice to meet you. I’m your sister, Stella.(初めまして。私はあなたたちの姉、ステラよ)」
その瞬間——
咲姉がふらっと一歩前に出て、ぽつりと言った。
「……“さき”って、呼んでたって聞いたんだけど」
すると、ステラがちょっとだけ困った顔になって、でもすぐにふんわり笑った。
「うん。“さき”のほうが……響きが可愛いから、好き」
「そ、そう……」
咲姉の耳が、また真っ赤になっていた。
私はというと、ただただ見とれていた。
ステラお姉ちゃんの仕草も、声も、まるでプリンセスみたいだったから。
そのとき、後ろから葵兄が小さくため息をついて——
「……派手に出迎えしてんなぁ……」
とつぶやいた。
「……あら? 葵」
ステラお姉ちゃんが、すっと目を細める。
「あなた、相変わらずムスッとしてるわね。ちゃんと笑えるようになった?」
「は……? 余計なお世話だし」
「ふふふ。じゃあ、あいさつ代わりにハグする?」
「しねーよ!!」
全力で拒否したのに、咲姉と私はびっくりした。
……葵兄が、ちゃんと怒ってる!!
いや、なんかそれすらも新鮮だった。
いつもは「いい人モード」なのに、今の葵兄は、ちょっとだけ年相応に見えた。
お母さんがこっそり私の耳元で言った。
「ほらね、言ったとおりでしょ? ステラの前では“素”になるのよ、あの子」
「……すごっ」
私の夏休みは、ここから“家族再会物語”の本番に入るみたい。
まだちょっと緊張してるけど、
ステラお姉ちゃんのとなりにいると、少しだけ大人になった気がする。
ステラお姉ちゃんとのぎこちない再会がひと段落したとき。
リビングの奥のドアが「ギィ」と開いた。
そこから出てきたのは、背の高い男の人だった。
髪は真っ白で、でも背筋はまっすぐ。スーツ姿がきちんと似合っていて、映画に出てきそうなくらいダンディだった。
「……Grandpa!」
ステラが声をかけると、その人がにこっと笑った。
「Oh… so, you are… Saku and Akane?」
——おじいちゃんだ。
おばあちゃんよりも少し無口そうで、声は低くて落ち着いてる。
でも、私たちを見つめる目はすごく優しかった。
「えっと……は、はい! わたし、Akane!」
「わ、わたしはSakuです!」
思わず、英語っぽく自己紹介してしまった。
おじいちゃんは嬉しそうに「Good! Very good!」と拍手してくれる。
咲姉が小声で私の耳元でささやいた。
「……なんか、学校の英語の授業より緊張するんだけど」
「わかる……!」
おじいちゃんは、葵兄の方に目をやった。
「Aoi. You are tall now. Very cool.」
そう言って、がっしりした手で葵兄の肩をポンと叩く。
葵兄は「は、はぁ……」と苦笑いしてたけど、ちょっと嬉しそうに見えた。
そのあと、おじいちゃんはみんなを見回してから、静かに言った。
「Family… together. Very happy.」
——その言葉に、胸がじんわりした。
日本語はあんまり通じないけど、気持ちはちゃんと伝わってくる。
「Family」って言葉がこんなにあったかく聞こえたのは初めてかもしれない。
おばあちゃんが小さく笑った。
「この人ね、普段はあまり口数が多くないの。でも“家族”のことになると、とても情熱的なのよ」
「……似てるな」
ぽつりと呟いたのは葵兄だった。
「え?」私と咲姉が同時に聞き返す。
「……俺たちの父さんと」
おじいちゃんはその会話がわからないはずなのに、なぜかにっこり笑って、ゆっくりうなずいた。
——ああ、この人も、私たちの“おじいちゃん”なんだ。
それを実感して、胸の奥がじんわり温かくなるのを感じた
✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎
ステラお姉ちゃんの案内で、私たちはそれぞれの部屋に荷物を運び終えた。
広い家にはゲストルームもたくさんあって、姉妹で同じ部屋にしてもらった。
でも、今日はまだ寝られそうにない。
「……なんか、夢みたいだよね」
ベッドの上で、咲姉がポツリとつぶやく。
「ほんとにね……ロンドンにいて、おばあちゃんがいて、そして、あのステラお姉ちゃんが実在してるんだもん」
「実在って……」
思わず笑っちゃった。
でも、気持ちはすっごくわかる。
ステラお姉ちゃんって、完璧すぎてちょっと現実味がないんだよね。
そのとき、コンコン、とノックの音。
「May I come in?(入ってもいい?)」
聞こえてきたのは、もちろんステラお姉ちゃんの声。
「うん!どうぞ!」
ドアが開いて、ステラお姉ちゃんがティーカップを3つ持って入ってきた。
「眠れないでしょ? だから、ハーブティー淹れてきたわ。
子どもでも飲めるカモミールよ」
「わあ……ありがとう!」
私と咲姉はベッドの端にちょこんと座って、ティーカップを受け取る。
「こっちの生活って、やっぱり違う?」
「うん。街の匂いも、人の目も、みんな違う感じがする」
「私も最初はすごく戸惑ったわ。でも、慣れると快適よ。自由で、心地よくて。
……それに、ここには“もうひとつの家族”がいるから」
「もうひとつの家族……?」
ステラお姉ちゃんはちょっと微笑んで、ティーカップを口元に運んだ。
「もちろん、血のつながった“本当の家族”にも会いたかった。
だから今、こうして話せてるのが……ちょっと信じられないのよ、実は」
……え?
あの完璧そうに見えるお姉ちゃんが、
そんなふうに“寂しかった”って思ってたなんて。
「じゃあさ、これから一緒に過ごせるの、嬉しい?」
「……とても、ね」
ステラお姉ちゃんが、そっと私たちの手を包むように握った。
「これからの数日間、たくさん話しましょう? 姉妹として」
「うん!」
「うん、絶対!」
このとき私の胸の中に、ふわっと暖かい何かが芽生えた。
遠く離れていた家族が、また一緒になれた気がして——
まるで、ずっと探していたピースがはまったみたいだった。