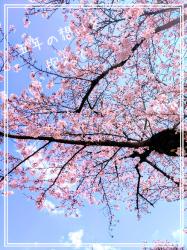混乱させると分かっていても、打たずにはいられなかった。
言い残したことがたくさんあって、知って欲しいこともいっぱいあった。
前もって考えておいた文を打っていく。
俺には時間がないから、本当は溢れる気持ちをなんとかとどめた。
俺のスマホを開いた人が見つけられるように、メモを開く指示をロック画面に出して、スマホを開くパスワードを切って。
ようやく全ての作業を終えた時、もうタイムリミットまであと数分のところまで来ていた。
俺はスマホを元に戻し、寝心地の悪いベッドに横たわる。
置かれた時計が59分を回っていることを確認して俺は目を閉じた。
『ばいばい』
目尻に涙が一筋伝ったとき、秒針が12を指した。
その瞬間、俺は消えた。
停止を伝える機械音は俺にはもう聞こえない。
言い残したことがたくさんあって、知って欲しいこともいっぱいあった。
前もって考えておいた文を打っていく。
俺には時間がないから、本当は溢れる気持ちをなんとかとどめた。
俺のスマホを開いた人が見つけられるように、メモを開く指示をロック画面に出して、スマホを開くパスワードを切って。
ようやく全ての作業を終えた時、もうタイムリミットまであと数分のところまで来ていた。
俺はスマホを元に戻し、寝心地の悪いベッドに横たわる。
置かれた時計が59分を回っていることを確認して俺は目を閉じた。
『ばいばい』
目尻に涙が一筋伝ったとき、秒針が12を指した。
その瞬間、俺は消えた。
停止を伝える機械音は俺にはもう聞こえない。