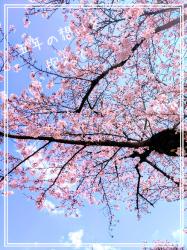待ち合わせ場所に現れた水季はいつもの明るさがなく、見ている方が苦しいほどだった。
「水季、大丈夫?」
「お兄ちゃんが、死んだ」
「え、」
あまりに予想していない重さの話でその後に言葉が続かない。
「休んでた間にお葬式とか、お兄ちゃんの荷物の整理とかしてた」
「…大変だったね」
「それで、佐那に聞きたいことがあって」
「え、私?」
授業のことだろうか、でもそんなことはわざわざ集まって聞くことでもないし、けどそれ以外に身に覚えがなくて、私は水季の様子を伺う。
「佐那さ、私のお兄ちゃんと知り合いだったりする?お兄ちゃんのスマホにこんなのがあって、私もあんまり見てないんだけど」
「水季、大丈夫?」
「お兄ちゃんが、死んだ」
「え、」
あまりに予想していない重さの話でその後に言葉が続かない。
「休んでた間にお葬式とか、お兄ちゃんの荷物の整理とかしてた」
「…大変だったね」
「それで、佐那に聞きたいことがあって」
「え、私?」
授業のことだろうか、でもそんなことはわざわざ集まって聞くことでもないし、けどそれ以外に身に覚えがなくて、私は水季の様子を伺う。
「佐那さ、私のお兄ちゃんと知り合いだったりする?お兄ちゃんのスマホにこんなのがあって、私もあんまり見てないんだけど」