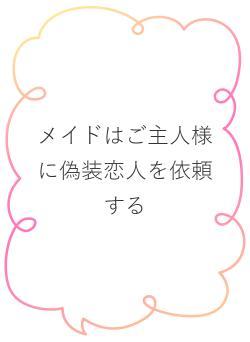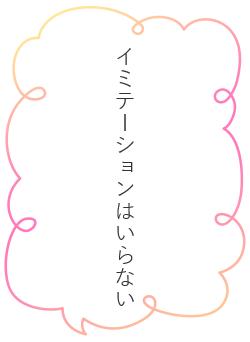「いやー、面白い子だね。夢川さん」
家に帰った夏希は春斗に対してそう切り出した。
夏希が唐突なのはいつものことなので普段なら気にしないが、夏希の口から出てきた名前に引っ掛かって、春斗は夏希へと視線を向けた。
「今日ね、夢川さんと話す機会があったんだけど、いいリアクションしてくれるんだよ」
「あまり夢川をからかうなよ」
「保護者面しちゃってまぁ……話聞きたくないの? 春斗のこと好き? って聞いてみたんだけどさ、なんて返ってきたと思う?」
「…………」
春斗の眉間にはしわが寄る。
あまり怒らせても怖いので、夏希はさっさと答えを告げることにした。
「友達として好き、だって」
「そうか」
春斗にとっては予想できた答えであってなんの問題もない。だがどうも満足いかない気分だ。
「それで次におれのことは? って聞いたんだけどさ、そしたらおれのことも友達として好きだって」
「…………」
春斗と琉莉は一年以上前からの付き合いだ。それなのに夏希と同じ評価なのは納得がいかない。だがそれを顔に出すのは悔しくて、春斗はノーリアクションを貫いた。
「おれにからかわれないように頑張ったんだろうね。負けん気が強くて可愛いよね、夢川さん」
「さっきも言ったが、あまり夢川をからかうな」
そこで春斗は話を切り上げて自分の部屋へと戻った。
自室でベッドに横になった後も、夏希の言葉が離れない。
『負けん気が強い』
夏希は確かにそう言った。けれど春斗は琉莉のことをそう思ったことは一度もない。一年以上一緒に役員の仕事をしていて、一度もないのだ。
自分の見たことのない琉莉の一面を夏希だけが知っている。その事実がひどく不愉快だった。
その日から、夏希が見ている琉莉を見たくて観察を始めた。
学校で夏希が琉莉といるときには話し掛けずに、遠くからそのやり取りを見守る。そして気付いたのは、琉莉が自分と一緒のときとはまるで違う表情をしている事実だった。
春斗といるときの琉莉は優秀だが遠慮がちなところがあった。けれど夏希と話している琉莉ははきはきしていて明るい。
ああいう琉莉の姿が夏希の目には映っていたのだと知った。
もう一つ。気付いたことがあった。
夏希は誰とでも仲良くしているが、その中でも琉莉は特別なようだった。他のみんなは気付いていないようだったが、春斗の目は誤魔化せない。
夏希は琉莉のことが好きなのだ。
夏希は中学のときから尋常じゃなくモテるし、自分よりも夏希の方が琉莉の相手に相応しい。春斗はそう感じた。
「春斗、今日も放課後生徒会あるんだろ」
「ああ。夏希はバイトだったな」
ちょうどよく廊下ですれ違った夏希に声を掛けられた。そうだ、と名案が浮かぶ。
役員の仕事が終わったら、琉莉を誘って夏希のバイト先であるコンビニに行こう。そうして二人の接触機会を増やせばいい。
夏希のようにいたずらをしない春斗の言うことに琉莉は簡単に従った。
コンビニに琉莉を連れて行くと、春斗が予想していなかった珍客がそこにいた。
「あらあら、春斗が夏希のいる時間にコンビニ来るなんて珍しいわね」
「……姉貴」
春斗と夏希の姉・秋菜。
話を聞くと、秋菜は仕事帰りにお酒とつまみを買って帰るところだったらしい。
「この子が春斗の彼女?」
春斗の横に立つ琉莉を見るなり、ルージュの引かれた唇が弧を描く。
「え、いえ……あのわたしは」
「あら、じゃあ夏希の彼女? まぁどっちでもいいわ。どっちと結婚しても私の妹になるんですものね」
笑いながらそんな冗談を言う。
秋菜は単なる冗談のつもりだったのだろうが、春斗は真剣に想像してしまった。
(そうか。もし夏希と上手くいったら、俺の妹になるのか)
微笑ましさより苦々しさの方が勝る。みんなが笑う中、ひとり口を引き結んでいた。
「秋菜さんは夏希くん似なんですね」
「夏希が私に似てるのよ」
「あ、それもそうか」
そのやり取りが耳に届いて、ようやく春斗も笑いの輪の中に戻る。
レジ打ちと支払いが終わると、夏希が「はーい、ありがとうございましたー」とさっさと帰れというメッセージのこもった挨拶をした。
「ばいばい、柊くん」
手を振って帰る琉莉に対して、夏希がはにかむ。
やっぱり夏希は琉莉が好きなんだな、と改めて春斗は思った。
なんかおかしい。
ついこの間まで普通だったのに、春斗くんの様子がおかしい。
「柊くんは何か知ってる?」
「……さぁ? 分からないな」
どうにもわたしは春斗くんに避けられてるみたい。春斗くんの機嫌を損ねることをした覚えがなくて、困惑してしまう。
春斗くんは尊敬できる生徒会長というだけでなく、大切な友達だ。そんな彼に距離を置かれるなんてことになれば苦しい。
「もしかして彼女ができたとかかな?」
夏希くんに可能性を告げると、思いの外胸が痛んだ。
自分で言っておいてなんだけど、春斗くんに彼女ができたなんて信じられない。役員の仕事があるときには一緒に帰っていたし、彼女の姿なんて影も形もなかった。
「それはないんじゃないかな。夢川さん以外の女の子の話しないし」
「……そっか」
心がわずかに浮上する。
嬉しい。春斗くんと一番仲がいいのはわたしなんだ。
「夏希」
「うわ、春斗! いつの間に!」
教室の後ろのドアから入ってきたらしい春斗くんが柊くんに話しかける。
「今日もコンビニでバイトだろ。帰りに期間限定の中華まん五個買って来てって連絡来た」
「知ってる。さっき俺にも届いてるし」
「ちゃんと見てたのか」
「あのさ、春斗はおれのこと信用してなさすぎ」
「二人とも性格は反対なのに仲いいよね」
春斗くんと柊くんのやりとりが面白くて声を掛けると柊くんは笑ってくれたけど、春斗くんは仏頂面で顔を逸らしてしまった。
「春斗くん?」
「大した用もないのに話し掛けないでくれないか」
「え……」
返ってきたリアクションに頭の中が真っ白になる。冷たく突き放されるなんてこと想像もしてなかった。
「おい春斗、そういう言い方はないだろ」
「じゃあ中華まん忘れるなよ」
春斗くんはわたしの方を振り返ることなく教室から出て行ってしまう。
「春斗くん」
「夢川さん、おれあいつと話してくるよ」
夏希くんがぽんとわたしの肩を叩いた。
「安心して待ってて」
「春斗! おれと夢川さんどっちが大事なんだよ!」
「女友達に少女漫画でも借りたのか?」
ひとりきりの生徒会室に乗り込んできた夏希に、淡々と春斗は返事をする。
「本気の質問だよ! おれと夢川さん、どっちが大事なんだよ!」
「……どちらも大事だが?」
「そこは夢川さんって言えよ!」
脱力してうなだれそうになるところを立て直し、夏希は本当に言いたかったことを伝える。
「春斗、おれに夢川さんを譲ろうとしてるだろ。自分だって夢川さんのことを好きなくせに」
「…………」
「本当に嘘が吐けないんだな、春斗は」
いつの間にか琉莉を好きになっていた夏希。そしてそれを感じ取っていた春斗。春斗がどうして琉莉と距離を取ったのかを考えたら、これしか理由がなかった。
「夢川さん、傷ついてた。夢川さんを傷つけてまで、おれのことを優先してくれるわけ?」
「夏希なら夢川を不幸にしないだろ」
「それって夢川さんの気持ちを考えてないんじゃないか」
「……夢川の気持ち? 夢川だって夏希と一緒で楽しそうだったが?」
夏希はこれ見よがしに溜息を吐いた。
「そりゃあ友達だからね。でも恋ってもっと特別だと思う。おれから見たら、春斗といるときの夢川さんは他の誰といるときとも違って幸せそうだった」
夏希から見れば、琉莉の特別は春斗の方だった。
いろんな女の子を見てきた夏希は、琉莉が本当に好きなのが誰かを見抜くことができた。
「春斗、おれは春斗にも幸せになってもらいたい」
「夏希」
「夢川さんが春斗のことを好きなら、答えはもうはっきりしてるだろ」
そこまで伝えると、春斗は生徒会室を飛び出していった。
「あーあ、鍵もかけずに出て行くなんて春斗らしくないな」
心の中で「がんばれ」と応援しながら、ひとり笑みを浮かべた。
「夢川」
「…………」
廊下を歩いているときに後ろから声がかかる。
わたしは振り向けなかった。声の主が誰だか知っていたから。
「ごめん、夢川」
「…………」
「俺は、夢川と夏希が恋人同士になればいいと思ってた」
「……そう」
「嘘だ。恋人同士になんてなって欲しくないって思ってたけど、それが一番二人のためだと思っていた」
春斗くんの話が理解できない。それがなんだというんだ。
両肩に重さが加わる。びっくりして振り返りそうになる。
「そのまま聞いてくれ」
「……分かった」
「俺は夢川のことが好きだ。夏希じゃなくて俺を選んで欲しい」
言われたことの意味が分からなくて、呆然とする。
春斗くんが、わたしのことを好き?
そう言ってもらえて心が震える。ずっと欲しかった言葉だった。
「……わたしも春斗くんのことが好き」
「それは友達として?」
「違うよ。男の子として春斗くんのことが好きなの」
ぎゅっと後ろから抱きしめられて、春斗くんの匂いが近くにある。
「俺の恋人になってください」
「……はい。すごく、嬉しい」
泣きそうになりながら、わたしは笑った。
家に帰った夏希は春斗に対してそう切り出した。
夏希が唐突なのはいつものことなので普段なら気にしないが、夏希の口から出てきた名前に引っ掛かって、春斗は夏希へと視線を向けた。
「今日ね、夢川さんと話す機会があったんだけど、いいリアクションしてくれるんだよ」
「あまり夢川をからかうなよ」
「保護者面しちゃってまぁ……話聞きたくないの? 春斗のこと好き? って聞いてみたんだけどさ、なんて返ってきたと思う?」
「…………」
春斗の眉間にはしわが寄る。
あまり怒らせても怖いので、夏希はさっさと答えを告げることにした。
「友達として好き、だって」
「そうか」
春斗にとっては予想できた答えであってなんの問題もない。だがどうも満足いかない気分だ。
「それで次におれのことは? って聞いたんだけどさ、そしたらおれのことも友達として好きだって」
「…………」
春斗と琉莉は一年以上前からの付き合いだ。それなのに夏希と同じ評価なのは納得がいかない。だがそれを顔に出すのは悔しくて、春斗はノーリアクションを貫いた。
「おれにからかわれないように頑張ったんだろうね。負けん気が強くて可愛いよね、夢川さん」
「さっきも言ったが、あまり夢川をからかうな」
そこで春斗は話を切り上げて自分の部屋へと戻った。
自室でベッドに横になった後も、夏希の言葉が離れない。
『負けん気が強い』
夏希は確かにそう言った。けれど春斗は琉莉のことをそう思ったことは一度もない。一年以上一緒に役員の仕事をしていて、一度もないのだ。
自分の見たことのない琉莉の一面を夏希だけが知っている。その事実がひどく不愉快だった。
その日から、夏希が見ている琉莉を見たくて観察を始めた。
学校で夏希が琉莉といるときには話し掛けずに、遠くからそのやり取りを見守る。そして気付いたのは、琉莉が自分と一緒のときとはまるで違う表情をしている事実だった。
春斗といるときの琉莉は優秀だが遠慮がちなところがあった。けれど夏希と話している琉莉ははきはきしていて明るい。
ああいう琉莉の姿が夏希の目には映っていたのだと知った。
もう一つ。気付いたことがあった。
夏希は誰とでも仲良くしているが、その中でも琉莉は特別なようだった。他のみんなは気付いていないようだったが、春斗の目は誤魔化せない。
夏希は琉莉のことが好きなのだ。
夏希は中学のときから尋常じゃなくモテるし、自分よりも夏希の方が琉莉の相手に相応しい。春斗はそう感じた。
「春斗、今日も放課後生徒会あるんだろ」
「ああ。夏希はバイトだったな」
ちょうどよく廊下ですれ違った夏希に声を掛けられた。そうだ、と名案が浮かぶ。
役員の仕事が終わったら、琉莉を誘って夏希のバイト先であるコンビニに行こう。そうして二人の接触機会を増やせばいい。
夏希のようにいたずらをしない春斗の言うことに琉莉は簡単に従った。
コンビニに琉莉を連れて行くと、春斗が予想していなかった珍客がそこにいた。
「あらあら、春斗が夏希のいる時間にコンビニ来るなんて珍しいわね」
「……姉貴」
春斗と夏希の姉・秋菜。
話を聞くと、秋菜は仕事帰りにお酒とつまみを買って帰るところだったらしい。
「この子が春斗の彼女?」
春斗の横に立つ琉莉を見るなり、ルージュの引かれた唇が弧を描く。
「え、いえ……あのわたしは」
「あら、じゃあ夏希の彼女? まぁどっちでもいいわ。どっちと結婚しても私の妹になるんですものね」
笑いながらそんな冗談を言う。
秋菜は単なる冗談のつもりだったのだろうが、春斗は真剣に想像してしまった。
(そうか。もし夏希と上手くいったら、俺の妹になるのか)
微笑ましさより苦々しさの方が勝る。みんなが笑う中、ひとり口を引き結んでいた。
「秋菜さんは夏希くん似なんですね」
「夏希が私に似てるのよ」
「あ、それもそうか」
そのやり取りが耳に届いて、ようやく春斗も笑いの輪の中に戻る。
レジ打ちと支払いが終わると、夏希が「はーい、ありがとうございましたー」とさっさと帰れというメッセージのこもった挨拶をした。
「ばいばい、柊くん」
手を振って帰る琉莉に対して、夏希がはにかむ。
やっぱり夏希は琉莉が好きなんだな、と改めて春斗は思った。
なんかおかしい。
ついこの間まで普通だったのに、春斗くんの様子がおかしい。
「柊くんは何か知ってる?」
「……さぁ? 分からないな」
どうにもわたしは春斗くんに避けられてるみたい。春斗くんの機嫌を損ねることをした覚えがなくて、困惑してしまう。
春斗くんは尊敬できる生徒会長というだけでなく、大切な友達だ。そんな彼に距離を置かれるなんてことになれば苦しい。
「もしかして彼女ができたとかかな?」
夏希くんに可能性を告げると、思いの外胸が痛んだ。
自分で言っておいてなんだけど、春斗くんに彼女ができたなんて信じられない。役員の仕事があるときには一緒に帰っていたし、彼女の姿なんて影も形もなかった。
「それはないんじゃないかな。夢川さん以外の女の子の話しないし」
「……そっか」
心がわずかに浮上する。
嬉しい。春斗くんと一番仲がいいのはわたしなんだ。
「夏希」
「うわ、春斗! いつの間に!」
教室の後ろのドアから入ってきたらしい春斗くんが柊くんに話しかける。
「今日もコンビニでバイトだろ。帰りに期間限定の中華まん五個買って来てって連絡来た」
「知ってる。さっき俺にも届いてるし」
「ちゃんと見てたのか」
「あのさ、春斗はおれのこと信用してなさすぎ」
「二人とも性格は反対なのに仲いいよね」
春斗くんと柊くんのやりとりが面白くて声を掛けると柊くんは笑ってくれたけど、春斗くんは仏頂面で顔を逸らしてしまった。
「春斗くん?」
「大した用もないのに話し掛けないでくれないか」
「え……」
返ってきたリアクションに頭の中が真っ白になる。冷たく突き放されるなんてこと想像もしてなかった。
「おい春斗、そういう言い方はないだろ」
「じゃあ中華まん忘れるなよ」
春斗くんはわたしの方を振り返ることなく教室から出て行ってしまう。
「春斗くん」
「夢川さん、おれあいつと話してくるよ」
夏希くんがぽんとわたしの肩を叩いた。
「安心して待ってて」
「春斗! おれと夢川さんどっちが大事なんだよ!」
「女友達に少女漫画でも借りたのか?」
ひとりきりの生徒会室に乗り込んできた夏希に、淡々と春斗は返事をする。
「本気の質問だよ! おれと夢川さん、どっちが大事なんだよ!」
「……どちらも大事だが?」
「そこは夢川さんって言えよ!」
脱力してうなだれそうになるところを立て直し、夏希は本当に言いたかったことを伝える。
「春斗、おれに夢川さんを譲ろうとしてるだろ。自分だって夢川さんのことを好きなくせに」
「…………」
「本当に嘘が吐けないんだな、春斗は」
いつの間にか琉莉を好きになっていた夏希。そしてそれを感じ取っていた春斗。春斗がどうして琉莉と距離を取ったのかを考えたら、これしか理由がなかった。
「夢川さん、傷ついてた。夢川さんを傷つけてまで、おれのことを優先してくれるわけ?」
「夏希なら夢川を不幸にしないだろ」
「それって夢川さんの気持ちを考えてないんじゃないか」
「……夢川の気持ち? 夢川だって夏希と一緒で楽しそうだったが?」
夏希はこれ見よがしに溜息を吐いた。
「そりゃあ友達だからね。でも恋ってもっと特別だと思う。おれから見たら、春斗といるときの夢川さんは他の誰といるときとも違って幸せそうだった」
夏希から見れば、琉莉の特別は春斗の方だった。
いろんな女の子を見てきた夏希は、琉莉が本当に好きなのが誰かを見抜くことができた。
「春斗、おれは春斗にも幸せになってもらいたい」
「夏希」
「夢川さんが春斗のことを好きなら、答えはもうはっきりしてるだろ」
そこまで伝えると、春斗は生徒会室を飛び出していった。
「あーあ、鍵もかけずに出て行くなんて春斗らしくないな」
心の中で「がんばれ」と応援しながら、ひとり笑みを浮かべた。
「夢川」
「…………」
廊下を歩いているときに後ろから声がかかる。
わたしは振り向けなかった。声の主が誰だか知っていたから。
「ごめん、夢川」
「…………」
「俺は、夢川と夏希が恋人同士になればいいと思ってた」
「……そう」
「嘘だ。恋人同士になんてなって欲しくないって思ってたけど、それが一番二人のためだと思っていた」
春斗くんの話が理解できない。それがなんだというんだ。
両肩に重さが加わる。びっくりして振り返りそうになる。
「そのまま聞いてくれ」
「……分かった」
「俺は夢川のことが好きだ。夏希じゃなくて俺を選んで欲しい」
言われたことの意味が分からなくて、呆然とする。
春斗くんが、わたしのことを好き?
そう言ってもらえて心が震える。ずっと欲しかった言葉だった。
「……わたしも春斗くんのことが好き」
「それは友達として?」
「違うよ。男の子として春斗くんのことが好きなの」
ぎゅっと後ろから抱きしめられて、春斗くんの匂いが近くにある。
「俺の恋人になってください」
「……はい。すごく、嬉しい」
泣きそうになりながら、わたしは笑った。