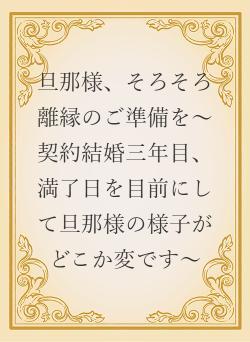――その表情に、俺は直感する。
ああ、これは良くないやつだ、と。
何が良くないかって? それはわからない。でもわかるだろう?
表情だけじゃない、空気感というやつが。理由はわからないが、大事な話をされるときのような。
例えを上げるなら、そう――別れ話とか。
(えっ。俺、今からユリシーズに振られるの?)
瞬間、頭の中がわけのわからない考えでいっぱいになる。
そんなはずはないとわかっているのに、デート帰りに彼女に振られた前世の記憶と重なって――。
――いや、待て。落ち着け。そもそも俺はユリシーズと付き合っていない。
つまり、これは断じて別れ話などではない。
だが、だとしたらいったい何だ? 俺、ユリシーズにこんな顔されることしたか? やっぱり肉ばっかり食べたのがいけなかったのか?
混乱する俺の視線の先で、ユリシーズは躊躇いがちに口を開く。――そして。
「アレク、君は本当に――――」
――だが、その言葉は最後まで続かなかった。
ユリシーズの言葉を遮るように、俺たちのすぐ横で馬車が急停止したからだ。
しかもそれはただの馬車ではなかった。
黒塗りに金の装飾の施された、貴族所有の一等馬車だった。
(――おい、この馬車って)
瞬間、俺はその馬車に乗っている人物が誰であるかを察した。
なぜなら馬車の扉に描かれた紋章は、この街に着いてから嫌と言うほど目にしたマークなのだから。
そのマークとは、“双頭の鷲”――この土地を治める領主、ノーザンバリー辺境伯の家紋である。
つまり、この馬車に乗っているのはノーザンバリー辺境伯であるということだ。
その馬車が、どういうわけか俺たちの隣に停まった。その理由は……?
「お……おい、ユリシーズ。何で領主の馬車がここに停まるんだ? まさか、セシルがこの宿に泊まることが――」
百歩譲って、もしも今の俺たちが貴族らしい服装をしていれば馬車が停まることもあったかもしれない。が、今の俺たちは誰がどう見たって貴族には見えないはず。
だがユリシーズは、慌てふためく俺の横で冷静に呟いたのだ。
「伯父上」――と。