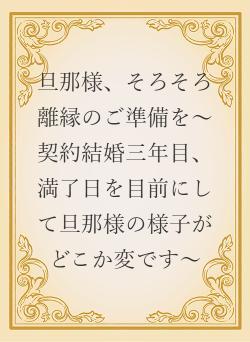――ああ、こいつは何てかっこいいんだろう。
俺だったら絶対に恥ずかしくて言えないような言葉を、こんなに真っすぐに伝えられるなんて。
俺はこいつのこういうところを、心底尊敬する。
俺は結局何も答えられず、けれどユリシーズは満足そうに微笑んだ。
すると丁度タイミングを見計らったかのように、ロイドが声を上げる。
「聖女さま、帰ってきたよ」――と。
その声に俺は眼下を見下ろした。
するとそこには確かに、ノーザンバリー辺境伯の紋の入った馬車があった。
――ああ、間違いない、リリアーナだ!
「俺、行ってくる!」
俺はユリシーズを顧みる。
すると、「うん、行ってらっしゃい」と言って、俺を送り出してくれるユリシーズ。
俺は部屋を飛び出して階段を駆け下りた。
玄関ホールの扉を開け、広いロータリーを駆け抜ける。
そして、停車した馬車から降りるリリアーナを思いきり抱き締めた。
「リリアーナ……! 怪我はないか!? よく頑張ったな! 偉いぞ!」
すると突然のことに驚いたのか、リリアーナは目をぱちくりとさせる。
――驚いた顔も最高だ。
リリアーナは少しの間俺の腕の中で茫然としていたが、しばらくしてハッと顔を上げた。
「お兄さま……お身体は……お身体の具合は……?」
「手紙送ったろ? もう大丈夫だ、心配ない」
「……あぁ……でも、だってお兄さまのことだから……」
「お前を心配させないように、嘘をついてるかもって?」
「……っ」
「そんな嘘すぐばれるだろ。俺だってそこまで愚かじゃない。――それよりごめんな。出発までずっとお前が看病してくれてたって、ユリシーズから聞いた。見送りできなくて悪かった」
「……そんな……そんなこと……! お兄さまがご無事なだけで……、わたしは……」
――ああ、リリアーナ……。
セシルやグレン、マリアや他の使用人たちの前にもかかわらず、俺はリリアーナを強く抱きしめる。
二度とリリアーナを悲しませないと。二度とリリアーナを傷付けないと。
そう深く心に刻み込み、俺は痺れを切らしたセシルによってリリアーナと引き離されるまで、久しぶりのリリアーナの感触を堪能したのだった。