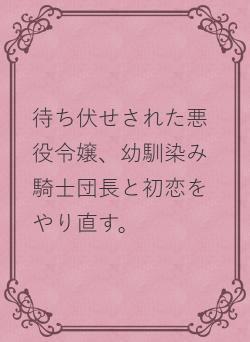王の側近として多忙なために、あまり社交場に出て来ないモーベット侯爵は、女性が一度は夢見るような……まるで御伽噺に出てくる王子様のように、とても容姿の整った男性だった。
日光に透けてきらめくさらりとした金髪に、長い睫毛にけぶる清水を思わせる涼やかな水色の瞳。本当に同じ人間なのかと疑ってしまうくらいに、凜々しく造作の整ったお顔。
現在は宰相補佐……つまり、文官として城で働いているけれど、以前は軍人になる道も考えていたらしく、程よく肉付き体は鍛えられていた。
おまけに見上げるほどに背が高く、こうして近くに立ったままで私が目線を合わせようとすると、こちらの方が首が痛くなってしまいそうだった。
「あらあら! まあ。こうして並んでいるのを見ると、本当にお似合いの二人だわ。まるで結婚することになるのが、決められていた運命のようね」
うっとりとした叔母の身内びいきが過ぎる大袈裟な言いように、私は苦笑いをした。だって、モーベット侯爵が、私にお似合いな訳がないもの。
日光に透けてきらめくさらりとした金髪に、長い睫毛にけぶる清水を思わせる涼やかな水色の瞳。本当に同じ人間なのかと疑ってしまうくらいに、凜々しく造作の整ったお顔。
現在は宰相補佐……つまり、文官として城で働いているけれど、以前は軍人になる道も考えていたらしく、程よく肉付き体は鍛えられていた。
おまけに見上げるほどに背が高く、こうして近くに立ったままで私が目線を合わせようとすると、こちらの方が首が痛くなってしまいそうだった。
「あらあら! まあ。こうして並んでいるのを見ると、本当にお似合いの二人だわ。まるで結婚することになるのが、決められていた運命のようね」
うっとりとした叔母の身内びいきが過ぎる大袈裟な言いように、私は苦笑いをした。だって、モーベット侯爵が、私にお似合いな訳がないもの。