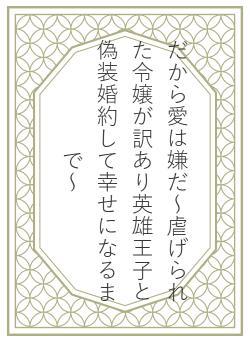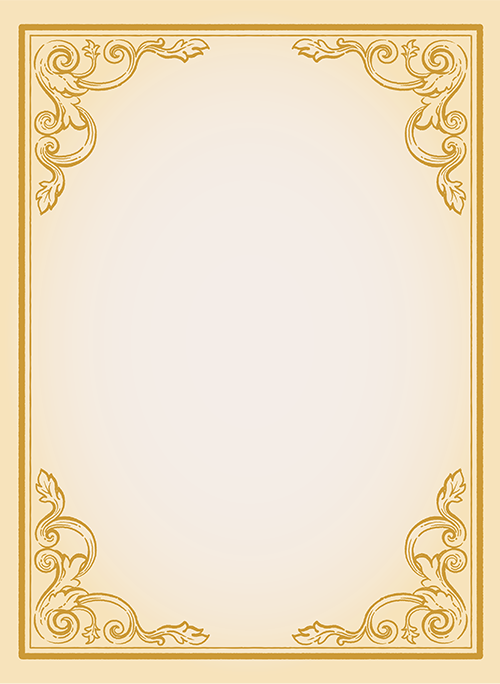次の日。
私はクルトに伝えた通り、ベイリー公爵家に向かっていた。
そんな私に騎士団長のアロンと、その部下が一人付き添っている。
アロンは王都遠征の責任者だ。本来ならシンシア様の側を離れるなんてありえない。
でも、シンシア様がターチェ家に戻ったとたんに、バルゴアの騎士たちが滞在している場所に乗り込んで「この中で、一番優秀で強い人は誰ですか⁉」と叫んだ。
騎士たちが「お嬢?」「テオドール様?」とざわつく中、すぐにアロンが「一番かは分かりませんが、責任者は俺です」と名乗り出る。
「でしたら、あなたは明日からテオドール様の護衛をしてください」
「っ、はい!」
一瞬だけ戸惑ったものの、即座に指示に従う姿はさすがだった。ここにいる騎士たちは、バルゴアに忠誠を誓っている。シンシア様ももちろんその忠誠の対象に含まれていた。
慌てた私が「アロンは、騎士団を率いる存在です。私の護衛をするわけには――」と口を挟むと、シンシア様がジトッとした目で私を見た。
今までそんな視線を向けられたことがなかった私は、シンシア様の新たな一面を見れた気がして、場違いにも胸が高鳴る。
「でしたら、騎士団ごとテオドール様の護衛につけましょうか?」
「え? いや、それは……」
「嫌でしょう? 言っときますけどね、私は過保護にされるのには慣れているんです! テオドール様を私と同じくらい過保護にすることだってできるんですよ!」
こんなに可愛い脅し文句を、私は今まで聞いたことがない。
私たちの会話を騎士たちがニヤニヤしながら聞いている。シンシア様は、そんな騎士たちを振り返った。
「テオドール様は、明日から危険な場所に行きます。だから、皆さんでテオドール様を守ってほしいんです。お願いします」
シンッと静まり返った中で、誰かが「お嬢の、お願い?」と呟く。それは次第に広がり、歓声へと変わっていく。
「わああああ! お嬢からの初めてのお願いだ!」
「お嬢が俺たちにお願いする日が来るなんて!」
「もちろんです! 任せてください!」
「今日は祝いだ!」
盛り上がる騎士たちの横で、シンシア様が「どうして、そうなるんですか……」と呆れている。
「皆、シンシア様に頼ってもらって嬉しいんですよ」
「そういうものですか?」
その顔にはよく分からないと書かれていた。
「うーん。でも、私もさっきテオドール様にお願いしてもらって嬉しかったので、それと似たような感じかもしれませんね」
「シンシア様は、私に頼られたら嬉しいのですか?」
「それは、もちろん!」
シンシア様に頼られたいとは思っていたが、頼って喜んでもらえるなんて思っていなかった。一方的に頼られたいという私の考えは、シンシア様には失礼なことだったのかもしれない。
「でしたら、私はシンシア様を頼るので、シンシア様も私を頼ってくださいね」
「はい」
嬉しそうに微笑むシンシア様を見て、これが正解だったのだと気がつく。
そういうことがあり、私の護衛にまさかのアロンがついている。もう一人のアロンの部下エドガーもかなり優秀な者らしい。
二人とも精悍な顔つきで、身体も私と比べ物にならないくらい鍛え上げている。そして、腰には剣。
これだけ立派な護衛を連れてくるとは思っていなかったらしく、私を出迎えたベイリー公爵は、顔を引きつらせていた。
「お久しぶりです」
私が声をかけると「あ、ああ。久しいな」と無理やり笑みを浮かべる。
「テオドール、こちらの方々は?」
「バルゴアで騎士団長をしているアロンと、その部下エドガーです。シンシア様が私の護衛につけてくださいました」
「き、騎士団長が、おまえの護衛に?」
青ざめる様子を見て、思わずため息をついてしまう。
ずっと冷遇し続けている息子が、他の場所で優遇されていることを受け止めきれないのだろう。
「クルトから聞きました。仕事が溜まっているそうですね?」
「あ、ああ……。忙しくてな。少し手伝ってくれ」
ベイリー公爵は、私が王家の役人になり、しばらく経った頃にも、そんなことを言いながら私に仕事を押しつけてきた。
その少しの手伝いがどんどん増えて行き、ベイリー公爵家から毎日のように書類が送られてくることになるなんて、あのときの私は思いもしなかった。
久しぶりに顔を合わせたベイリー公爵は相変わらずで、私の訪問を歓迎する様子もなく、執務室へと案内する。
中に入ると、執務机には書類の山ができていた。よくここまで溜め込んだなと感心してしまう。
「では、始めましょうか」
執務机に座った私は、書類に取りかかった。
初めは疑うように私の仕事を見ていたベイリー公爵だが、何枚か仕上げた書類を確認すると、上機嫌になり去っていく。手伝う気はまったくないらしい。
ベイリー公爵が部屋から出て行くのを見届けてから、私は書類の最後に自身のサインを書き足した。
「アロン。確認し終わった書類を、送り主に返送してください」
「はい、分かりました」
アロンもエドガーも、文句を言わず黙々と雑用をこなしてくれるので、どんどん書類の山が片付いていった。
王家の役人時代も、雑用係を雇えばよかったのかもしれないと思ったが、雇った者が信頼できるとは限らない。優秀で信頼できる人材がいるということは、それだけで強みになるのだと、つくづく思う。
日が暮れると、メイドが執務室に食事を3人分運んできた。
パンにスープ、肉と野菜が少し。その食事を見たアロンが「さっき通りかかったんですが、公爵とその息子が、これとは比べ物にならないくらいのごちそう食って酒飲んで騒いでいましたよ」と教えてくれる。
子どもの頃からそうだったが、相変わらず私を食事の席に招くつもりはないようだ。食事がまずくなるので、今さら招いてほしいとも思わないが、バルゴアの騎士たちにもこの待遇をすることに、問題を感じないのは愚かだと思う。
エドガーが先に食べて「おかしなものは、入っていませんね」と毒見をしてくれた。
「私に仕事をさせるのが目的なので、毒を盛ることはないでしょう。逃げられないようにして、私をどこかに閉じ込める可能性は高いですが」
そう伝えると、目に見えてアロンと部下の表情が険しくなった。味方がいてくれるというのは、とても心強い。
あっという間に3日が経った。
山積みになっていた書類の山は、綺麗さっぱりなくなっている。
執務室で、のんびりとお茶を楽しんでいるところに、クルトが入ってきた。
「ねぇ、兄さん。神殿からこんな手紙が届いたんだ。どういう意味だと思う?」
手紙の中身を見ると、アンジェリカ様が神殿に入ったことを知らせるものだった。
クルトに「アンジェリカ様は、今どちらに?」と尋ねると、「さぁ?」と興味なさそうな声が返って来た。
そういえば、アロンが見かけた食事の席に、アンジェリカ様はいなかった。この家の中で、アンジェリカ様は私と同じような扱いを受けていたのかもしれない。だとすれば、彼女がここから逃げ出すのも当然のこと。
「アンジェリカ様は、神殿に入ったそうだ。洗礼を済ませたので、おまえとの婚姻関係も白紙に戻った」
「え? それって、僕がアンジェリカと離婚できたってこと?」
「そうなるな」
「やった!」
手放しで喜ぶクルトは、自分が王家を敵に回し、アンジェリカ様からも見放されたことに気がついていない。
「だったら、兄さん。シンシア様をここに呼んでよ!」
あんなことをしておいて、まだシンシア様を狙っていることに内心で驚いてしまう。自分は誰からも愛されて当たり前だという自信が人をここまで愚かにするのか。
湧き上がった怒りを抑え込みながら、私は口を開いた。
「……4日後に、ここに来ることになっている」
「そうなの⁉ ちょうど良かった! そうだ、シンシア様に贈る物を買いに行ってくるよ!」
満面の笑みで執務室を出て行くクルトを私は見送る。
その様子を見ていたアロンが「どうして、シンシア様が自分に会いに来ると思えるんでしょうね?」と呆れている。
クルトは両親から愛されて育った。そして、社交界に出たあとは、その美貌で女性たちからのお誘いが絶えなかったらしい。会話もうまいので、多くの貴族からも好かれていた。
アンジェリカ様の心を射止めて、結婚できたことに満足していたら……。妻を愛して大切にしていたら、彼の未来は明るかったかもしれない。今となっては、その道は完全に閉ざされてしまった。
さらに3日経つと、ベイリー公爵が執務室に駆け込んできた。
「一体、何をした⁉」
「何をと言われても……」
公爵は手に持っていた手紙を、執務机に叩きつけた。
それらはベイリー公爵家と深い関わりのある家々からだった。
「傍系が一斉に、私に公爵の座を退くように訴えてきた! そして、全員がクルトではなくおまえに後を継がせろと言っている!」
「私は仕事をしていただけです」
そう言いながら、書類をベイリー公爵に見せた。
目が書類の上から下に動いていき、最後に大きく見開く。
「……テオドール・ベイリー、だと? おまえ、まさか、書類に自分のサインを……?」
声を震わすベイリー公爵に、私は微笑みかける。
「そうですよ、サインしました。ここに山と積んであった書類、全てに」
これまでは、ベイリー公爵家から回って来た書類には、ベイリー公爵のサインをしていた。書類を見た者が、ベイリー公爵が採決したものだと思うように。
今回は、それをやめて、私のサインに変えただけ。
普通なら王家の役人だった私に仕事を押しつけていたなんて信じてもらえない。しかし、私が王都からいなくなったとたんに、ベイリー公爵の仕事が滞った。そして、ようやく以前のように仕事が回りだしたと思ったら、書類には私のサインがしてある。
サインを見て、多くの者が気づいただろう。ベイリー公爵は、今までずっと息子のテオドールに仕事を押しつけていたのだと。
「テオドール、貴様なんてことを!」
私はクルトに伝えた通り、ベイリー公爵家に向かっていた。
そんな私に騎士団長のアロンと、その部下が一人付き添っている。
アロンは王都遠征の責任者だ。本来ならシンシア様の側を離れるなんてありえない。
でも、シンシア様がターチェ家に戻ったとたんに、バルゴアの騎士たちが滞在している場所に乗り込んで「この中で、一番優秀で強い人は誰ですか⁉」と叫んだ。
騎士たちが「お嬢?」「テオドール様?」とざわつく中、すぐにアロンが「一番かは分かりませんが、責任者は俺です」と名乗り出る。
「でしたら、あなたは明日からテオドール様の護衛をしてください」
「っ、はい!」
一瞬だけ戸惑ったものの、即座に指示に従う姿はさすがだった。ここにいる騎士たちは、バルゴアに忠誠を誓っている。シンシア様ももちろんその忠誠の対象に含まれていた。
慌てた私が「アロンは、騎士団を率いる存在です。私の護衛をするわけには――」と口を挟むと、シンシア様がジトッとした目で私を見た。
今までそんな視線を向けられたことがなかった私は、シンシア様の新たな一面を見れた気がして、場違いにも胸が高鳴る。
「でしたら、騎士団ごとテオドール様の護衛につけましょうか?」
「え? いや、それは……」
「嫌でしょう? 言っときますけどね、私は過保護にされるのには慣れているんです! テオドール様を私と同じくらい過保護にすることだってできるんですよ!」
こんなに可愛い脅し文句を、私は今まで聞いたことがない。
私たちの会話を騎士たちがニヤニヤしながら聞いている。シンシア様は、そんな騎士たちを振り返った。
「テオドール様は、明日から危険な場所に行きます。だから、皆さんでテオドール様を守ってほしいんです。お願いします」
シンッと静まり返った中で、誰かが「お嬢の、お願い?」と呟く。それは次第に広がり、歓声へと変わっていく。
「わああああ! お嬢からの初めてのお願いだ!」
「お嬢が俺たちにお願いする日が来るなんて!」
「もちろんです! 任せてください!」
「今日は祝いだ!」
盛り上がる騎士たちの横で、シンシア様が「どうして、そうなるんですか……」と呆れている。
「皆、シンシア様に頼ってもらって嬉しいんですよ」
「そういうものですか?」
その顔にはよく分からないと書かれていた。
「うーん。でも、私もさっきテオドール様にお願いしてもらって嬉しかったので、それと似たような感じかもしれませんね」
「シンシア様は、私に頼られたら嬉しいのですか?」
「それは、もちろん!」
シンシア様に頼られたいとは思っていたが、頼って喜んでもらえるなんて思っていなかった。一方的に頼られたいという私の考えは、シンシア様には失礼なことだったのかもしれない。
「でしたら、私はシンシア様を頼るので、シンシア様も私を頼ってくださいね」
「はい」
嬉しそうに微笑むシンシア様を見て、これが正解だったのだと気がつく。
そういうことがあり、私の護衛にまさかのアロンがついている。もう一人のアロンの部下エドガーもかなり優秀な者らしい。
二人とも精悍な顔つきで、身体も私と比べ物にならないくらい鍛え上げている。そして、腰には剣。
これだけ立派な護衛を連れてくるとは思っていなかったらしく、私を出迎えたベイリー公爵は、顔を引きつらせていた。
「お久しぶりです」
私が声をかけると「あ、ああ。久しいな」と無理やり笑みを浮かべる。
「テオドール、こちらの方々は?」
「バルゴアで騎士団長をしているアロンと、その部下エドガーです。シンシア様が私の護衛につけてくださいました」
「き、騎士団長が、おまえの護衛に?」
青ざめる様子を見て、思わずため息をついてしまう。
ずっと冷遇し続けている息子が、他の場所で優遇されていることを受け止めきれないのだろう。
「クルトから聞きました。仕事が溜まっているそうですね?」
「あ、ああ……。忙しくてな。少し手伝ってくれ」
ベイリー公爵は、私が王家の役人になり、しばらく経った頃にも、そんなことを言いながら私に仕事を押しつけてきた。
その少しの手伝いがどんどん増えて行き、ベイリー公爵家から毎日のように書類が送られてくることになるなんて、あのときの私は思いもしなかった。
久しぶりに顔を合わせたベイリー公爵は相変わらずで、私の訪問を歓迎する様子もなく、執務室へと案内する。
中に入ると、執務机には書類の山ができていた。よくここまで溜め込んだなと感心してしまう。
「では、始めましょうか」
執務机に座った私は、書類に取りかかった。
初めは疑うように私の仕事を見ていたベイリー公爵だが、何枚か仕上げた書類を確認すると、上機嫌になり去っていく。手伝う気はまったくないらしい。
ベイリー公爵が部屋から出て行くのを見届けてから、私は書類の最後に自身のサインを書き足した。
「アロン。確認し終わった書類を、送り主に返送してください」
「はい、分かりました」
アロンもエドガーも、文句を言わず黙々と雑用をこなしてくれるので、どんどん書類の山が片付いていった。
王家の役人時代も、雑用係を雇えばよかったのかもしれないと思ったが、雇った者が信頼できるとは限らない。優秀で信頼できる人材がいるということは、それだけで強みになるのだと、つくづく思う。
日が暮れると、メイドが執務室に食事を3人分運んできた。
パンにスープ、肉と野菜が少し。その食事を見たアロンが「さっき通りかかったんですが、公爵とその息子が、これとは比べ物にならないくらいのごちそう食って酒飲んで騒いでいましたよ」と教えてくれる。
子どもの頃からそうだったが、相変わらず私を食事の席に招くつもりはないようだ。食事がまずくなるので、今さら招いてほしいとも思わないが、バルゴアの騎士たちにもこの待遇をすることに、問題を感じないのは愚かだと思う。
エドガーが先に食べて「おかしなものは、入っていませんね」と毒見をしてくれた。
「私に仕事をさせるのが目的なので、毒を盛ることはないでしょう。逃げられないようにして、私をどこかに閉じ込める可能性は高いですが」
そう伝えると、目に見えてアロンと部下の表情が険しくなった。味方がいてくれるというのは、とても心強い。
あっという間に3日が経った。
山積みになっていた書類の山は、綺麗さっぱりなくなっている。
執務室で、のんびりとお茶を楽しんでいるところに、クルトが入ってきた。
「ねぇ、兄さん。神殿からこんな手紙が届いたんだ。どういう意味だと思う?」
手紙の中身を見ると、アンジェリカ様が神殿に入ったことを知らせるものだった。
クルトに「アンジェリカ様は、今どちらに?」と尋ねると、「さぁ?」と興味なさそうな声が返って来た。
そういえば、アロンが見かけた食事の席に、アンジェリカ様はいなかった。この家の中で、アンジェリカ様は私と同じような扱いを受けていたのかもしれない。だとすれば、彼女がここから逃げ出すのも当然のこと。
「アンジェリカ様は、神殿に入ったそうだ。洗礼を済ませたので、おまえとの婚姻関係も白紙に戻った」
「え? それって、僕がアンジェリカと離婚できたってこと?」
「そうなるな」
「やった!」
手放しで喜ぶクルトは、自分が王家を敵に回し、アンジェリカ様からも見放されたことに気がついていない。
「だったら、兄さん。シンシア様をここに呼んでよ!」
あんなことをしておいて、まだシンシア様を狙っていることに内心で驚いてしまう。自分は誰からも愛されて当たり前だという自信が人をここまで愚かにするのか。
湧き上がった怒りを抑え込みながら、私は口を開いた。
「……4日後に、ここに来ることになっている」
「そうなの⁉ ちょうど良かった! そうだ、シンシア様に贈る物を買いに行ってくるよ!」
満面の笑みで執務室を出て行くクルトを私は見送る。
その様子を見ていたアロンが「どうして、シンシア様が自分に会いに来ると思えるんでしょうね?」と呆れている。
クルトは両親から愛されて育った。そして、社交界に出たあとは、その美貌で女性たちからのお誘いが絶えなかったらしい。会話もうまいので、多くの貴族からも好かれていた。
アンジェリカ様の心を射止めて、結婚できたことに満足していたら……。妻を愛して大切にしていたら、彼の未来は明るかったかもしれない。今となっては、その道は完全に閉ざされてしまった。
さらに3日経つと、ベイリー公爵が執務室に駆け込んできた。
「一体、何をした⁉」
「何をと言われても……」
公爵は手に持っていた手紙を、執務机に叩きつけた。
それらはベイリー公爵家と深い関わりのある家々からだった。
「傍系が一斉に、私に公爵の座を退くように訴えてきた! そして、全員がクルトではなくおまえに後を継がせろと言っている!」
「私は仕事をしていただけです」
そう言いながら、書類をベイリー公爵に見せた。
目が書類の上から下に動いていき、最後に大きく見開く。
「……テオドール・ベイリー、だと? おまえ、まさか、書類に自分のサインを……?」
声を震わすベイリー公爵に、私は微笑みかける。
「そうですよ、サインしました。ここに山と積んであった書類、全てに」
これまでは、ベイリー公爵家から回って来た書類には、ベイリー公爵のサインをしていた。書類を見た者が、ベイリー公爵が採決したものだと思うように。
今回は、それをやめて、私のサインに変えただけ。
普通なら王家の役人だった私に仕事を押しつけていたなんて信じてもらえない。しかし、私が王都からいなくなったとたんに、ベイリー公爵の仕事が滞った。そして、ようやく以前のように仕事が回りだしたと思ったら、書類には私のサインがしてある。
サインを見て、多くの者が気づいただろう。ベイリー公爵は、今までずっと息子のテオドールに仕事を押しつけていたのだと。
「テオドール、貴様なんてことを!」