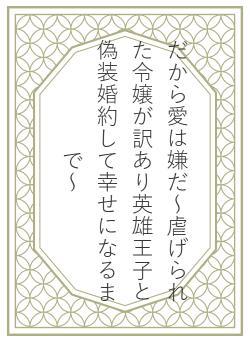ーー 結婚なんてしなければ良かった、アンジェリカのせいで僕の人生はめちゃくちゃだよ!
クルトのその言葉を聞いて、これまでの彼の言動がようやく理解できた。
何も知らなかった頃の私は、クルトと結婚できたことを喜んでいた。でも、クルトは私とは違い早い段階でこの結婚を後悔していたのね。
だから、結婚後の私に対して、あんなにも無関心だったんだわ。
私の幸せがクルトとの結婚で壊れたように、クルトの幸せも私と結婚したことで壊れた。
私たちに幸せな結婚生活なんて、初めからなかったんだわ。こんな簡単なことに、今まで気がつけなかったなんて……。
呆然と立ち尽くしていると、「アンジェリカ様……」と遠慮がちに声をかけられた。なぜかシンシアが今にも泣きそうな顔をしている。
どうして、そんな顔をしているのよ。大変な目に遭ったのは、あなたなのに。
私は大丈夫だと伝えて別れたけど、それは決して強がりなんかじゃなかった。
一緒にいた時間は、わずかだったけど、シンシアは私にたくさんのことを教えてくれた。
私が幸せになりたいように、他人も幸せになりたいと願っている。もし、私がクルトの幸せを考えていたら、何か違っていたのかしら?
クルトは腰が抜けているのか、まだ地面に座り込んでいる。そして、テオドールが明日、ベイリー公爵家に来ることを無邪気に喜んでいた。
私は背後から、そっとクルトに声をかけた。
「ねぇ、クルト」
振り返ったクルトは、私がいることに驚いている。
「なんだ、アンジェリカ。いたのか」
その声は、とても冷たい。
「私があなたにできることってあるかしら?」
「何を今さら……」
そうよね。私も今さらだと思うわ。でも、きっとこれが最後になると思うから。
私の言葉を鼻で笑ったクルトは「そうだな……。僕たちが離婚できるように陛下を説得してくれよ」と言った。
「それがあなたの幸せなの?」
「幸せ? そうだよ。アンジェリカには無理だろうけどね」
「分かったわ。やってみる」
「え?」
「……クルト。あなたを愛して選んでしまってごめんなさい。さようなら」
クルトは驚いていたけど、彼が何かを言う前に私は背を向け歩き出した。
テオドールの来訪を喜んでいるクルトは、きっとテオドールの後始末の仕方を知らない。
テオドールにかかれば事件をもみ消すなんて簡単なこと。そして、敵を排除するのもお手の物。私の婚約者だった頃、そうすることで彼は、私への批判を最小限に抑えていた。
今ならお父様がテオドールを私の王配に選んだ理由が分かる。きっと優秀なテオドールを敵に回したくなかったんだわ。
そんなテオドールは、今回のことでベイリー公爵家を敵と判断した。このままでは、ベイリー公爵家の一員になっている私まで排除されてしまう。そうなれば、お父様やロザリンドにまた迷惑がかかる。それだけは避けなければ。
私はシンシアが教えてくれた『この晩餐会の目的は、恐らくアンジェリカ様の救済だと思います』という言葉を信じて、元来た道を急いで戻った。
お茶会は、まだやっているかしら? 終わっていたらどうしよう?
私に気がついた王宮メイドが、お茶会会場へと案内してくれる。
中に入ると、ロザリンドに微笑みかけられた。その表情はどこかホッとしている。
「お姉様。お待ちしておりました」
言葉の通りロザリンドは私を待っていてくれたようで、すぐに席に案内された。
晩餐会に参加していた数人の貴族女性が、すでに席に着いている。彼女たちは、私に会釈したあと、何事もなかったように穏やかな会話を始めた。
ここには王女時代に私を称えて、媚びへつらっていた者たちは一人もいない。そのせいで、誰が誰なのかよく分からなかった。おそらくロザリンドを支持している家の者たちだと思う。
そんな中、ロザリンドが「本当に浮気をくり返す男性は嫌ですわね」と言った。驚く私に「先ほどまで、その話をしていたのです」と微笑む。
その言葉は、浮気男に嫁いだ私への嫌みにも聞こえる。むしろ、今までの私ならそう受け取って激怒していたはず。
でも、シンシアはお茶会に行けば『アンジェリカ様の味方ができるかもしれませんよ』と言っていた。だとすれば、もしかして、これは……。
私は悩みながらもロザリンドに「その男性の妻は、どうしていたの?」と尋ねた。
「度重なる浮気に耐えかねて、神殿に入ったそうです」
「神殿に?」
「はい。神殿に入れば貴族であれ平民であれ、神の名のもとに平等です。一度、神殿に入った者を、何者であれ無理やり連れもどすことはできないのです」
「知らなかったわ」
「そうですね。私もつい最近まで知りませんでした。このことは、公(おおやけ)にはされていませんから」
「どうして?」
「神殿側が誰でも受け入れようとしているわけではなく、元から信仰心が高い者が、神殿に相談に来たときだけの例外的な対応なのです」
「本来は、信者を保護するためのものなのね。でも、神殿に入ってしまったら妻の生家には、迷惑はかからないの?」
ロザリンドは、静かに頷く。
「神殿では、病院や孤児院での奉仕活動、困窮者への炊き出しなど様々な活動を行っています。それらは、徳が高いことだとされていて、褒められはしても、生家が迷惑に思うことはありません」
「そう……」
ロザリンドは私をまっすぐ見つめた。
「王家は神殿に多額の寄付をしています。決して拒むことはないでしょう」
これはようするに、クルトとの結婚生活がつらかったら神殿に入りなさいということなのね?
そうすれば、王家に迷惑がかからないことを教えてくれている。私は気になっていたことを、ロザリンドに尋ねた。
「神殿に入れば、婚姻関係はなくなるの?」
「はい。洗礼を受ければ神の子になりますので、婚姻も解消されたことになります」
それなら、私と離婚したいというクルトの願いも叶う。
「分かったわ。ありがとう」
私がお礼を言うと、ロザリンドの瞳が見開かれた。14歳になったばかりの彼女は、まだどこかあどけなさを残している。
「ロザリンド。全部押しつけてごめんなさい。大変でしょう……?」
小さく首を振り、ロザリンドは少し困ったように微笑んだ。
「お姉様の大変さが、今になってようやく私にも分かってきたところです」
クルトのその言葉を聞いて、これまでの彼の言動がようやく理解できた。
何も知らなかった頃の私は、クルトと結婚できたことを喜んでいた。でも、クルトは私とは違い早い段階でこの結婚を後悔していたのね。
だから、結婚後の私に対して、あんなにも無関心だったんだわ。
私の幸せがクルトとの結婚で壊れたように、クルトの幸せも私と結婚したことで壊れた。
私たちに幸せな結婚生活なんて、初めからなかったんだわ。こんな簡単なことに、今まで気がつけなかったなんて……。
呆然と立ち尽くしていると、「アンジェリカ様……」と遠慮がちに声をかけられた。なぜかシンシアが今にも泣きそうな顔をしている。
どうして、そんな顔をしているのよ。大変な目に遭ったのは、あなたなのに。
私は大丈夫だと伝えて別れたけど、それは決して強がりなんかじゃなかった。
一緒にいた時間は、わずかだったけど、シンシアは私にたくさんのことを教えてくれた。
私が幸せになりたいように、他人も幸せになりたいと願っている。もし、私がクルトの幸せを考えていたら、何か違っていたのかしら?
クルトは腰が抜けているのか、まだ地面に座り込んでいる。そして、テオドールが明日、ベイリー公爵家に来ることを無邪気に喜んでいた。
私は背後から、そっとクルトに声をかけた。
「ねぇ、クルト」
振り返ったクルトは、私がいることに驚いている。
「なんだ、アンジェリカ。いたのか」
その声は、とても冷たい。
「私があなたにできることってあるかしら?」
「何を今さら……」
そうよね。私も今さらだと思うわ。でも、きっとこれが最後になると思うから。
私の言葉を鼻で笑ったクルトは「そうだな……。僕たちが離婚できるように陛下を説得してくれよ」と言った。
「それがあなたの幸せなの?」
「幸せ? そうだよ。アンジェリカには無理だろうけどね」
「分かったわ。やってみる」
「え?」
「……クルト。あなたを愛して選んでしまってごめんなさい。さようなら」
クルトは驚いていたけど、彼が何かを言う前に私は背を向け歩き出した。
テオドールの来訪を喜んでいるクルトは、きっとテオドールの後始末の仕方を知らない。
テオドールにかかれば事件をもみ消すなんて簡単なこと。そして、敵を排除するのもお手の物。私の婚約者だった頃、そうすることで彼は、私への批判を最小限に抑えていた。
今ならお父様がテオドールを私の王配に選んだ理由が分かる。きっと優秀なテオドールを敵に回したくなかったんだわ。
そんなテオドールは、今回のことでベイリー公爵家を敵と判断した。このままでは、ベイリー公爵家の一員になっている私まで排除されてしまう。そうなれば、お父様やロザリンドにまた迷惑がかかる。それだけは避けなければ。
私はシンシアが教えてくれた『この晩餐会の目的は、恐らくアンジェリカ様の救済だと思います』という言葉を信じて、元来た道を急いで戻った。
お茶会は、まだやっているかしら? 終わっていたらどうしよう?
私に気がついた王宮メイドが、お茶会会場へと案内してくれる。
中に入ると、ロザリンドに微笑みかけられた。その表情はどこかホッとしている。
「お姉様。お待ちしておりました」
言葉の通りロザリンドは私を待っていてくれたようで、すぐに席に案内された。
晩餐会に参加していた数人の貴族女性が、すでに席に着いている。彼女たちは、私に会釈したあと、何事もなかったように穏やかな会話を始めた。
ここには王女時代に私を称えて、媚びへつらっていた者たちは一人もいない。そのせいで、誰が誰なのかよく分からなかった。おそらくロザリンドを支持している家の者たちだと思う。
そんな中、ロザリンドが「本当に浮気をくり返す男性は嫌ですわね」と言った。驚く私に「先ほどまで、その話をしていたのです」と微笑む。
その言葉は、浮気男に嫁いだ私への嫌みにも聞こえる。むしろ、今までの私ならそう受け取って激怒していたはず。
でも、シンシアはお茶会に行けば『アンジェリカ様の味方ができるかもしれませんよ』と言っていた。だとすれば、もしかして、これは……。
私は悩みながらもロザリンドに「その男性の妻は、どうしていたの?」と尋ねた。
「度重なる浮気に耐えかねて、神殿に入ったそうです」
「神殿に?」
「はい。神殿に入れば貴族であれ平民であれ、神の名のもとに平等です。一度、神殿に入った者を、何者であれ無理やり連れもどすことはできないのです」
「知らなかったわ」
「そうですね。私もつい最近まで知りませんでした。このことは、公(おおやけ)にはされていませんから」
「どうして?」
「神殿側が誰でも受け入れようとしているわけではなく、元から信仰心が高い者が、神殿に相談に来たときだけの例外的な対応なのです」
「本来は、信者を保護するためのものなのね。でも、神殿に入ってしまったら妻の生家には、迷惑はかからないの?」
ロザリンドは、静かに頷く。
「神殿では、病院や孤児院での奉仕活動、困窮者への炊き出しなど様々な活動を行っています。それらは、徳が高いことだとされていて、褒められはしても、生家が迷惑に思うことはありません」
「そう……」
ロザリンドは私をまっすぐ見つめた。
「王家は神殿に多額の寄付をしています。決して拒むことはないでしょう」
これはようするに、クルトとの結婚生活がつらかったら神殿に入りなさいということなのね?
そうすれば、王家に迷惑がかからないことを教えてくれている。私は気になっていたことを、ロザリンドに尋ねた。
「神殿に入れば、婚姻関係はなくなるの?」
「はい。洗礼を受ければ神の子になりますので、婚姻も解消されたことになります」
それなら、私と離婚したいというクルトの願いも叶う。
「分かったわ。ありがとう」
私がお礼を言うと、ロザリンドの瞳が見開かれた。14歳になったばかりの彼女は、まだどこかあどけなさを残している。
「ロザリンド。全部押しつけてごめんなさい。大変でしょう……?」
小さく首を振り、ロザリンドは少し困ったように微笑んだ。
「お姉様の大変さが、今になってようやく私にも分かってきたところです」