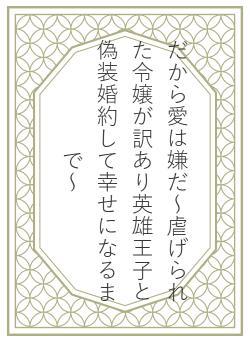和やかな晩餐が終われば、男女それぞれ別の部屋に分かれます。
テオドール様が言うには、こういう場合、男性たちはカードゲームで賭け事をすることもあるそうですが、今回は王宮なので軽くお酒を飲むだけになるとのこと。
女性たちは、別室でお茶会という名のウワサ話大会ですね。
どちらも重要な社交の場になるのでしょう。
テオドール様が心配そうな顔で私を見ています。
「シンシア様。王宮メイドに扮(ふん)したジーナが護衛しているとはいえ、くれぐれもお気をつけください」
「はい。テオドール様も」
テオドール様と別れた私は、事前にテオドール様から聞いていた言葉を思い出していました。
『この晩餐会の目的は、恐らくアンジェリカ様の救済だと思います』
その予想通り、国王陛下は皆の前でアンジェリカ様に謝罪しました。
たとえ親しい者たちしかいないにしても、一国の王が過ちを認めることは、なかなか許されません。しかし、そうすることで、陛下がアンジェリカ様を大切に思う気持ちが、参加者たちにも伝わったでしょう。
そんなアンジェリカ様を蔑(ないがし)ろにすることは、王家を軽んじていると同じこと。それを理解して、クルト様も浮気をやめて今後はアンジェリカ様を大切にしてくださったらいいのですが……。
そうすれば、アンジェリカ様と別れて私と結婚するなどというおかしな発想も出てきませんよね?
参加者たちがぞろぞろと別室に移動している中、後方にいたアンジェリカ様が、立ち止まってしまいました。不思議に思い見ていると、フラッと別方向に歩き出します。
「え?」
どうしよう……。ロザリンド様にお伝えしたいですが、彼女は参加者の女性たちを取り仕切る立場にあるので、この場を離れるわけにはいきません。
私は近くにジーナがいることを確認してから、アンジェリカ様のあとを追いました。ジーナはしっかりと私について来てくれています。
これなら危ないことにはならないですよね?
アンジェリカ様はフラフラしながら王宮庭園のほうに歩いていきました。
夜の庭園は、ところどころ明かりが灯されているものの暗くて怖いです。戻ろうかと思いましたが、こんなところにアンジェリカ様を一人で置いていけません。
「アンジェリカ様!」
声をかけるとアンジェリカ様は、ようやく立ち止まってくれました。振り返り私を見つめる瞳が、どこかうつろです。
「……シンシア? どうしてここに」
「アンジェリカ様がお一人で歩いていくのを見つけてしまい……」
「そう……。私についてきたのね」
そのときザァと風が吹いて、庭園内の草木を揺らしました。アンジェリカ様は、風で乱された赤い髪を優雅にかきあげます。
「……ねぇ、あなたに聞きたいことがあるんだけど」
「は、はい?」
「テオドールのこと、好きなのよね?」
「はい」
「それは、いつから?」
「いつから……? えっと、初めて出会ったときからです」
あれは忘れもしない王都で初めて社交パーティーに参加したときのこと。
とんでもない黒髪美青年がいるなと思っていたら、それがテオドール様でした。
「どうして?」
「ど、どうしてと言われましても……」
「だって、今のテオドールは美しいけど、あのときのテオドールはそうじゃなかったじゃない」
「え? テオドール様は初めて会ったときからずっと美しいですよ?」
アンジェリカ様は、私をまじまじと見てきます。
「どこに惹かれたのよ?」
「どこって……。サラサラな黒髪や誠実そうな佇まいとか。あっ、あと、瞳がルビーのように美しかったんです!」
少し目を見開いたアンジェリカ様は、「そう」と呟きました。
「私が今日になってやっと気がついたことに、あなたは初めから気がついていたのね……」
口元には自嘲のような笑みが浮かんでいます。
「あなたは見る目があるのね。私はぜんぜんダメだったわ。私は……どうしたら良かったの?」
アンジェリカ様の声は震えて、目にはうっすらと涙が浮かんでいます。
「私ね、幼いころからずっとお父様の言いなりで、自分で何かを決めたことがなかったの。テオドールが婚約者に決まったときも、私には事前に相談すらなかった」
この国の多くの貴族女性の結婚は、そうだと聞いています。恋愛小説でもそういう話が多いです。
そんな中、自由に相手が選べる私は、どれほど恵まれているのでしょうか。
アンジェリカ様は、深いため息をつきました。
「クルトと出会って恋に落ちて、この人なら私を幸せにしてくれると思ったの。だから、私はクルトを選んだ。初めてお父様の命令を無視して、自分の意見を通したわ」
「それがテオドール様との婚約破棄ですね……」
「そうよ。でも結果はこれ。ベイリー公爵家では冷遇されて、クルトは外に愛人を作りめったに家に帰って来ない。私の幸せなんかどこにもなかった」
アンジェリカ様は、まるで縋るように私の両肩に手を置きました。
「私はどうしたら良かったの? ねぇ、教えてよ……誰か、教えて……」
溢れた涙がアンジェリカ様の頬を伝って落ちていきます。
「アンジェリカ様……」
上手く話せるか分かりませんが、私は言葉を選びながら話しました。
「あの、私はずっと特別な誰かを選ばないようにしてきました」
専属メイドも、護衛騎士も私は選びませんでした。もし私が誰かを選んだら、その人はバルゴアに忠誠を誓い、私のために死ぬ覚悟を持たないといけないから。
「だから、アンジェリカ様がクルト様を選んだように、私もテオドール様が初めて自分で選んだ人なんです」
アンジェリカ様は静かに私の言葉に耳を傾けています。
「アンジェリカ様がどうしたら良かったのかは私にも分かりません。もし、テオドール様がクルト様のように浮気をしたら、悲しくてつらくて死にたくなると思います。すごく怒るし、テオドール様に暴言を吐いてしまうかも……」
想像しただけで胸が張り裂けてしまいそうなのに、アンジェリカ様は、これまでどれだけつらい思いをされていたのでしょうか。
浮気なんて、この世からなくなってしまえばいいのに。
「わ、分からないんですけど、私は、いつもテオドール様に幸せでいてほしいと願っています」
「幸せ……?」
そう呟いたアンジェリカ様は「クルトの幸せなんて、考えたことなかったわ」と続けます。
「私はずっと自分が幸せになりたくて、幸せにしてくれる男性を探していて……。どうしてなりたくもない女王にならないといけないのといつも嘆いて周囲を恨んで、他人の幸せなんて考えたことなかった。そっか、そうなのね。……ようやく分かった」
アンジェリカ様の表情は、どこか晴れ晴れとしていました。
テオドール様が言うには、こういう場合、男性たちはカードゲームで賭け事をすることもあるそうですが、今回は王宮なので軽くお酒を飲むだけになるとのこと。
女性たちは、別室でお茶会という名のウワサ話大会ですね。
どちらも重要な社交の場になるのでしょう。
テオドール様が心配そうな顔で私を見ています。
「シンシア様。王宮メイドに扮(ふん)したジーナが護衛しているとはいえ、くれぐれもお気をつけください」
「はい。テオドール様も」
テオドール様と別れた私は、事前にテオドール様から聞いていた言葉を思い出していました。
『この晩餐会の目的は、恐らくアンジェリカ様の救済だと思います』
その予想通り、国王陛下は皆の前でアンジェリカ様に謝罪しました。
たとえ親しい者たちしかいないにしても、一国の王が過ちを認めることは、なかなか許されません。しかし、そうすることで、陛下がアンジェリカ様を大切に思う気持ちが、参加者たちにも伝わったでしょう。
そんなアンジェリカ様を蔑(ないがし)ろにすることは、王家を軽んじていると同じこと。それを理解して、クルト様も浮気をやめて今後はアンジェリカ様を大切にしてくださったらいいのですが……。
そうすれば、アンジェリカ様と別れて私と結婚するなどというおかしな発想も出てきませんよね?
参加者たちがぞろぞろと別室に移動している中、後方にいたアンジェリカ様が、立ち止まってしまいました。不思議に思い見ていると、フラッと別方向に歩き出します。
「え?」
どうしよう……。ロザリンド様にお伝えしたいですが、彼女は参加者の女性たちを取り仕切る立場にあるので、この場を離れるわけにはいきません。
私は近くにジーナがいることを確認してから、アンジェリカ様のあとを追いました。ジーナはしっかりと私について来てくれています。
これなら危ないことにはならないですよね?
アンジェリカ様はフラフラしながら王宮庭園のほうに歩いていきました。
夜の庭園は、ところどころ明かりが灯されているものの暗くて怖いです。戻ろうかと思いましたが、こんなところにアンジェリカ様を一人で置いていけません。
「アンジェリカ様!」
声をかけるとアンジェリカ様は、ようやく立ち止まってくれました。振り返り私を見つめる瞳が、どこかうつろです。
「……シンシア? どうしてここに」
「アンジェリカ様がお一人で歩いていくのを見つけてしまい……」
「そう……。私についてきたのね」
そのときザァと風が吹いて、庭園内の草木を揺らしました。アンジェリカ様は、風で乱された赤い髪を優雅にかきあげます。
「……ねぇ、あなたに聞きたいことがあるんだけど」
「は、はい?」
「テオドールのこと、好きなのよね?」
「はい」
「それは、いつから?」
「いつから……? えっと、初めて出会ったときからです」
あれは忘れもしない王都で初めて社交パーティーに参加したときのこと。
とんでもない黒髪美青年がいるなと思っていたら、それがテオドール様でした。
「どうして?」
「ど、どうしてと言われましても……」
「だって、今のテオドールは美しいけど、あのときのテオドールはそうじゃなかったじゃない」
「え? テオドール様は初めて会ったときからずっと美しいですよ?」
アンジェリカ様は、私をまじまじと見てきます。
「どこに惹かれたのよ?」
「どこって……。サラサラな黒髪や誠実そうな佇まいとか。あっ、あと、瞳がルビーのように美しかったんです!」
少し目を見開いたアンジェリカ様は、「そう」と呟きました。
「私が今日になってやっと気がついたことに、あなたは初めから気がついていたのね……」
口元には自嘲のような笑みが浮かんでいます。
「あなたは見る目があるのね。私はぜんぜんダメだったわ。私は……どうしたら良かったの?」
アンジェリカ様の声は震えて、目にはうっすらと涙が浮かんでいます。
「私ね、幼いころからずっとお父様の言いなりで、自分で何かを決めたことがなかったの。テオドールが婚約者に決まったときも、私には事前に相談すらなかった」
この国の多くの貴族女性の結婚は、そうだと聞いています。恋愛小説でもそういう話が多いです。
そんな中、自由に相手が選べる私は、どれほど恵まれているのでしょうか。
アンジェリカ様は、深いため息をつきました。
「クルトと出会って恋に落ちて、この人なら私を幸せにしてくれると思ったの。だから、私はクルトを選んだ。初めてお父様の命令を無視して、自分の意見を通したわ」
「それがテオドール様との婚約破棄ですね……」
「そうよ。でも結果はこれ。ベイリー公爵家では冷遇されて、クルトは外に愛人を作りめったに家に帰って来ない。私の幸せなんかどこにもなかった」
アンジェリカ様は、まるで縋るように私の両肩に手を置きました。
「私はどうしたら良かったの? ねぇ、教えてよ……誰か、教えて……」
溢れた涙がアンジェリカ様の頬を伝って落ちていきます。
「アンジェリカ様……」
上手く話せるか分かりませんが、私は言葉を選びながら話しました。
「あの、私はずっと特別な誰かを選ばないようにしてきました」
専属メイドも、護衛騎士も私は選びませんでした。もし私が誰かを選んだら、その人はバルゴアに忠誠を誓い、私のために死ぬ覚悟を持たないといけないから。
「だから、アンジェリカ様がクルト様を選んだように、私もテオドール様が初めて自分で選んだ人なんです」
アンジェリカ様は静かに私の言葉に耳を傾けています。
「アンジェリカ様がどうしたら良かったのかは私にも分かりません。もし、テオドール様がクルト様のように浮気をしたら、悲しくてつらくて死にたくなると思います。すごく怒るし、テオドール様に暴言を吐いてしまうかも……」
想像しただけで胸が張り裂けてしまいそうなのに、アンジェリカ様は、これまでどれだけつらい思いをされていたのでしょうか。
浮気なんて、この世からなくなってしまえばいいのに。
「わ、分からないんですけど、私は、いつもテオドール様に幸せでいてほしいと願っています」
「幸せ……?」
そう呟いたアンジェリカ様は「クルトの幸せなんて、考えたことなかったわ」と続けます。
「私はずっと自分が幸せになりたくて、幸せにしてくれる男性を探していて……。どうしてなりたくもない女王にならないといけないのといつも嘆いて周囲を恨んで、他人の幸せなんて考えたことなかった。そっか、そうなのね。……ようやく分かった」
アンジェリカ様の表情は、どこか晴れ晴れとしていました。