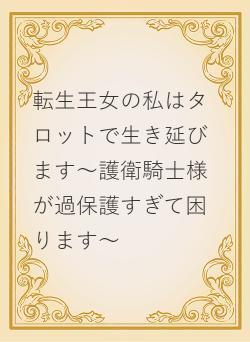「これはどういうことだ! カティア・イーリィ」
庭園内にあるガゼボに向かって、銀髪の男が叫んでいた。幼なじみのスティグ・ギルズ伯爵令息である。
「何が、でしょうか」
私は椅子に座ったまま、静かに答える。後ろから聞こえてきた怒声に、振り向く素振りすら見せず、必死に平静を装っていた。が、内心はどうしよう、と冷や汗ものだった。
だって仕方がないじゃない。私がカティア・イーリィではないことがバレたら、大変なことになってしまうんだから。スティグがやってきた理由も合わせて……。
あー! これをどうしろっていうのよー!!
ついにやってきてしまった非常事態に、私はいっぱいいっぱいになり、頭を抱えたくなった。けれど今はそんな態度は取れない。
なにせ、相手は幼なじみ。カティアの性格を知り尽くしているのだ。もしも私が想定外の行動を取ったらどう思うだろうか。
具合が悪いのかな。虫の居所でも悪い? そんな希望的観測をしてくれる人ならいいけれど……さすがに都合が良すぎるでしょう。
今度はため息を吐きたくなったが、それもまたできなかった。
スティグはカティアのことを知っているが、私の方はというと……全く知らないのだ。微塵も、欠片も記憶にないのよーーー!!
何で、どうして? こういう転生、憑依にはあるのがお約束でしょう。なくてもほら、この世界がゲームか小説か漫画の中とか……そんな予備知識も用意してくれないなんて……。
ちょっと酷いんじゃないのーーー!! これじゃ、私がカティアじゃないって、すぐにバレちゃうじゃない!
誰か! 責任者、出て来て! そして私を今すぐ助けてー!
***
事の起こりは、一週間前に遡る。
余命三カ月の宣告を受けて、ほんの数日延命した後、旅立った私は天国へ行かず、何故か目を覚ました。
全く別の世界の見知らぬ部屋に。カティア・イーリィという伯爵令嬢の体で。
よくある異世界転生だと思った。もしくは憑依。だから許容範囲内だった。私の身にも起こったんだな程度のことで、処理した。途端、問題が発生する。そう、ここがどこなのか分からないことだった。
私は生前、ゲームや小説、漫画をよく読んでいた方だけど、カティア・イーリィという名に全く身に覚えがない。
頭を一生懸命、捻っても分からないという、この事態!
これから一体、どう対処すれば良いの……。しかも突然、貴族だなんて……。む、無理がある。
私は途方に暮れながらも、なってしまったものは仕方がない、とカティアの体で現状を受け入れようとしていた。そんな矢先、さらなる問題が発生してしまったのだ。
そう。それが今、後ろにいるスティグ・ギルズだ。彼がやってきたのは、恐らくアレが原因だろう。
「えっ! 求婚書?」
なんと転生して早々、カティアに求婚書が来ているのだという。父親だという人に呼ばれて、執務室にある椅子に座ると、すぐに話を切り出された。
はて、何のことでしょうか?
「冗談……では、ない?」
「我が家に娘は一人しかいないのだから、他に誰がいる。ロレッタは私の妻なのだから、送ってくる愚か者はいない。よってイーリィ伯爵家に送られてきた求婚書は、すべてカティア宛になるのだ」
「え、一人……? 私、宛て?」
嘘。本当に? それこそ、冗談でしょう。
確かにこの体になってから、家族らしい人に会ったのは、目の前にいるこの父親だけ。といっても、まだ数時間しか経っていないのだから、無理もない。
それでも、私の世話をしてくれているメイドのメイに、それとなく聞くことだってできたはずなのに……。いくら混乱していたからって、こんな重要なことを確認し忘れるなんて〜。
わー! 私のバカバカバカ。大バカ者ー!
「大丈夫か、カティア。急に青ざめて……」
心配する声にハッとなる。顔をあげてよく見ると、父親だという人の顔がみるみる内に変化していった。驚きと、不快感に近い表情へと。
こ、これは不味い……!
「実はここに来る前から気分が悪くて……でも、お父様からの呼び出しだったので、無理をしてでも来たんです。とても重要なお話だと思いまして」
父親との会話でも、お貴族様は敬語で話をするものだと、前世の知識をフル動員して答えた。というよりも初対面で尚且つ、年上の男性にタメ口はさすがに……言える勇気はない。
「カティア。そういうことは先に言いなさい。求婚書など、後回しにでもできるのだから」
「ありがとうございます」
紫色の髪の奥から覗く、青い瞳が心配そうに私を見つめる。その眼差しを見て、この体の持ち主であるカティアが、思った以上に大事にされていることが分かった。
転生してから家族に会わなかったのは、偶々だったのかもしれない。何か事情があったんだろう。
たとえば、忙しかったから、とか。夜に呼び出すのがいい証拠だった。
「本当に具合が悪いようだ。カティアが私に敬語など……」
「え? それは……」
お貴族様だから……というのはあくまでも一般論。タメ口の家庭だって存在するだろう。色々な家庭事情があるんだから。
でもまさか、イーリィ伯爵家がそうだなんて……聞いてない! だからといってタメ口は……無理!
「……色々と緊張してしまって」
「ふむ。年頃になれば、求婚書や釣書が届くのが当たり前なんだが、そうか。カティアにはまだ早かったか」
「いえ、そういうわけではなく。その……相手が誰だかも分からないのに、求婚書だなんて。それを考えただけで、ちょっと……」
怖かった。転生してすぐに見知らぬ相手と結婚なんて……無理無理。あり得ない。
「そうか。しかし相手はスティグ・ギルズ伯爵令息だぞ。問題なかろう」
「と言われましても……好きでもない人と結婚なんてできません」
「……もう一度言うが、相手はスティグだぞ?」
「無理です」
この時、私はキッパリと答えた。
相手のことを確認している余裕なんてない。目の前にいる父親が驚いている顔も、勿論のこと。自分とその心を守るのに必死だったのだ。
庭園内にあるガゼボに向かって、銀髪の男が叫んでいた。幼なじみのスティグ・ギルズ伯爵令息である。
「何が、でしょうか」
私は椅子に座ったまま、静かに答える。後ろから聞こえてきた怒声に、振り向く素振りすら見せず、必死に平静を装っていた。が、内心はどうしよう、と冷や汗ものだった。
だって仕方がないじゃない。私がカティア・イーリィではないことがバレたら、大変なことになってしまうんだから。スティグがやってきた理由も合わせて……。
あー! これをどうしろっていうのよー!!
ついにやってきてしまった非常事態に、私はいっぱいいっぱいになり、頭を抱えたくなった。けれど今はそんな態度は取れない。
なにせ、相手は幼なじみ。カティアの性格を知り尽くしているのだ。もしも私が想定外の行動を取ったらどう思うだろうか。
具合が悪いのかな。虫の居所でも悪い? そんな希望的観測をしてくれる人ならいいけれど……さすがに都合が良すぎるでしょう。
今度はため息を吐きたくなったが、それもまたできなかった。
スティグはカティアのことを知っているが、私の方はというと……全く知らないのだ。微塵も、欠片も記憶にないのよーーー!!
何で、どうして? こういう転生、憑依にはあるのがお約束でしょう。なくてもほら、この世界がゲームか小説か漫画の中とか……そんな予備知識も用意してくれないなんて……。
ちょっと酷いんじゃないのーーー!! これじゃ、私がカティアじゃないって、すぐにバレちゃうじゃない!
誰か! 責任者、出て来て! そして私を今すぐ助けてー!
***
事の起こりは、一週間前に遡る。
余命三カ月の宣告を受けて、ほんの数日延命した後、旅立った私は天国へ行かず、何故か目を覚ました。
全く別の世界の見知らぬ部屋に。カティア・イーリィという伯爵令嬢の体で。
よくある異世界転生だと思った。もしくは憑依。だから許容範囲内だった。私の身にも起こったんだな程度のことで、処理した。途端、問題が発生する。そう、ここがどこなのか分からないことだった。
私は生前、ゲームや小説、漫画をよく読んでいた方だけど、カティア・イーリィという名に全く身に覚えがない。
頭を一生懸命、捻っても分からないという、この事態!
これから一体、どう対処すれば良いの……。しかも突然、貴族だなんて……。む、無理がある。
私は途方に暮れながらも、なってしまったものは仕方がない、とカティアの体で現状を受け入れようとしていた。そんな矢先、さらなる問題が発生してしまったのだ。
そう。それが今、後ろにいるスティグ・ギルズだ。彼がやってきたのは、恐らくアレが原因だろう。
「えっ! 求婚書?」
なんと転生して早々、カティアに求婚書が来ているのだという。父親だという人に呼ばれて、執務室にある椅子に座ると、すぐに話を切り出された。
はて、何のことでしょうか?
「冗談……では、ない?」
「我が家に娘は一人しかいないのだから、他に誰がいる。ロレッタは私の妻なのだから、送ってくる愚か者はいない。よってイーリィ伯爵家に送られてきた求婚書は、すべてカティア宛になるのだ」
「え、一人……? 私、宛て?」
嘘。本当に? それこそ、冗談でしょう。
確かにこの体になってから、家族らしい人に会ったのは、目の前にいるこの父親だけ。といっても、まだ数時間しか経っていないのだから、無理もない。
それでも、私の世話をしてくれているメイドのメイに、それとなく聞くことだってできたはずなのに……。いくら混乱していたからって、こんな重要なことを確認し忘れるなんて〜。
わー! 私のバカバカバカ。大バカ者ー!
「大丈夫か、カティア。急に青ざめて……」
心配する声にハッとなる。顔をあげてよく見ると、父親だという人の顔がみるみる内に変化していった。驚きと、不快感に近い表情へと。
こ、これは不味い……!
「実はここに来る前から気分が悪くて……でも、お父様からの呼び出しだったので、無理をしてでも来たんです。とても重要なお話だと思いまして」
父親との会話でも、お貴族様は敬語で話をするものだと、前世の知識をフル動員して答えた。というよりも初対面で尚且つ、年上の男性にタメ口はさすがに……言える勇気はない。
「カティア。そういうことは先に言いなさい。求婚書など、後回しにでもできるのだから」
「ありがとうございます」
紫色の髪の奥から覗く、青い瞳が心配そうに私を見つめる。その眼差しを見て、この体の持ち主であるカティアが、思った以上に大事にされていることが分かった。
転生してから家族に会わなかったのは、偶々だったのかもしれない。何か事情があったんだろう。
たとえば、忙しかったから、とか。夜に呼び出すのがいい証拠だった。
「本当に具合が悪いようだ。カティアが私に敬語など……」
「え? それは……」
お貴族様だから……というのはあくまでも一般論。タメ口の家庭だって存在するだろう。色々な家庭事情があるんだから。
でもまさか、イーリィ伯爵家がそうだなんて……聞いてない! だからといってタメ口は……無理!
「……色々と緊張してしまって」
「ふむ。年頃になれば、求婚書や釣書が届くのが当たり前なんだが、そうか。カティアにはまだ早かったか」
「いえ、そういうわけではなく。その……相手が誰だかも分からないのに、求婚書だなんて。それを考えただけで、ちょっと……」
怖かった。転生してすぐに見知らぬ相手と結婚なんて……無理無理。あり得ない。
「そうか。しかし相手はスティグ・ギルズ伯爵令息だぞ。問題なかろう」
「と言われましても……好きでもない人と結婚なんてできません」
「……もう一度言うが、相手はスティグだぞ?」
「無理です」
この時、私はキッパリと答えた。
相手のことを確認している余裕なんてない。目の前にいる父親が驚いている顔も、勿論のこと。自分とその心を守るのに必死だったのだ。